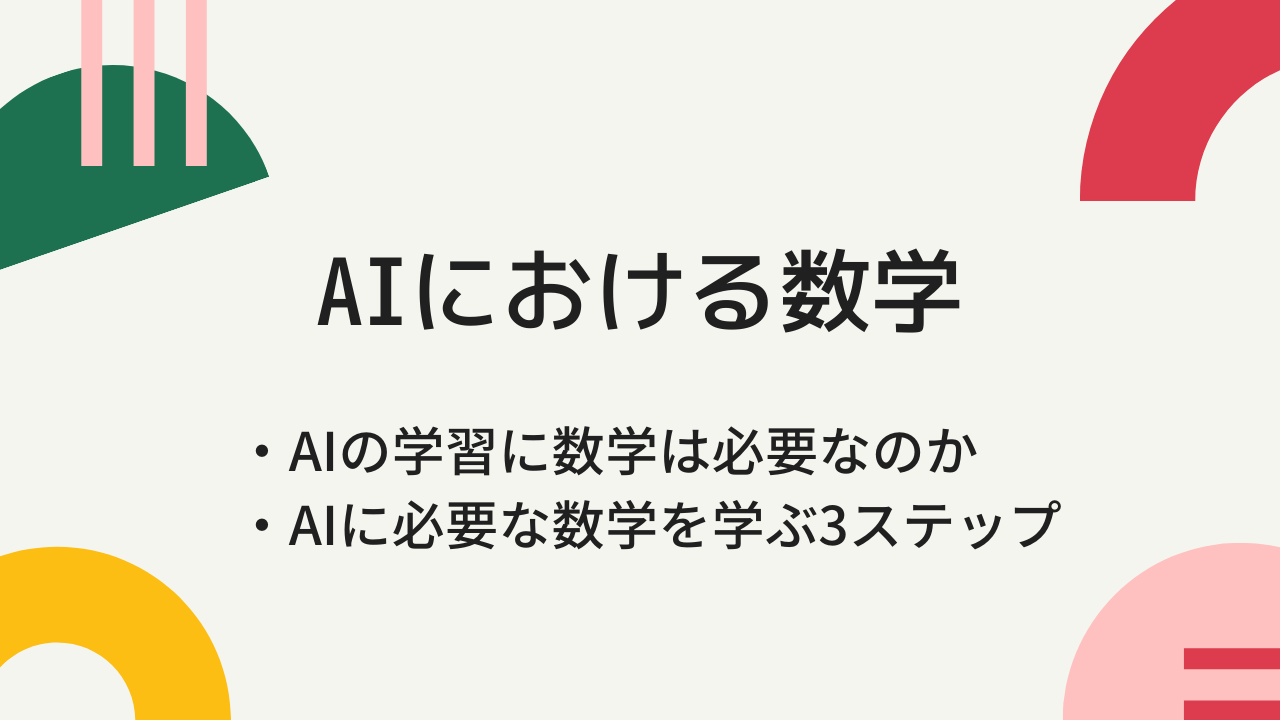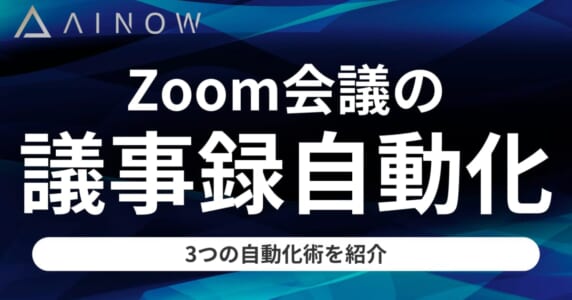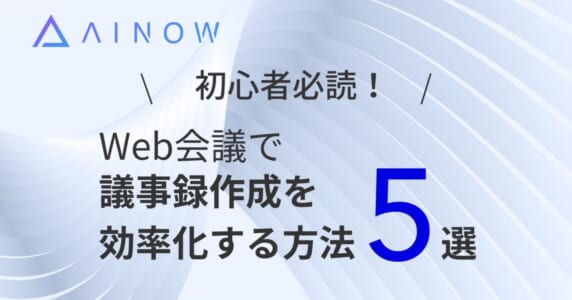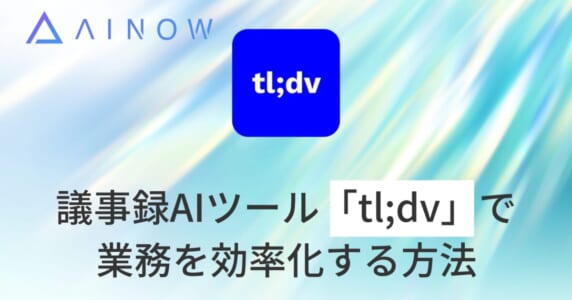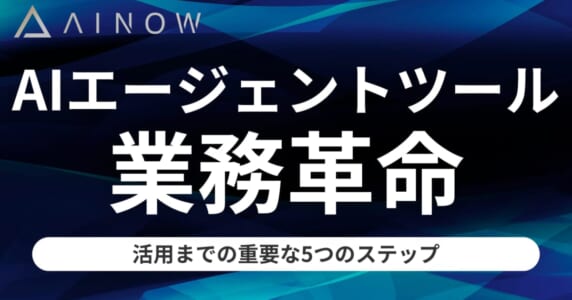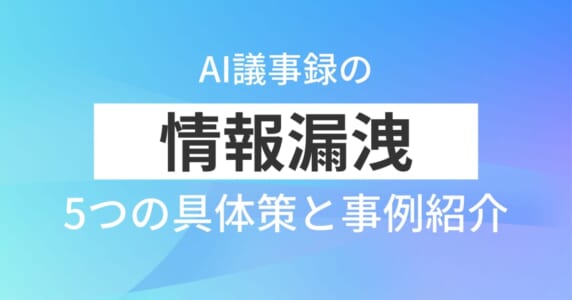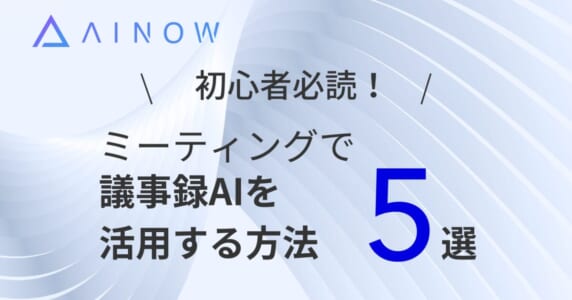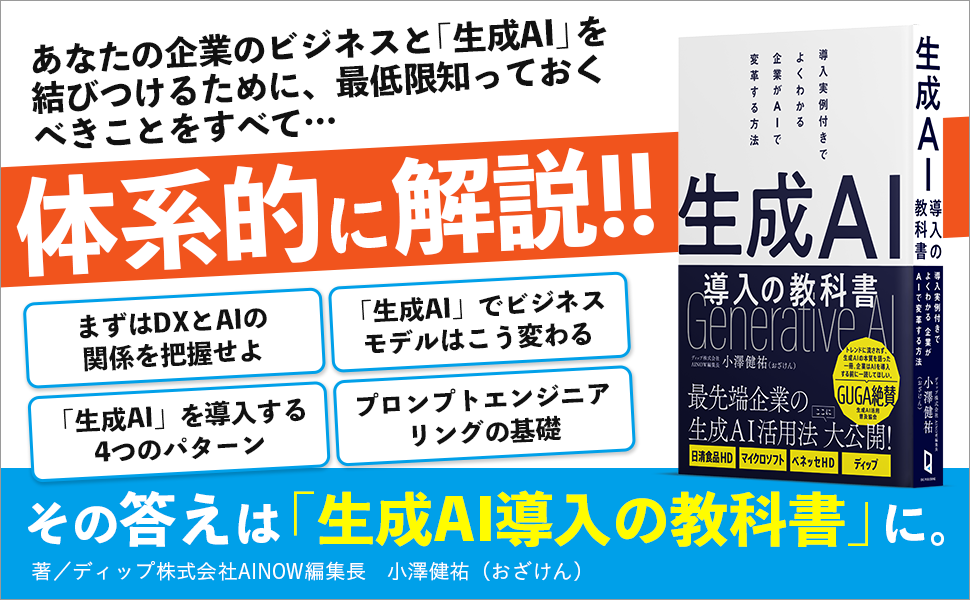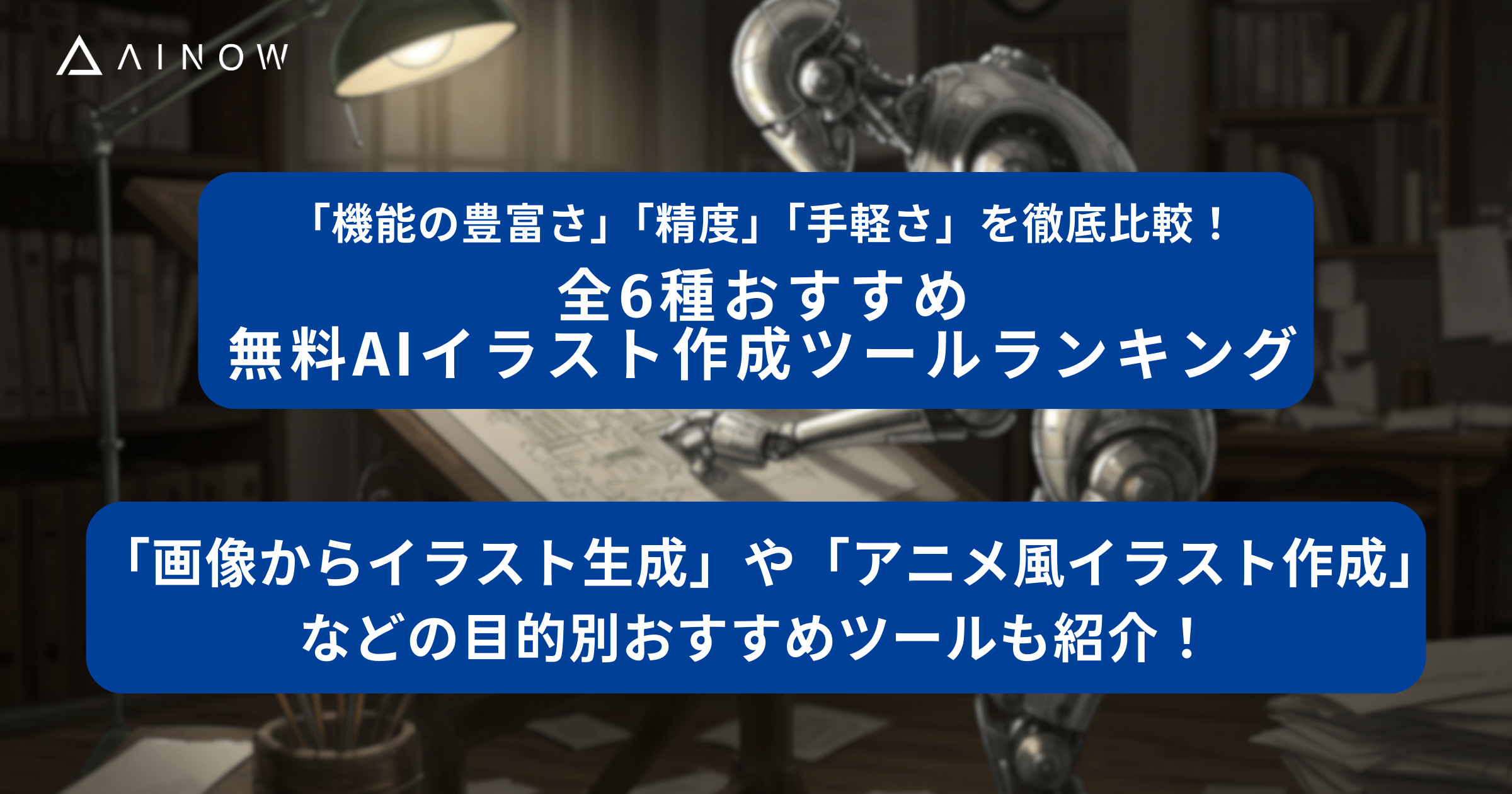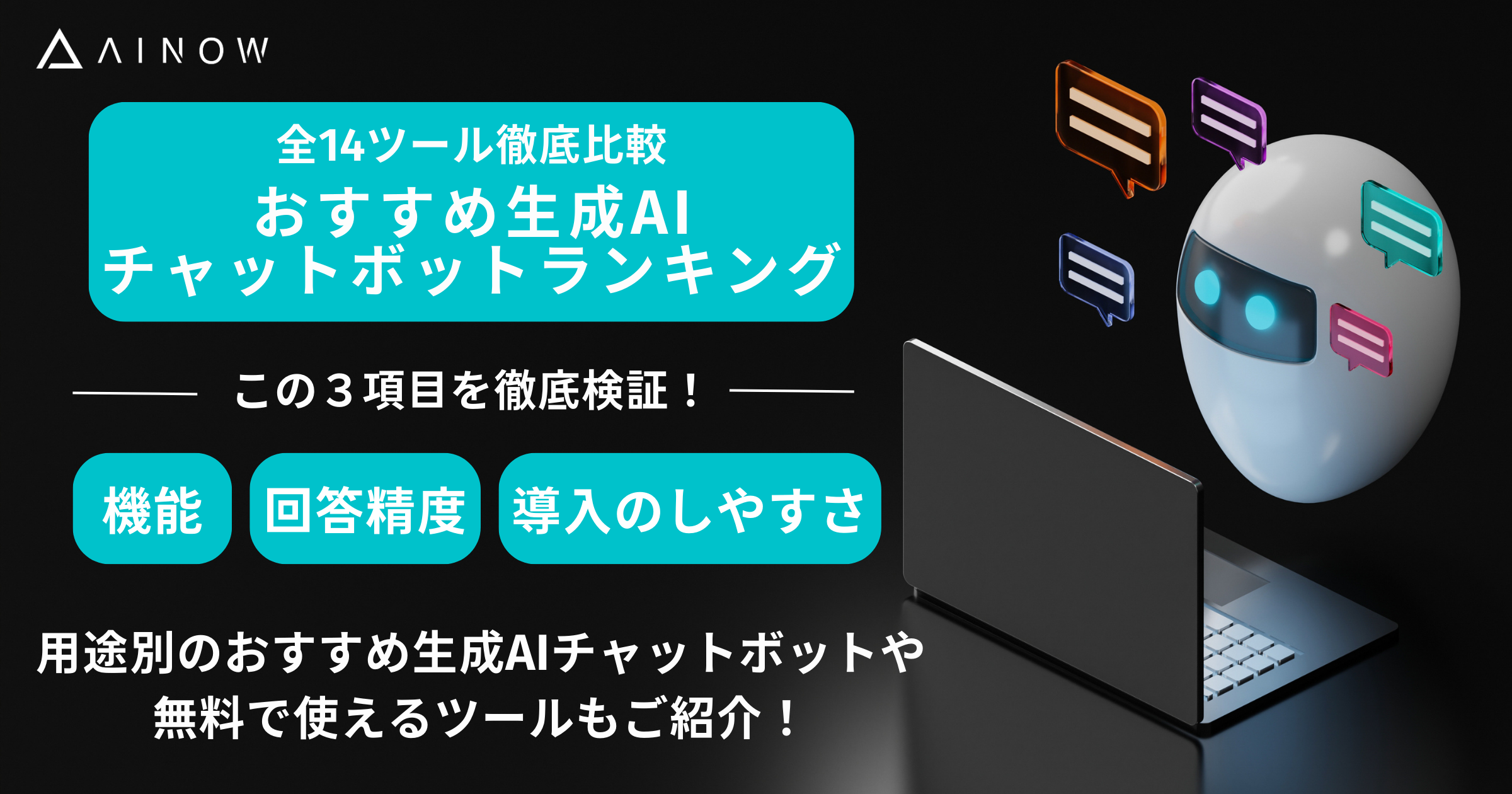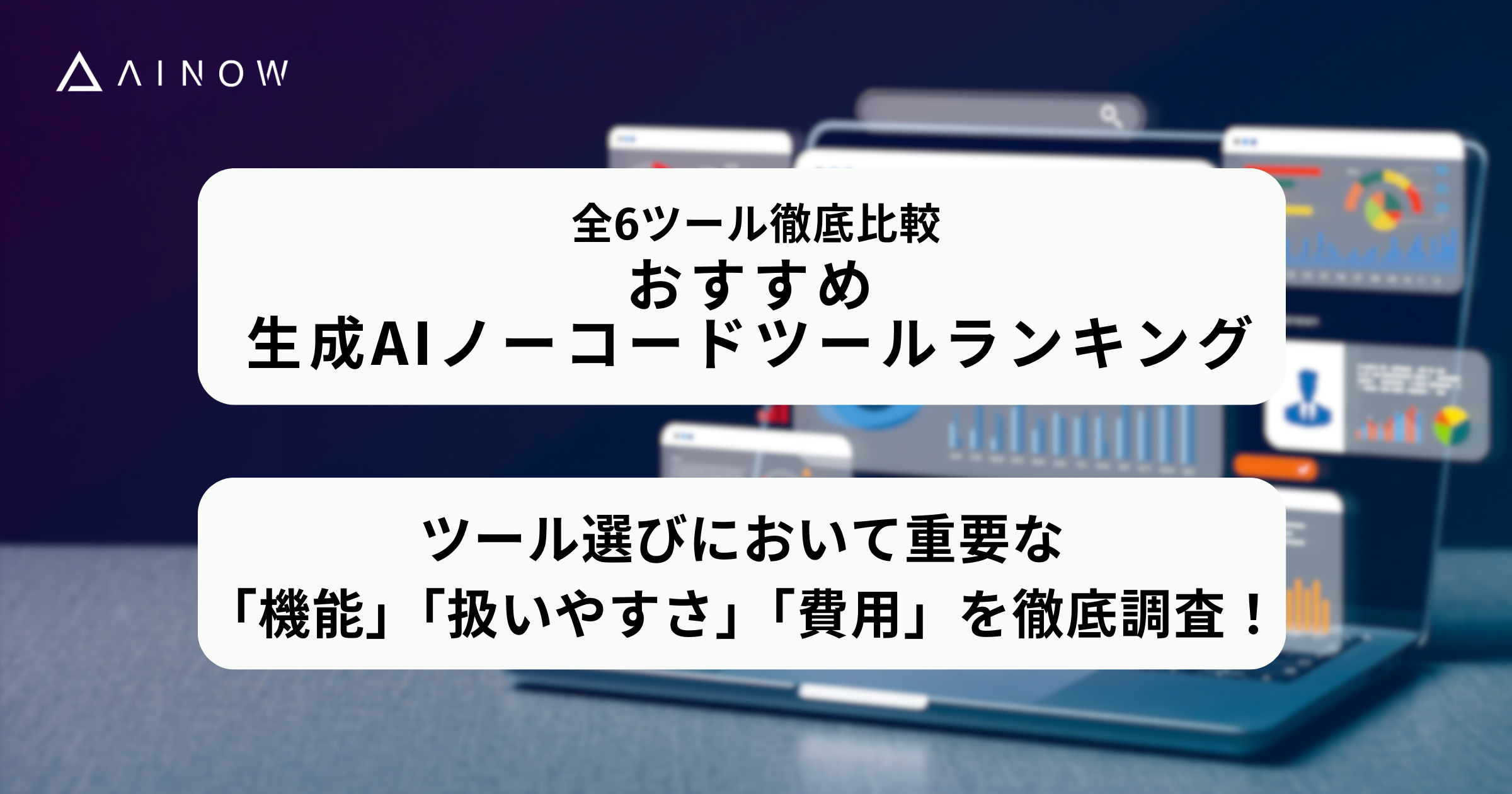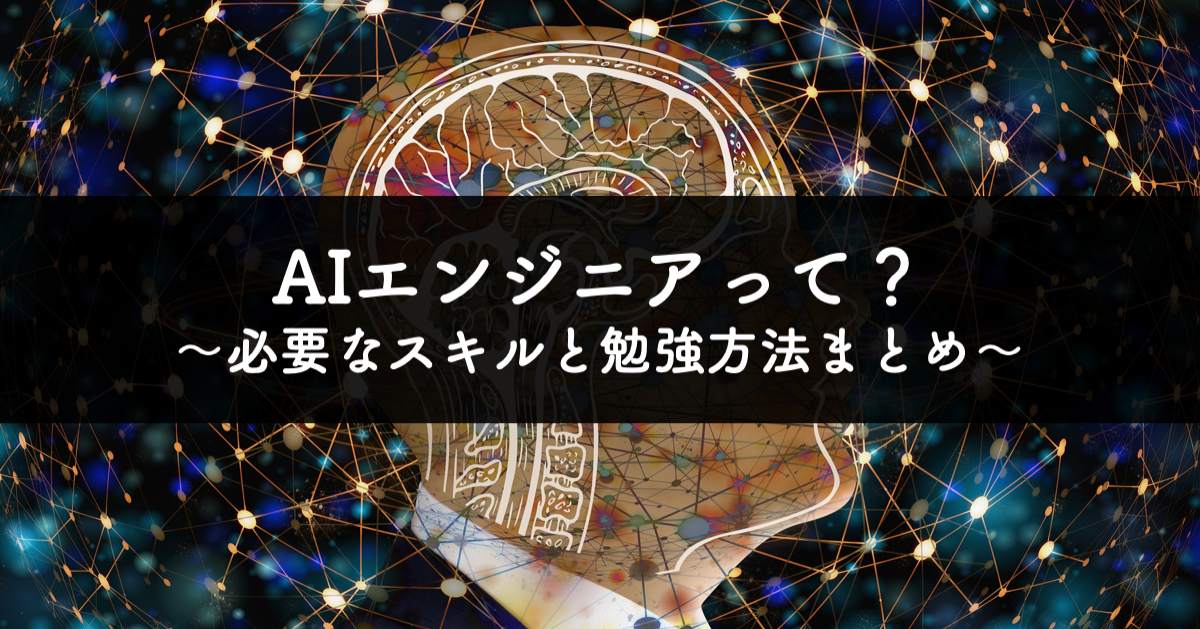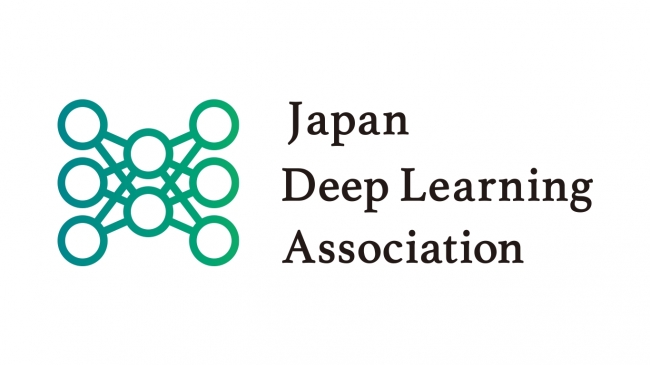近年、エンジニア不足を解消するために手動でコーディングしない、または工数を減らすシステムが開発されています。
今回はその中でもローコード開発ツールについて、また「ローコード」と「ノーコード」の違いをご紹介します。
目次
ローコードとは
ローコードとは、できるだけコード作成量を抑えて、少ないコードでアプリケーションを開発できるツール・手法です。
一昔前までは「高速開発」や「超高速開発」と呼ばれていましたが、近年「ローコード開発」と呼ばれ、昨今ではさらに工数を減らすだけでなくコード作成作業を必要としない「ノーコード」と呼ばれるツールも登場しました。
さまざまな開発プラットフォームやツールを組み合わせることで、「ローコード開発」や「ノーコード開発」が可能になります。
従来のようにプログラミング言語の知識を持つエンジニアにアプリケーションの開発を一任するのではなく、ビジネス側の役割を担いつつ技術面にも精通した人がコードを書かずに視覚的にアプリ開発に携われます。
「ローコード」「ノーコード」が求められる理由
現在、日本は大きなITの課題に直面しています。
経済産業省が発行する「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」にも、「2025年の崖」と記されているように、多くの企業がDXの推進を妨げる課題を抱えています。大まかな課題は以下の通りです。
- 既存のシステムが事業部門ごとに構築されていることにより、各レガシーシステムが管理しきれない状態(ブラックボックス状態)に陥ってしまい、データを上手く活用できずDX化が思うように推進できていない。
- 2015年時点では17万人だったIT人材不足が2025年には43万人にまで拡大する恐れがある。
- ユーザーである企業が、ベンダーである企業に丸投げしてしまっているがゆえに、システムがブラックボックス化が進行してしまう。またこのことに起因し、保守費用の増大にも繋がる。
以上の課題は誰でも開発者になれる「ローコード」開発ツールや「ノーコード」開発ツールを活用すると、組織ごとのよりニーズにあったアプリケーションを開発できるため、組織の課題を解消し、生産力の向上に大きな効果をもたらせます。
「ローコード」と「ノーコード」の違い
「ローコード(Low Code)」と「ノーコード(No Code)」の違いは、その名の通り「ローコード」は少ないプログラムコードで、「ノーコード」はプログラムコードなしでシステムを構築できるという違いがあります。
ローコードが必要な理由・ノーコードとの違い
また「ローコード」と「ノーコード」には対応できるアプリケーションの規模の違いもあります。
もっとも大きな違いは「ツールの対応規模」です。
「ノーコード」は基本的には1つの部署で使う小さなアプリケーションの構築に適しています。
しかし多くの「ノーコード」ツールは機能が限られていることが多く、企業規模が拡大した際に多くの課題が発生します。
考えられる課題
アーキテクチャという用語は、変数や関数、アルゴリズムをどのように組み合わせるかなどのプログラミングの構造を意味します。 多くのノーコードツールは、柔軟性がなく単純なアプリケーションアーキテクチャーになる可能性があります。
利用者の使い心地や操作性(ユーザーエクスペリエンス・UX)に重きを置いた開発が出来ず、従来のシステムに接続できません。 また他社システムや自社製システムのソリューションとの統合が困難です。
ノーコードで開発されたアプリケーションは、スタンドアロン(システムがネットワークや他の機器に接続せず、単独で動作している)状態のため、ガバナンス面における管理課題が挙げられます。 |
「ノーコード」に比べて「ローコード」は、拡張性に優れ環境対応が柔軟であるため幅広い場面で活用できます。
またローコード導入のメリットは以下の通りです。
ローコードを導入するメリット
ローコードツールを導入することで、コードを一から全て作成する必要がないため、プログラマーの工数を削減でき、作業時間の短縮を図れます。 また開発にかかる人件費や開発コストを抑えられます。
システムの提供者(ベンダー)がセキュリティ対策したうえで提供しているものなので、セキュリティ面での不安がありません。 そのため、開発者は自身で新たに構築した箇所のみにセキュリティ対応するだけで済みます。 |
ローコード選定ポイント
①事業ごとの「個別最適」ではなく、組織としての「全体最適」であること
それぞれ個人の部門や事業部で「個別最適」なツールを導入してしまうと、組織全体としてシステムを管理しきれずブラックボックス化してしまいます。
ブラックボックス化によるデータとプロセスの分断を避けるためにも、組織としての「全体最適」を目指すツールを選びましょう。
②IDや権限管理が適切にできる
企業において、ID管理はセキュリティ面での大きな判断基準となり得ます。
標準的なシングルサインオン(SSO)機能(SSO機能:1度ユーザー認証 (ログイン) することで、紐づけられているシステム・サービスを追加の認証なしで利用できる機能)やその他機能を搭載しているか確認しましょう。
また同様に、権限管理も重要なファクターです。役職ごとに権限に制限をかける機能や、組織に関する権限をコントロールできる機能を搭載したツールであるかを確認しましょう。
③複雑な業務プロセスにも柔軟に対応できる
集団で方針を決める合議(並列承認)や条件分岐、異なるワークフローとの連携など柔軟な設定が可能かを確認しましょう。
④業務監査をできる仕組みが整っている
業務プロセスが複雑かつ重要になるほど、誰がいつ承認したかのログを正しく取得し管理する必要があります。
そのため、監査ログを適切に取得できる仕組みが整っているかを確認しましょう。
⑤機能拡張に伴う運用負荷に耐えられる「スケーラビリティ」を有している
③でも述べた通り、「ローコード」開発ツールには柔軟性が求められます。
大企業で開発プラットフォームを利用する際、短期間のうちに莫大な数の業務とデータベースが構築され、多くの機能拡張がなされます。その膨大な運用負荷に耐えうるスケーラビリティが必要です。
⑥操作性
組織全体で「ローコード」や「ノーコード」を導入し、デジタルシフトを図るうえで、ツールの操作性は重要なファクターになります。
なるべくツール活用までの教育コストがかからない、簡単に・誰にでも使える「ローコード」開発ツールを選びましょう。
導入事例
株式会社SUBARU(スバル)
新型コロナウイルス感染症の影響で制限が出たサプライヤーとの情報連携のために、ローコード開発によってサプライヤー向けのポータルサイトを作成しました。
これによって、コロナウイルスによる影響を軽減できました。
三井物産リアルティ・マネジメント株式会社
三井不動産リアルティは、各部門がシステム部門の承認を得ずにアプリケーションを導入するのを防ぐためにローコード開発を活用しています。
2014年に社員が独断で導入した300ものシステムを廃止し、自作ツールを作り直すことで、稼働状況・メンテナンスを一元化しました。
まとめ
今回はローコード開発ツールについて解説しました。
ローコードツールはエンジニアが減少している現代において、簡単にシステム・アプリケーションを開発できるツールです。
組織のシステム構築のためにも、導入を検討しましょう。