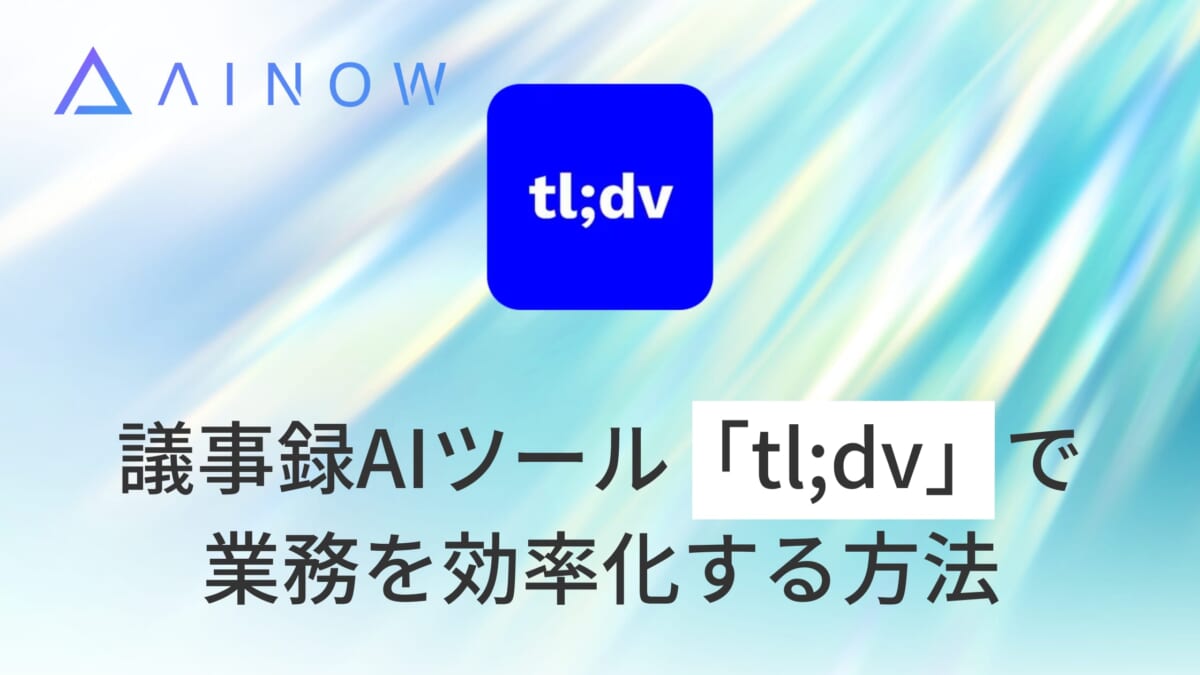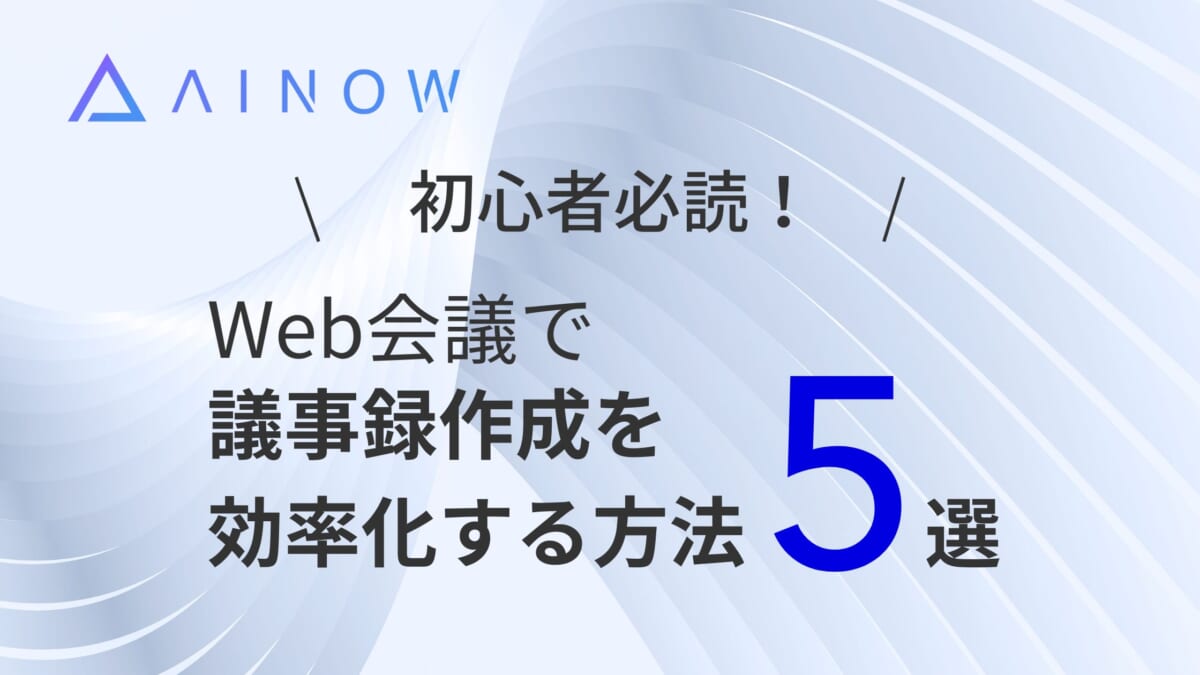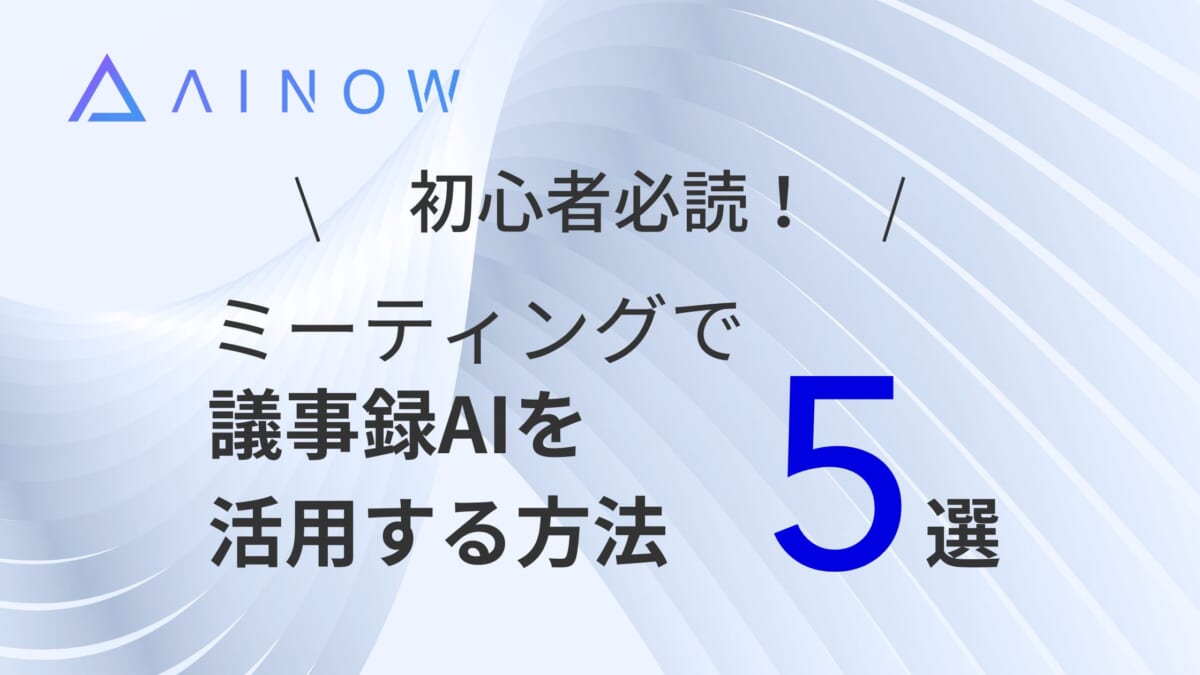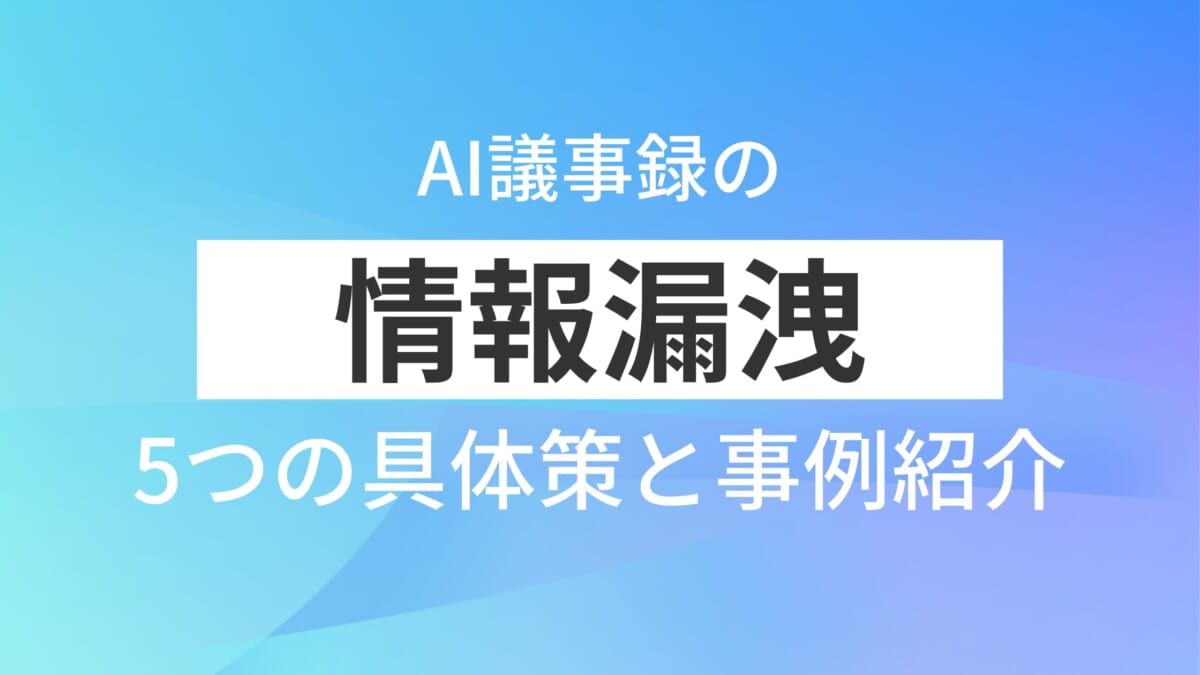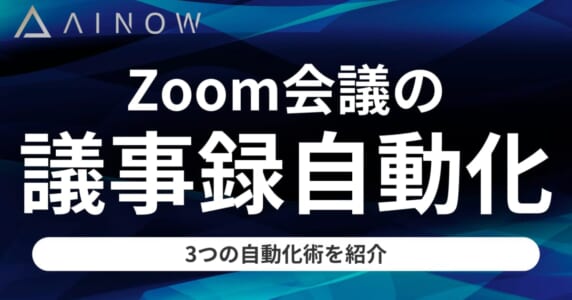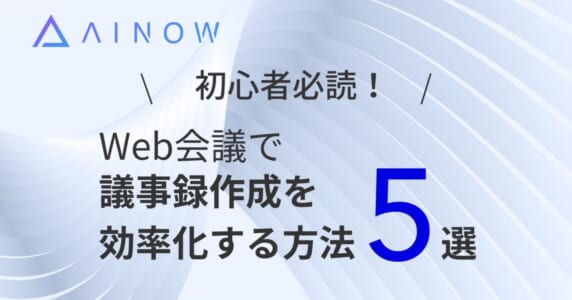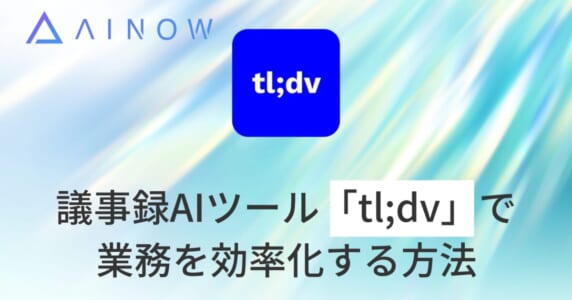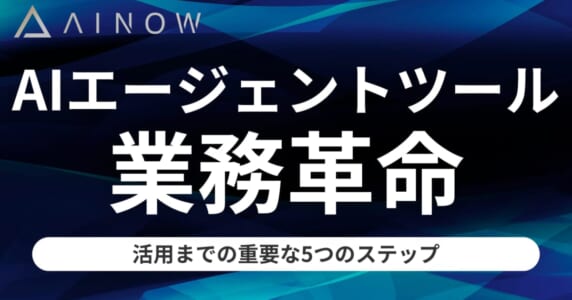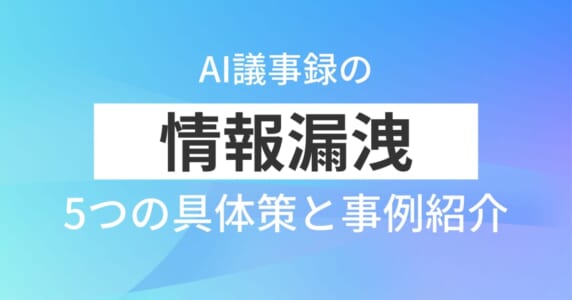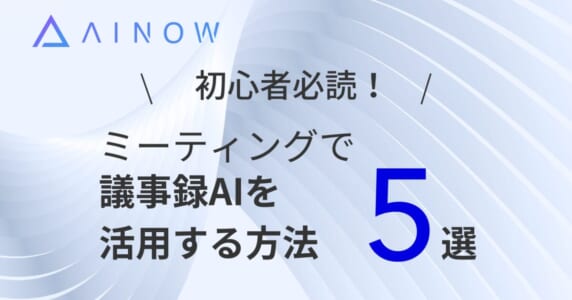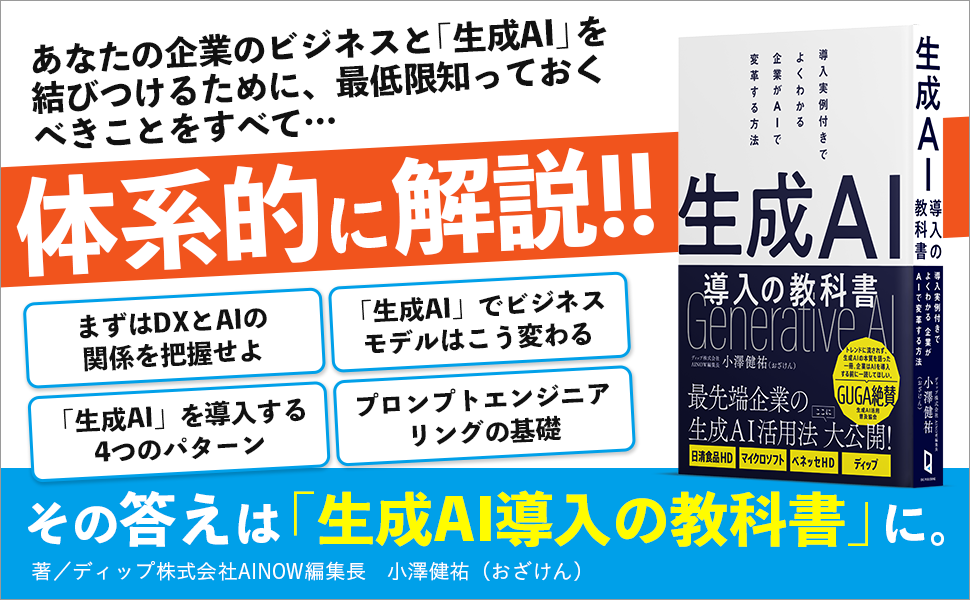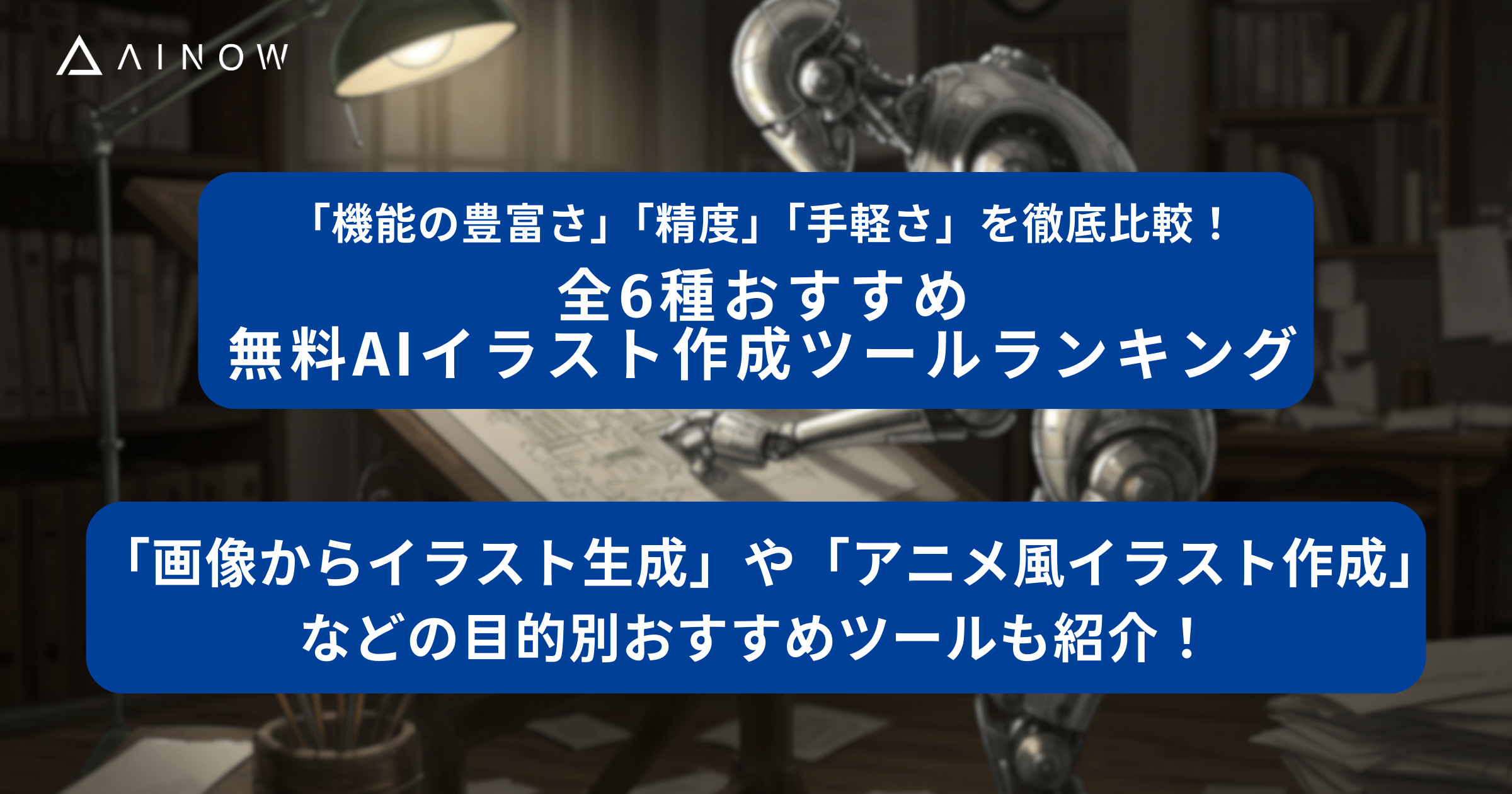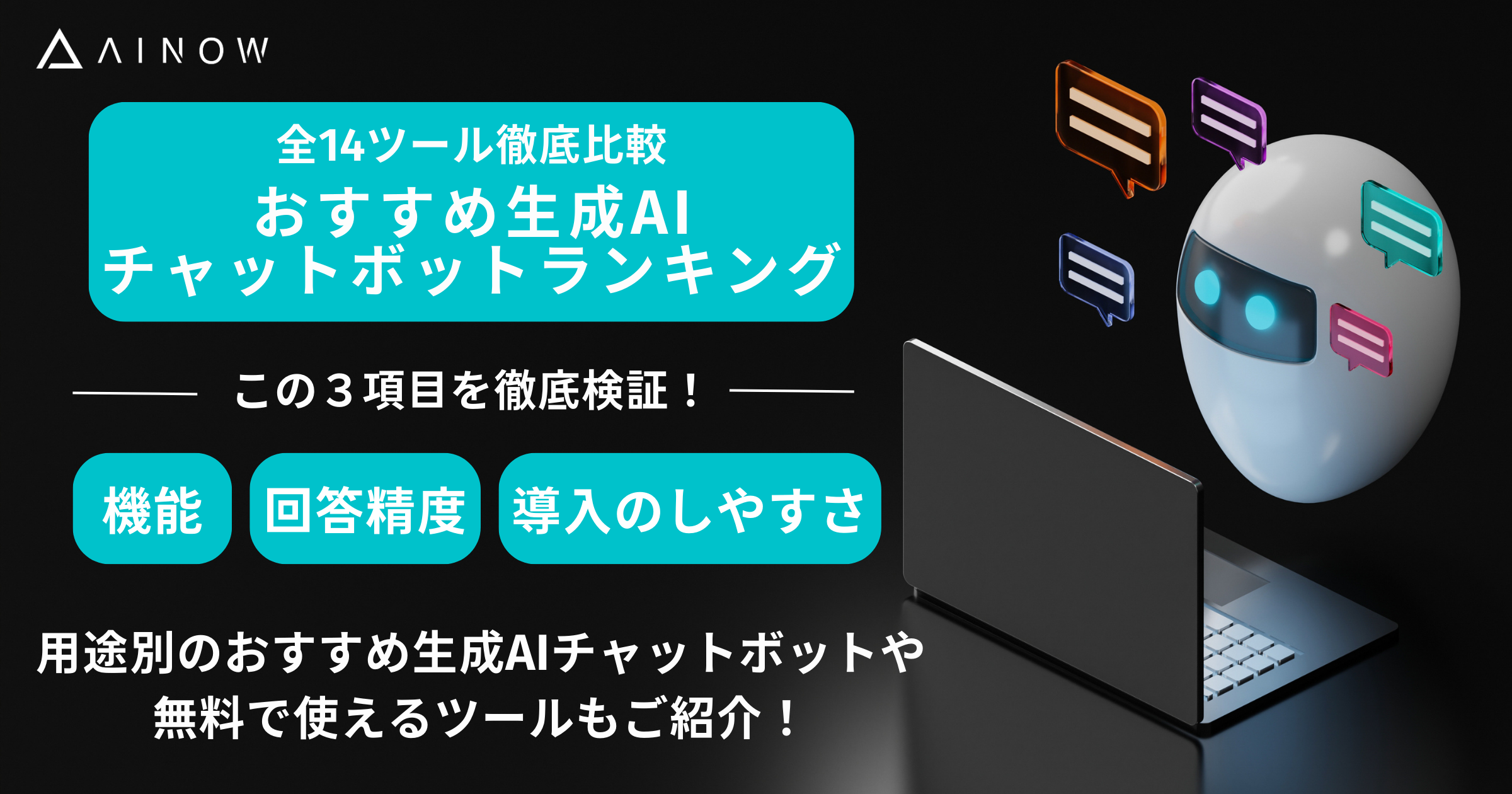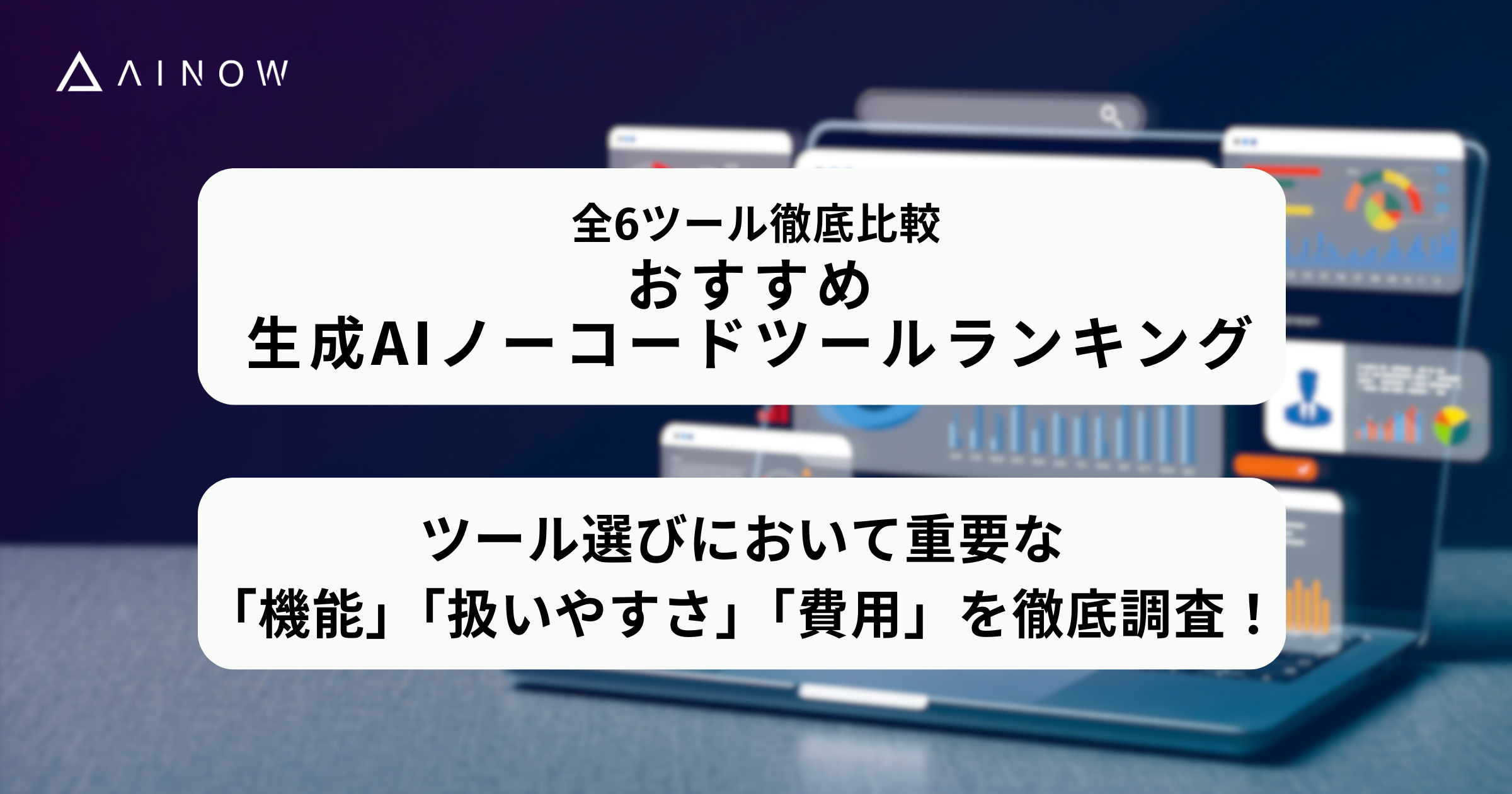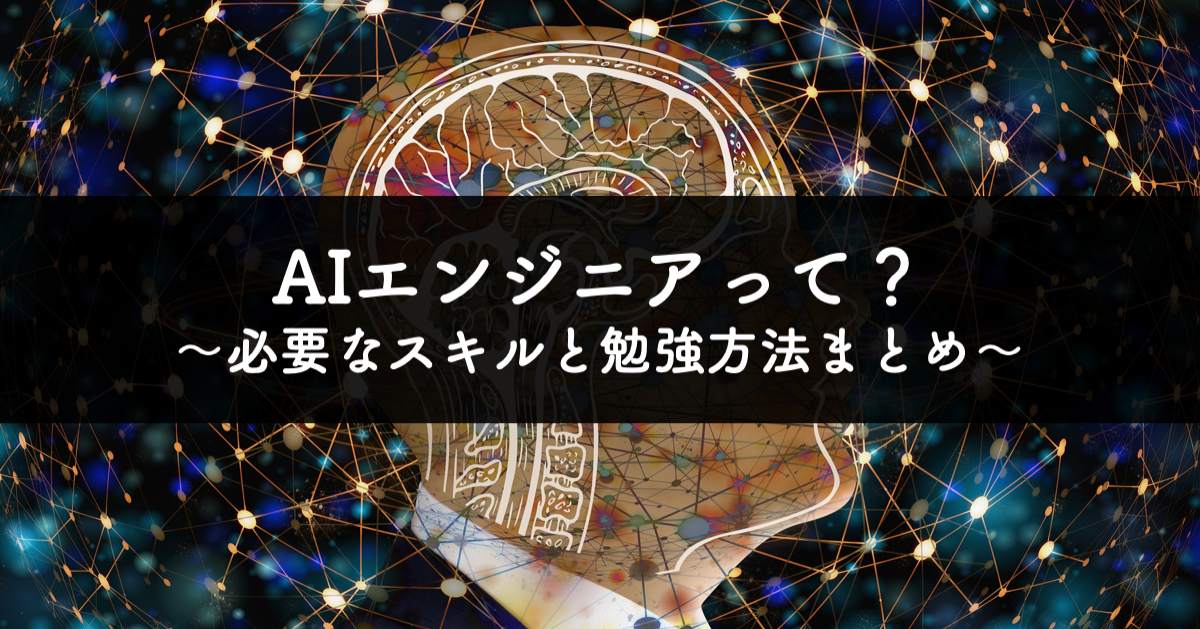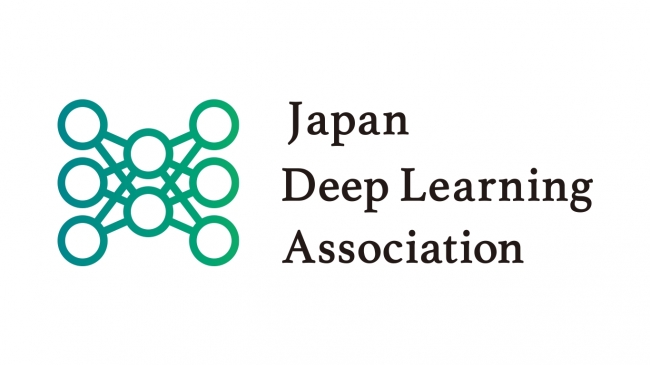今回は、「企画とAI」というテーマでお送りします。機械学習のAIプロジェクトでは「人」を軽視しがちなところがあります。顧客を見ずにアルゴリズムを見たり、属人的な仕事と非属人的な仕事の区別がついていなかったり。
AIプロジェクトの本質を見つめることで、よりよいAIの活用が見えてきます。今回はその「企画」編です。
イントロダクション

仕事をしていると旅に出たくなることがある。東京は関東平野の一部であり、平野は山に囲まれている。東京から電車で遠くへ出かけると、車窓は林立するビル群から関東平野の郊外の街並みへ姿を変え、やがてトンネルの暗闇へと変化する。ときおり光とともに山間の森の風景が姿を見せるが、しばしの暗闇を抜けると別天地へと変化する。同じ日本ではあるが、その風景は最初と別のものである。トンネルの時間と景色の変化は新しいビジネスの立ち上げを思わせる。
AI の現状について、さまざまな意見がある。そろそろ飽きてきたという人がいる。ブームが終わりつつあるという人がいる。AIに取り組まねば世界で戦えないという人がいる。各人の風景においてそれぞれは合理的な意見だろう。
これらの意見の背後には「最先端の技術をやってみた」と喜んでいたフェーズから、プロとしての責任を問われるフェーズへと移行しつつあるように見受けられる。ビジネス面においては実験すること自体が目的だったが成果を求めることへ揺り戻しが始まりつつあるように見受けられる。それは、単なる思いつきからキャッシュを生み出す仕組みをつくることへの移行である。
この移行は目新しいものではない。ITでも見られたことである。その成果は、スティーブ・ブランクのアントレプレナーの教科書やエリック・リースのリーン・スタートアップをはじめ、起業のプロセスやマネジメントとして体系化された。勉強熱心な方は関連書籍を何冊か読まれていることだろう。しかしながら、これらでは多く語られていないことがある。それは属人的なスキルとみなされている領域である。
この記事では最初に起業や企画における仮説検証の全体観について述べる。続いて属人的なスキルについて、あえて踏み込む。それは問題発見とユーザー・インタビューである。
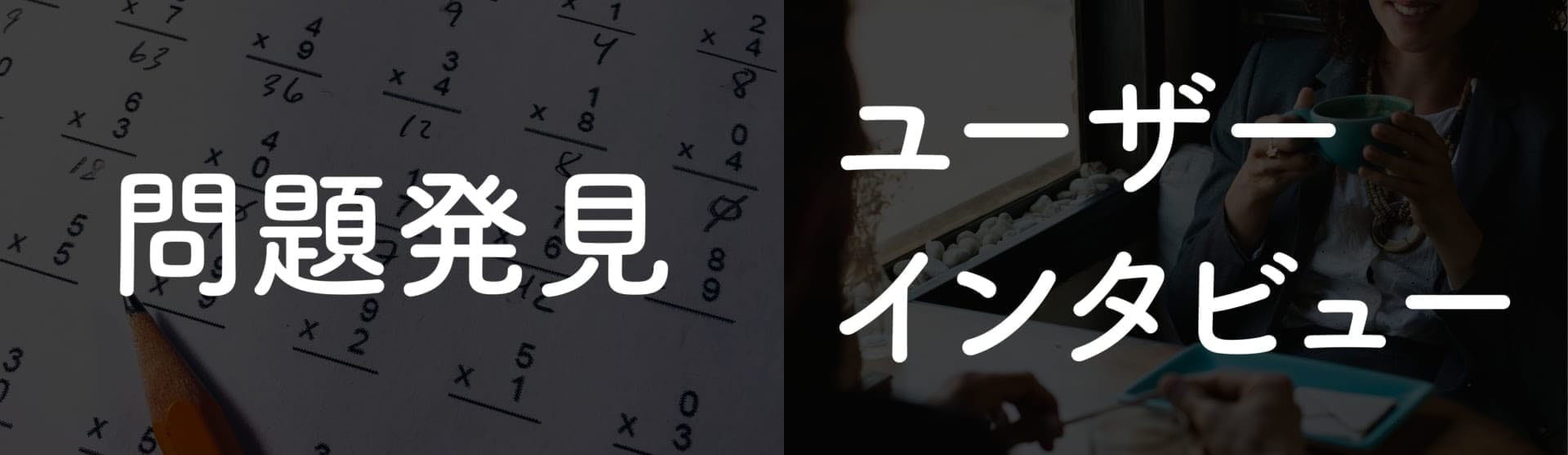
仮説検証のプロセス
1, 2 年くらい前、AIの情報というとアルゴリズムの解説しかなかった。そのような状況で、ある友人とAIとビジネスについて語ったことがある。
彼が言うには
「アルゴリズムから始めて、顧客を見ないで起業しちゃうスタートアップが多いんですよ」
とのことだった。
彼はリーンスタートアップを始めとする考え方をAI界隈に導入しようとしていた。
彼から学べることは「起業における考え方には型がありその手順を踏むことで打率をあげることができる」ということである。これは起業にとどまらず、既存の会社で新しい事業を始めるときにも、その型を使うことができる(リーンエンタープライズ参照)。その型はいくつもの良書で提案されている。ここでは起業の科学の考え方を参照したい。
最初にアイデアを思いつき簡単な検証をした後、以下のようなプロセスをたどる。
①CUSTOMER PROBLEM FIT
②PROBLEM SOLUTION FIT
③PRODUCT MARKET FIT
④TRANSITION TO SCALE
詳細は書籍を参照していただきたいが、大まかに言うと、
①は想定する顧客の問題を洗い出し、整理する。その問題はインタビューや行動観察で検証する。
②はワイヤーフレームで製品の概要を示し、使ってもらえるか/お金を払ってもらえるか、インタビューで検証する。
③でいよいよ製品を市場に投入する。製品が受け入れられるか、KPI やインタビューで検証し、改善する。
④は顧客獲得コストと顧客単価からスケール可能か検証する。
かつての製品開発と比べて製品のリリース前から仮説検証を頻繁に行っている。これはスタートアップを始め、製品開発の打率を格段にあげたと思われる。
しかしながら、スタートアップの方法論が多くを述べないことが2つある。
ひとつ目はアイデアをどこから得るか、という問題発見の方法論である。スタートアップに限らず、問題発見に述べられた本は非常に少ない。
ふたつ目は上記で繰り返し出てきたインタビューのノウハウである。論理的に分析するだけでなく、観察や対話の中で違和感を感じとる感性も重要である。マーケティングリサーチの分野で良書、マーケティング・インタビューがあるが、顧客開発や UXの文脈でもいくつか書籍が出ている。
以下では問題発見とユーザー・インタビューについて述べる。
イノベーションの機会
ある会社で社長が種類がたくさんある商品をレコメンドするアプリを作りたいと言った。
「XとYとZの全種類の商品をレコメンドするアプリを開発する」というものだった。私は「商品の種類ごとにターゲットが違う」といって反対した。あるデザイナーは「商品の種類ごとに利用シーンが違う」といって反対した。誰からも愛されないアプリにリソースを投入することは回避された。
華やかな企業の伝説にあこがれ、世界を変えるアイデアを夢見る起業家は多い。大変結構なことである。しかしながらすべての人を幸せにしようとして、八方美人になり、誰からも愛されない製品が多い。変革には理想と現実の両方を見る必要がある。現実を見ながら未来を見る必要がある。そのためには多数のLikeよりも少数のLoveから始める。多数に広がるのは未来の話である。
P.F. ドラッカーは30年以上のコンサルティングの経験から「イノベーションと企業家精神」でイノベーションの7つの機会を提示した。場面によっては重複することもあるが、分析の方法が異なる。現実を知覚することと数字を分析することである。ときに両者を使い分け、ときに両方を使う。以下、イノベーションの機会を打率の高い順に並べる。
- 予期せぬ成功と失敗を利用する
- ギャップを探す
- ニーズ(具体的な課題)を見つける
- 産業構造の変化を知る
- 人口構造の変化に着目する
- 認識の変化をとらえる
- 新しい知識を活用する
①から④は企業や組織、産業の内部に存在する。①から④の機会は表面的な出来事としてあらわれる。しかし水面下では本質的な変化や起こしやすい変化が存在することがある。そのシグナルとして時折現れるのである。
⑤から⑦は企業や産業の外部における事象である。
①から⑥の機会はなかなか注目されない。ときには無視されることすらある。競合が直視するまでの間、時間が味方してくれる。一方で⑦はコピーが可能である。競合がこぞって真似をする。この機会を利用する者は時間と戦わなくてはならない。
AIを活用することは基本的に ⑦に取り組むことである。着手した早さと資本の投下量、マネジメントの質によって時間の競争は決定づけられる。そのような競争を避けたければ、①から⑥を取り込み、競合が不安になったり無視したくなるビジネスをつくることが理想だろう。
この7つの機会の後にアイデアによるイノベーションがつづく。その成功譚は伝説として語られるが、そのほとんどは屍をさらすことになる。それは成功率が低くとも、その数は膨大であり、社会に活力を与える。成功した時には、それは高く評価され報われなければならない。とは言え、現実的にアイデアによるイノベーションが許されるのは、創業者をはじめとする、リスクをとれる者だけだろう。
ユーザー・インタビューの概要
新しい機会を発見したとしても、それが有効なものか分からないことが多い。新しい機会は所詮仮説にすぎない。
リソースを投下する前に仮説を検証する必要がある。スタートアップの方法論が教えるとおりである。とくに重要なことは顧客のニーズに関するものだろう。しかしながら多くの人が立ち止まる。「何をどう聞いたらいいんだ?」と。
ユーザー・インタビューは基本的に一般的なことからはじめて具体的なことへと進めていく。いきなり「この製品っていいと思いませんか?」と聞いても、「それって私と関係あるの?」と思われるが、波風を立てないように「まあ、いいんじゃないの」と当たり障りのない回答をされるのがオチである。たとえば、想定する顧客と利用シーンがあるだろうから、以下のような順番が考えられる。
- 挨拶と自己紹介をする
- 顧客の年齢、職業、家族構成などを聞く
- 商品・サービスの一般的なイメージなどを聞く
- 想定される製品の利用シーンについて、時間・頻度・量を聞く
- 悩みと直近の事例を具体的に聞く
- 解決してくれる代替品とその課題を聞く
- 悩みと代替品の課題を解決する対策を提示し、感想を聞く
- いくらなら払うか聞く
しかしながら、基本通りに一般から具体へ進めてもうまくいくとは限らない。インタビューをする側と受ける側に陥りがちな罠がある。
インタビュー・アンチパターンとその対策
まずインタビューをする側の典型例だが、自分の仮説に誘導する人がいる。
仮説は検証するものであって、売りつけるものではない。売りつけてしまうとインタビューを受ける人がおもんばかって、仮説に話を合わせてくることがある。
インタビューを受ける人は後のプロセスで痛い目を見ない。そのため、その場の人間関係をやりすごしがちである。インタビュアーは仮説に反するものであっても、フラットに聞くことが重要である。
フラットなインタビューは新しい発見をもたらすことがある。何回も仮説を練り直したり方向転換することはよくあることである。新しい発見は方向転換のヒントを与えてくれる。
インタビューを受ける側が、持論を展開することがある。たいていの場合、話が長く実りは少ない。
顧客は自分が悩んでいる問題の専門家だが、解決の専門家ではない。
適切なアドバイスもあるが、それは1割にも満たない。
ユーザー・インタビューでは、解決策ではなく問題を聞く。問題を掘り下げていく。掘り下げていく際には丁寧に具体化していくことが重要になる。
一般論ではなく、インタビューを受ける人が体験したリアルを追求する。「何があったのですか?」「具体的に言うと?」「例えば?」などの質問で個別の事例を追求していく。
具体化しながら問題の軸を探り、構造化していく。機能的な問題と感情的な問題の両方を行き来しながら掘り下げる。機能的ベネフィットと感情的なベネフィットを探るためである。
しかしながらインタビュアー泣かせなことに感情面を見せない人がいる。これは知的レベルが高い人によく見られる傾向である。知性によって現状を正当化する。ここにヒントがあることは多い。
たとえば、システム構築を大手に発注している会社があるとしよう。
理想的にはもっとスピードが早い業者を選びたい。しかし他の業者にスイッチするコストが高く、どこも同じようなものと正当化することがよくあるだろう。
そこでインタビュアーが理性を緩めたり、理想像を意識させたり、別の視点を提供する。「みなさん同じように困っていますよね」「対応が遅くて困った例を教えてもらえますか」「あなたがCIOで、システムを短期間で構築するように社長から言われたら、どのように解決しますか」など、さまざまな質問方法があるだろう。
構造化すると、問題を整理する軸が見つかる。語られていない領域を発見することがある。たとえば、AIエンジニアの養成講座を企画し、知り合いのITエンジニアからインタビューしたとしよう。
「AIができないとまずい」というグループと「AIでキャリアが広がる」というグループがあったとする。前者にはキャリアという言葉は出てこない。
そこで「あなたにとってAIはどんな意味があるのですか」と聞くと、前者は「事業でAIを使わないと、今後は戦えない」、後者は「給与がよさそう」「面白そう」という回答が得られた。
前者は事業を活性化する責任がある立場にあり、AIの競合は事業を強化するさまざまなノウハウになる。後者は個人の利益や興味を追求するものであり、AIの競合は最先端のテクノロジーや市場価値の高いスキルになる。
語られていないところにユーザーの価値観やセグメントの軸について重要なヒントが得られることがある。
インタビューを受ける側が、本音を言ってくれないことがある。例えば、見栄をはる、社会的役割に縛られる、暗黙知、などはよくあることである。
グループインタビューで発生しがちなので、インタビューに慣れないうちは1対1でおこなう方がよいだろう。
1対1でも本音を話してくれないことがある。そのような場合は、信頼関係を丁寧に築き、さまざまな技法を使うことが必要になる。
詳細はマーケティング・インタビューを参照されるか、実践と振り返りのなかで腕を磨いてほしい。
クロージング
ビジネス書では顧客のニーズを理解することが重要と繰り返し唱えられている。
その多くで提案されるのは、精神論や観察することであるが、体系立ったノウハウは少ない。顧客開発モデルやリーンスタートアップ以降、仮説検証のマネジメントが整理されてきたが、問題発見とインタビューは依然として属人的なものとして扱われている。
これらは感性をあつかう領域なので、ある程度の属人性が残るのは仕方がない。人によっては器用にこなしてしまい、当人が何をしているのか説明できないことも多い。他人からすると、それは神秘的なものに見える。
この記事は、あえて属人的な領域に足を踏み入れた。光が当たることが少ない領域を概観することを目指した。より掘り下げて調べたい人は文中の書籍を参照されたい。
この記事がAIをはじめとする新しいビジネスに挑戦する人のヒントになれば幸いである。
坂井さんの今までの記事はこちらから