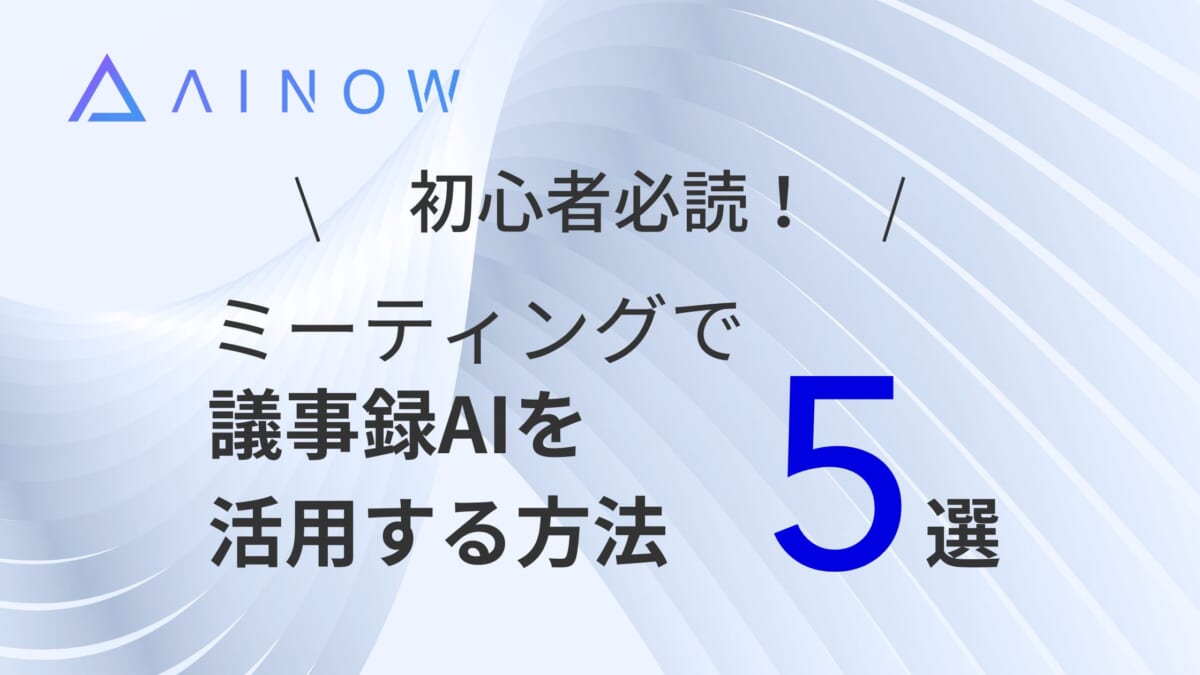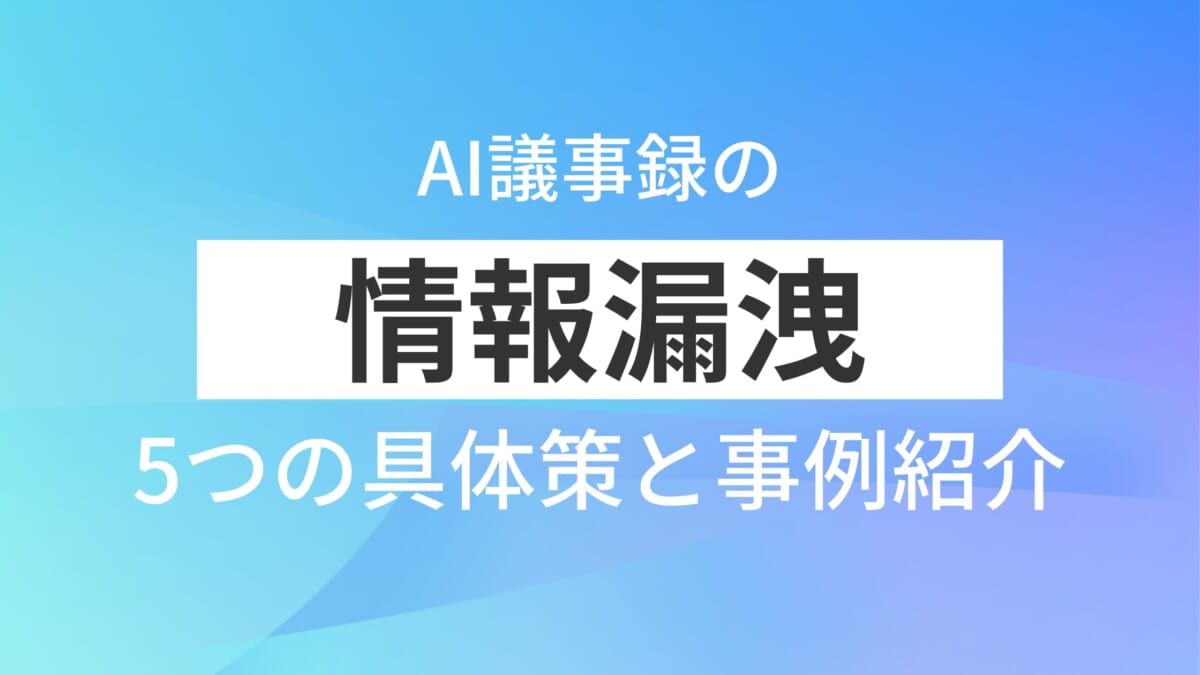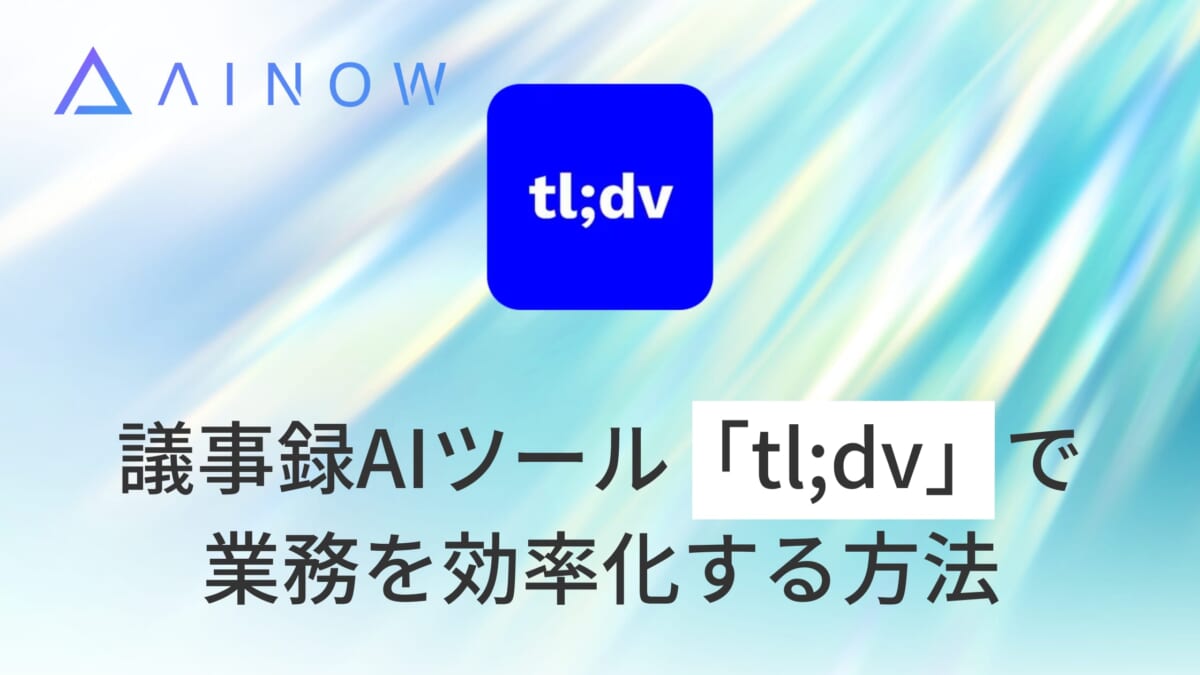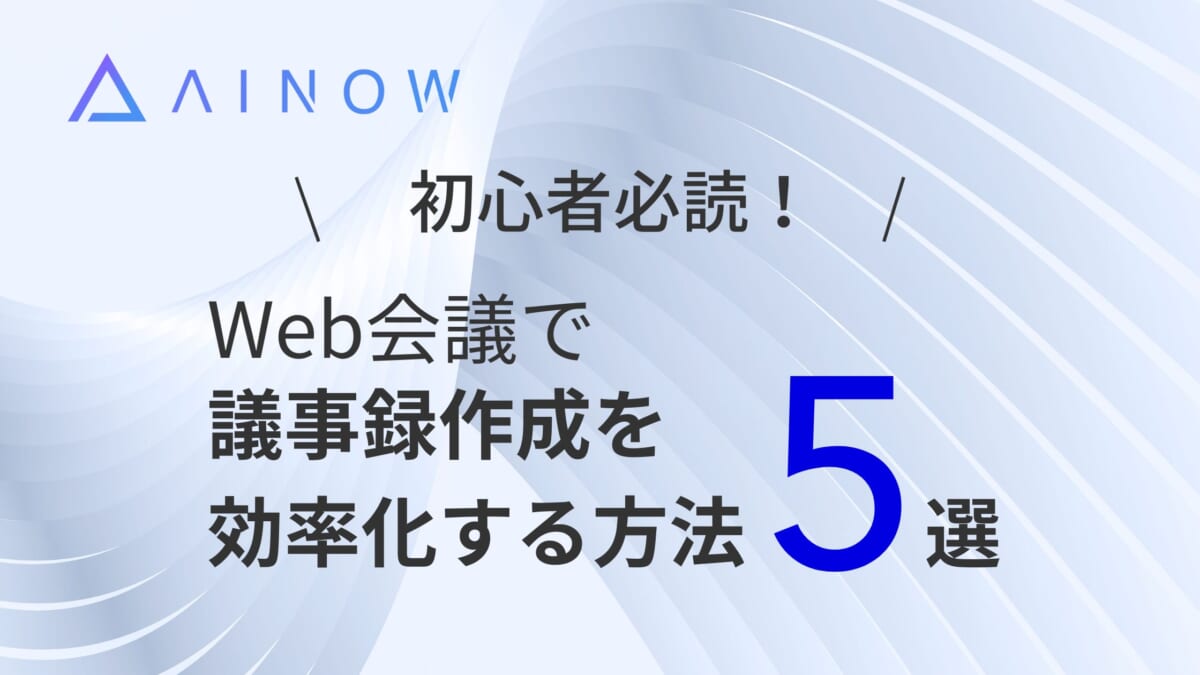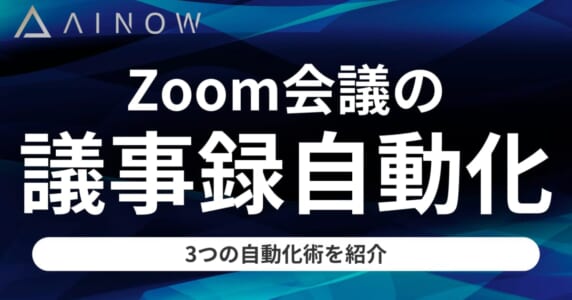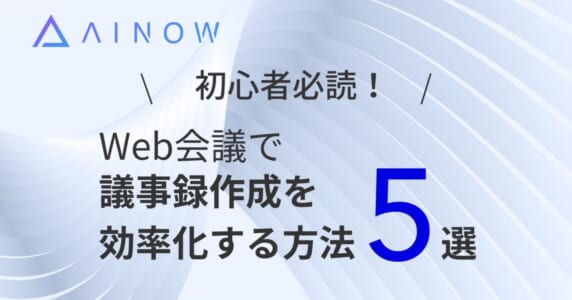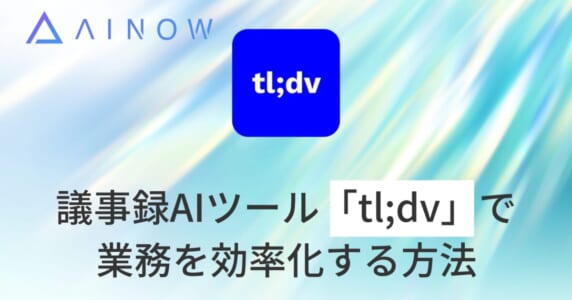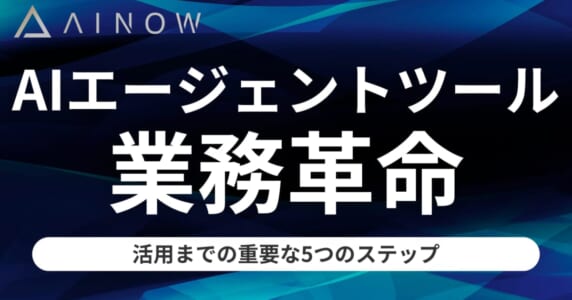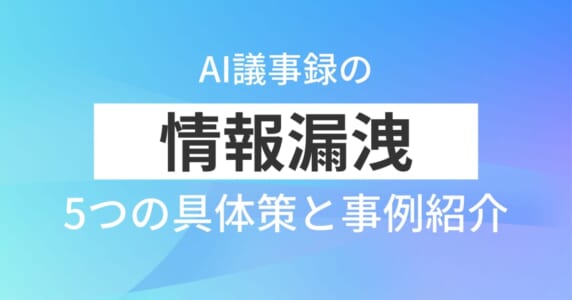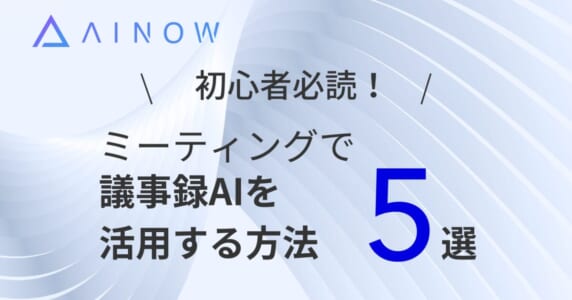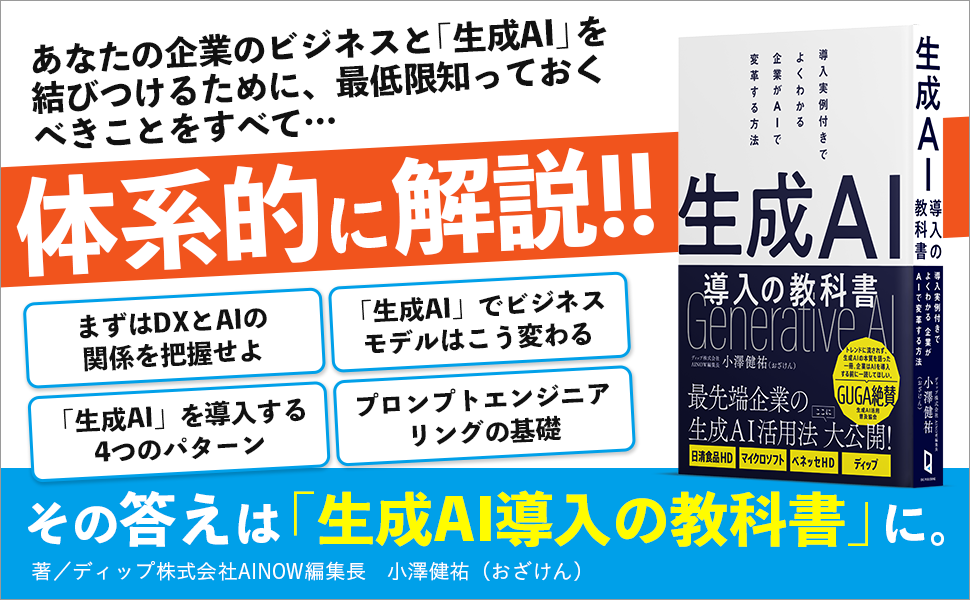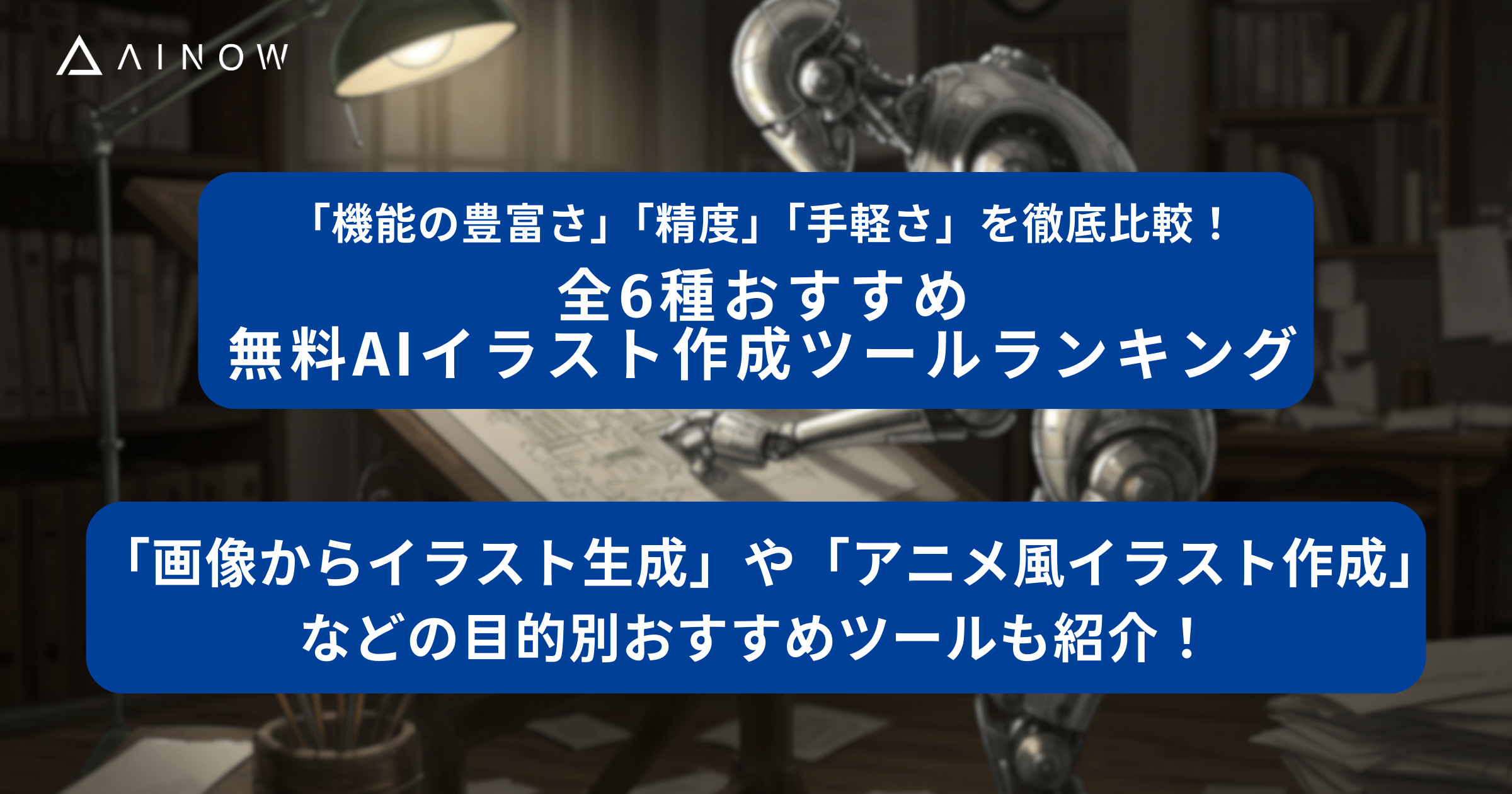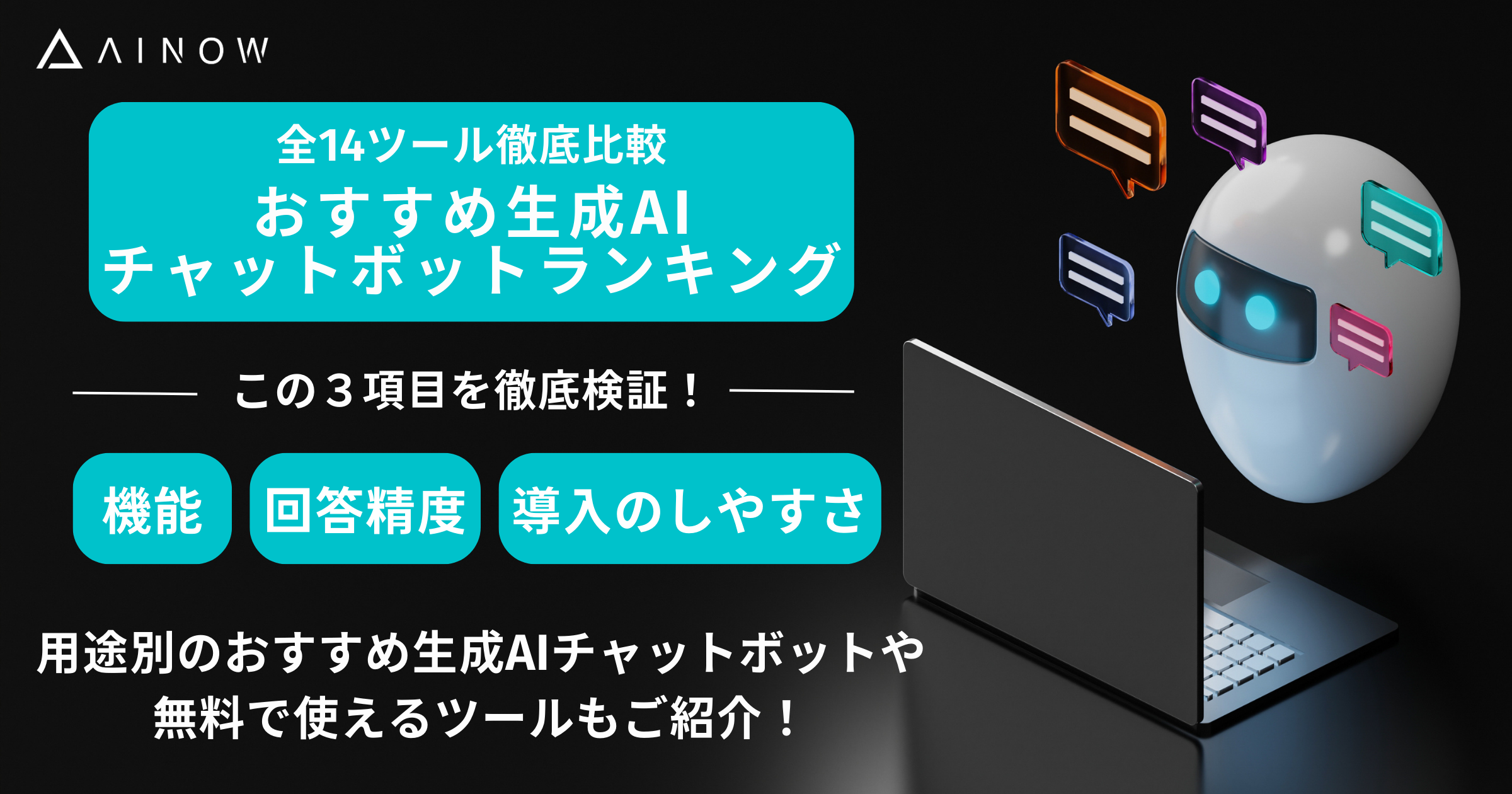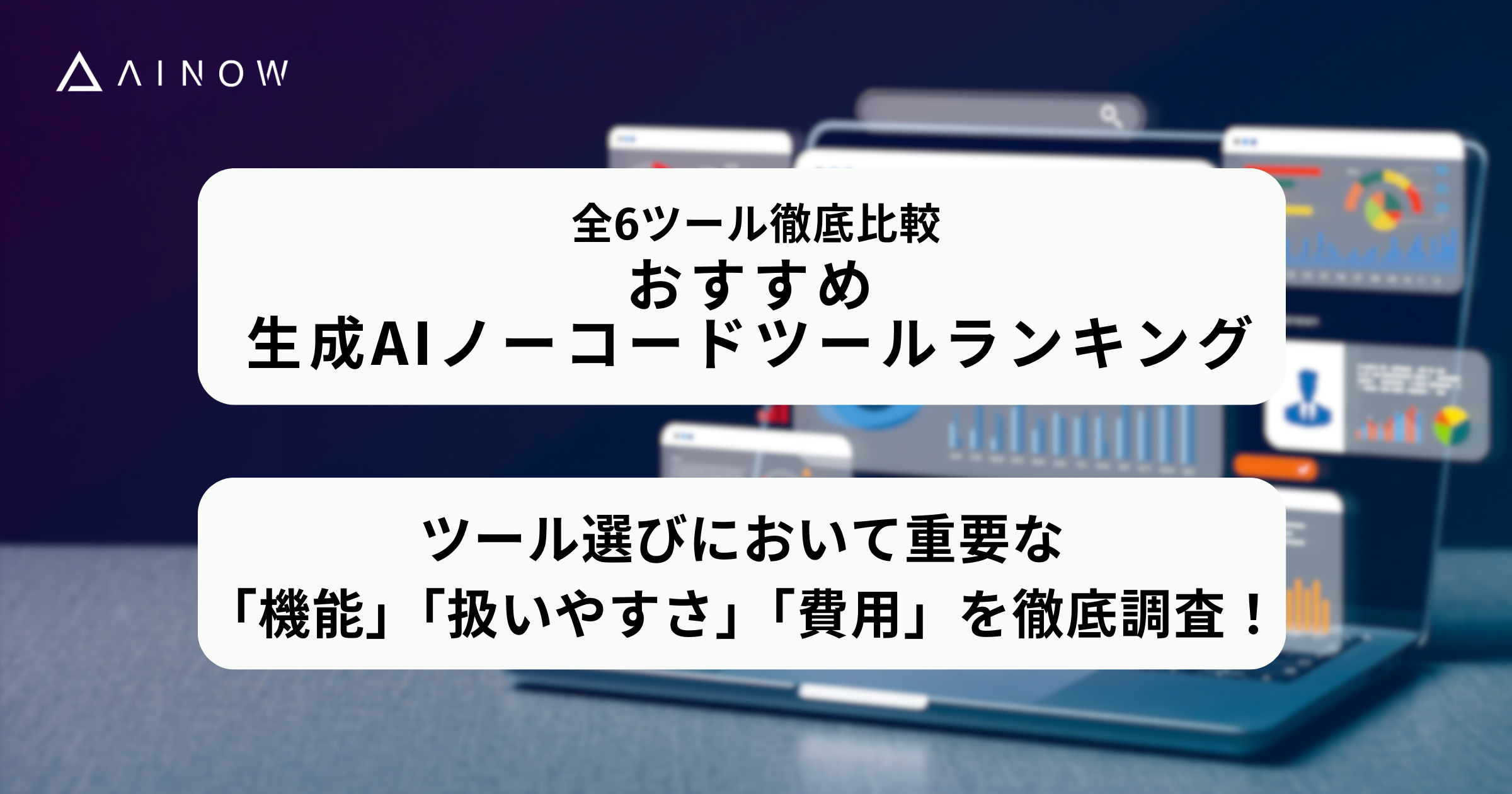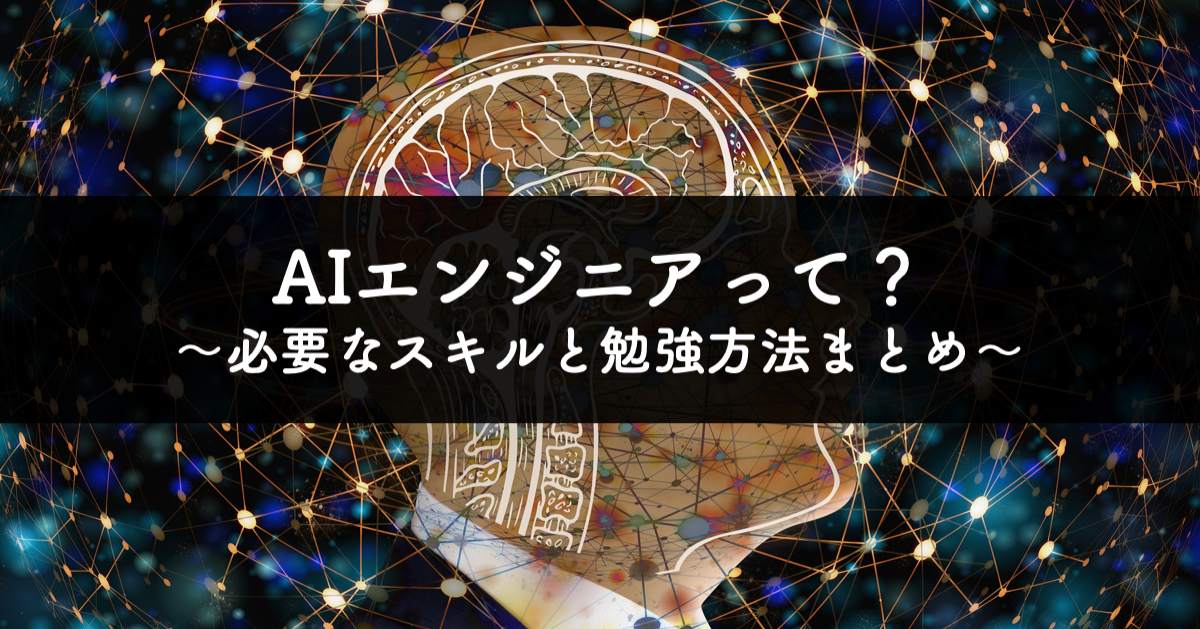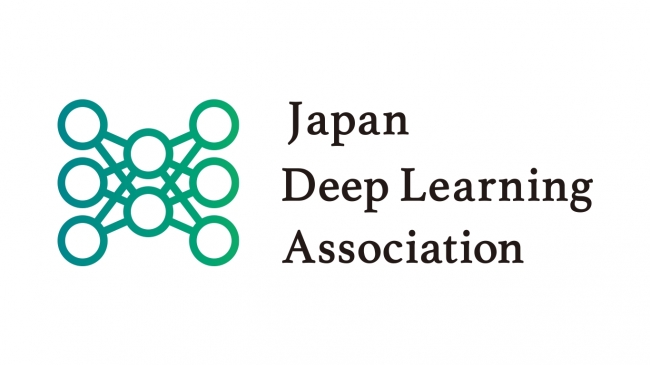我々は第三次AIブームの真っただ中にいる。メディアで人工知能が連日取り上げられ、深層学習の事業開発を行っている筆者のもとにも様々な業種から日々相談が寄せられている。一方、ここまでブームになりながら、深層学習で実用化まで到達したサービスは非常に数少なく、研究開発段階であるものがほとんどである。筆者は深層学習が人類に革命的な価値をもたらすことを確信し日々仕事に取り組んでいるが、この新しいテクノロジーの使い方を理解せずにブーム乗ることはとても危険だとも考えている。そのために、深層学習の理想と現実、それを踏まえて人が何に取り組むべきか考えてみたい。
我々は第三次AIブームの真っただ中にいる。メディアで人工知能が連日取り上げられ、深層学習の事業開発を行っている筆者のもとにも様々な業種から日々相談が寄せられている。一方、ここまでブームになりながら、深層学習で実用化まで到達したサービスは非常に数少なく、研究開発段階であるものがほとんどである。筆者は深層学習が人類に革命的な価値をもたらすことを確信し日々仕事に取り組んでいるが、この新しいテクノロジーの使い方を理解せずにブーム乗ることはとても危険だとも考えている。そのために、深層学習の理想と現実、それを踏まえて人が何に取り組むべきか考えてみたい。
第三次AIブームを引き起こした深層学習
人工知能という言葉そのものは1956年のダートマス会議でジョン・マッカーシーによって作られた比較的歴史のある言葉であるが、現在の第三次AIブームをけん引しているのは深層学習というテクノロジーである。今までのソフトウェア開発においては人が考えたアルゴリズムをプログラムに落とし込む演繹的な開発手法が中心であった。しかし、深層学習時代のソフトウェア開発においては、ビックデータを学習することで帰納的にアルゴリズムが出来上がるのである。人間のプログラマーが知恵を絞ってアルゴリズムを考えていた世界から、コンピューターが大量のデータを学習することで、今までとても困難であった分類、認識問題を解くことができるようになった。結果、2012年の画像認識コンテストにて深層学習がブレークスルーを起こしたのである。世界中でほとんどいなかったニューラルネットワークの研究者がその後激増し、各種学会の参加者が激増していったわけであるが、その背景にオープンイノベーションによる研究開発の加速がある。
爆速で進化し続ける深層学習の背景にあるオープンイノベーション
過去、先進的な研究は学会を中心に共有されており、その物理的な障壁により最新情報へのアクセスが阻害され、出版・手紙・人的ネットワークによる情報共有が中心であった。しかし、深層学習の場合、企業や大学の研究者が最新の研究成果を論文・サンプルコード・データセットをarXiv.org やGitHubを通じて公開しているのである。今まで企業競争力の源泉で絶対非公開あったような最新の研究成果が日々公開されることはイノベーションの創出を加速させるとともに、企業に対して競争領域の再検討を迫っている。過去のように研究成果を公開しない企業は、研究者に対して魅力的な職場を提供できなくなり、結果として公開に追い込まれるケースが増えている。深層学習を活用したい一般の企業からすると、深層学習そのものの研究というより、深層学習でできること・できないことを理解し、今後の事業戦略の中でどう活用するか?といった点のほうが重要となっている。例えば、筆者が懇意にしている製造業の会社では、CVPR(コンピュータービジョンの学会)で10月に発表された論文を、12月に自社ソリューションに実装する、といったことが実際に起こっている。世界中の研究者の英知の上に立ってビジネスを展開できる世界が今まさに来ている。
深層学習のよくある誤解と困難さ
上記のような話をさせて頂くと、ビックデータを用意すればバラ色の未来が訪れる、あれも出来ないか、これも出来ないか、という話が企業内で検討されることになる。一方、未だ深層学習の活用はおおむね研究領域に留まっている現状がある。ここに深層学習の本質的な限界と困難さがあり、筆者が遭遇する良くある誤解は、「未来を予測できる」「ひらめく」「100%の精度保証ができる」といった点になる。深層学習がいかに新しいテクノジーだといえ、統計的機械学習の一分野に過ぎず、学習したデータと違う未来は予測できず、突発的な事態を予測することもできない。また、学習データをランダムにサンプリングする時点でバイアスが入ってしまうことは避けられず、100%の精度を保証することはできない。このあたりは自動運転で盛んに議論されている点でもあるが、企業導入において大きな障壁となっている。人がやったとしても100%の精度は保証できないにもかかわらず、AIには100%の精度保証を要求するという矛盾する事態となっている。
また、データをもとにした帰納的なアプローチであるがゆえに、やってみないとどこまでの精度が出るかがわからない現実がある。これは今までの人が考えて実装する演繹的なやり方では発生しなかった状況であり、企業側の理解を得ることが大変難しい。さらに、深層学習にたけた研究者・技術者は今市場に枯渇している状況であることがコストの高止まりを生み、実績のある会社に技術開発をお願いすると、月300~1,000万円かかるのが通常である。いくら論文でアルゴリズムが公開されるとはいえ、それを実社会で活用しようとすると、追加のデータ収集、データ整備、アルゴリズムのチューニング、NVIDIA GPUに代表される大量の計算資源が必要になり、ここが大きなコスト要因となっている。深層学習の雄であるPreferred Networksに対してTOYOTA自動車が105億円追加投資したという事実は、優秀な研究者がいかに得難いか、ということを物語っている。では、企業はどう取り組むべきなのだろうか?
企業が深層学習を活用するためのヒント
企業が理解すべきことは、深層学習はパワフルなテクノロジーであるが、あくまでツールであり手段に過ぎないということである。深層学習ありきでプロジェクトを始めるのではなく、事業計画ありきで深層学習というツールの利活用を検討すべきなのである。良い例としてご紹介しているのが、アメリカのレタス農家の話である。コンピューターが犬と猫を見分けられるようになった、と聞いたときに大半の人間はだから何?と思考停止してしまうわけだが、それならレタスと雑草は見分けられそう、レタスだけ狙って収穫できるようにすれば年間数億円かかっている農薬コストを下げられると発想した人間がいたわけである。これは実際に実用化され、広く使われるようになっている。例えば、工場の外観検査であれば、24時間稼働の1ラインが3人交代で、人件費だけで1,000万円近くかかっている、といった計算が成り立つし、コンビニレジの無人化、といった話も同じような計算が成り立つ。また、売り上げを伸ばすという視点でいうと、タクシーを需要の多い場所に配車できるようにしたり、Webサービスで深層学習を使ったリコメンデーションを上げるといった取り組みが行われている。明確な事業目標達成のために深層学習が使えるのであれば使う、というアプローチが重要ということである。

そのためにどうやって社内人材を育成すべきか、という点も大きな課題である。確かに深層学習そのものの研究者は枯渇しており、世界中で取り合いになっていることは事実であるが、基本的に研究成果が公開されるため、その領域で競争力を持つことはとても困難であり得策ではない。企業が注力すべきことは、最新の研究成果を理解でき、それを企業のビジネスに会った形で実装できる人材の育成である。深層学習のプログラミング難易度は低く、deeplearning.ai のコースや、弊社・キカガク・Preferred Networksで推進している深層学習のハンズオンなどを受講することで、基礎能力を付けることはそこまで難しいことではない。また、実際に深層学習プロジェクトを推進すると体感することになるが、実際に工数と時間がかかるのは学習データの準備と作成である。そして、何を学習させて、何を深層学習で出力したいのかをデザインし、そのために必要なデータを計画的に蓄積していくことが大事になる。先進的な企業は、例えば、設計のためのデータを包括的に集めるプラットフォームを構築したり、メディアから収集できるデータを横ぐしに集めるプラットフォームを構築する取り組みを行っている。深層学習というテクノロジーの進化が、企業にデータ戦略の立案を要求する結果となっている。
人とAIが共創する世界へ
筆者はAIが人の仕事を置き換えるのではなく、本当は人間がやりたくない仕事をAIが肩代わりすることで、AIが人を助けていく時代が来ると考えている。新しいテクノロジーが人の職を奪う、という論争は古くはラッダイト運動からComputerが世に出たときまで、常に行われてきた。現在のComputerが生まれる前はComputerとは計算する人のことを指していた。確かに、計算する仕事そのものは機械が代替したかもしれないが、その後大きな産業になり、大量の雇用を生んだのは周知のとおりである。データサイエンティストという職業が機械学習の発展で生まれたように、深層学習の発展で新しい職業が生まれることになる。例えば、データの整備のための仕事が大量に発生するのは確実であり、そのための会社が設立されたり、中国にそれ専門の会社を作るといった動きが盛んになってきている。
人とAIが共創するいい例として眼鏡の話をさせて頂いている。1200年代の眼鏡の発明により、視力が悪い人でも視力が良い人と同じ生活が送れるようになった。深層学習の発展によってComputerがモノを見ることができるようになってきている。それではなぜ、目が見えない人のためにAI 眼鏡が作れないのか。その発想で弊社はAI眼鏡の取り組みを行っている。これこそ、AIが人の可能性を広げる例であり、このような取り組みが日本で多数行われることが今後日本の競争力に影響を与えるであろうし、筆者もそのために微力を尽くせればと考えている。
Seeing AI Prototype
ここまでお読みいただきありがとうございました。弊社では深層学習の実社会での応用を推進するために、腕に覚えのある深層学習関連会社の皆様と一緒にDeep Learning Labというコミュニティを推進しております。今回のような話や、実際に応用した事例紹介、著名な方の講演など、深層学習利活用のための方法論やヒントをつかめる会を開催しております。是非ご参加頂戴できると幸いです。