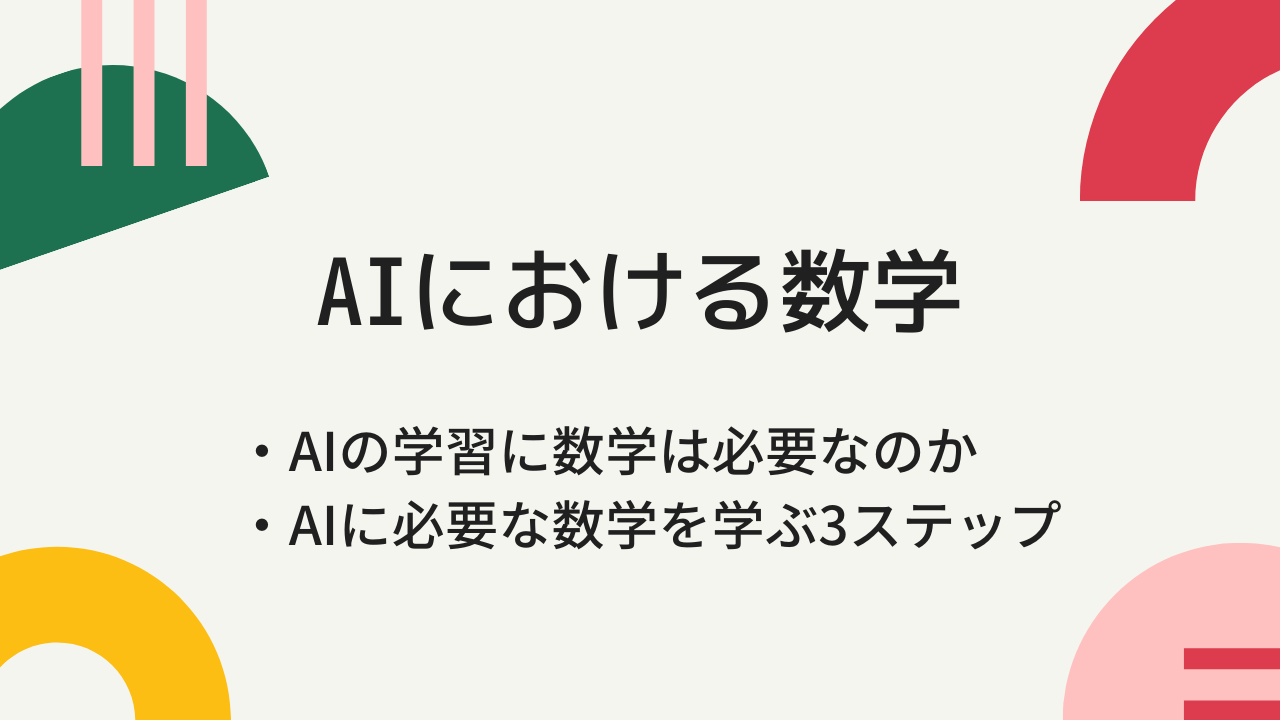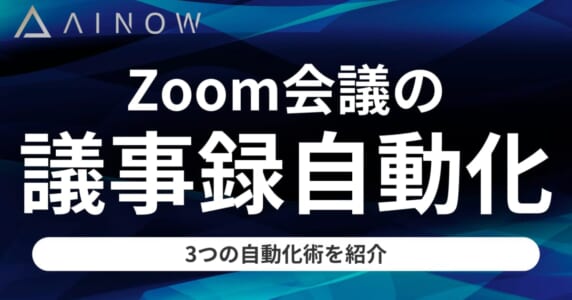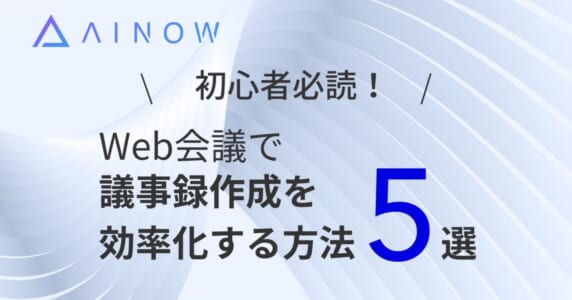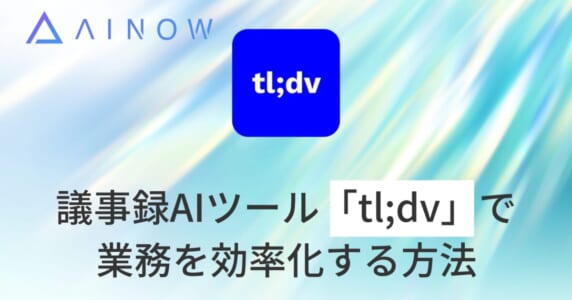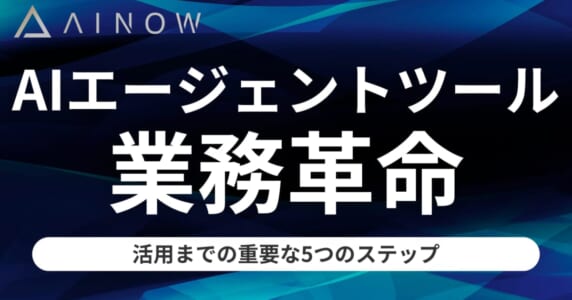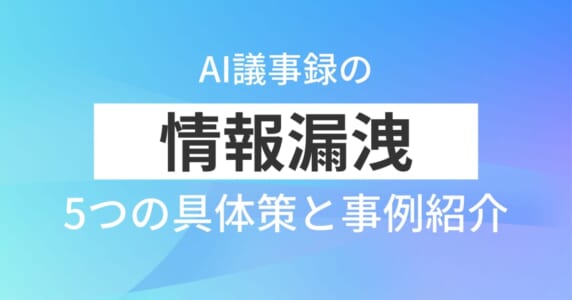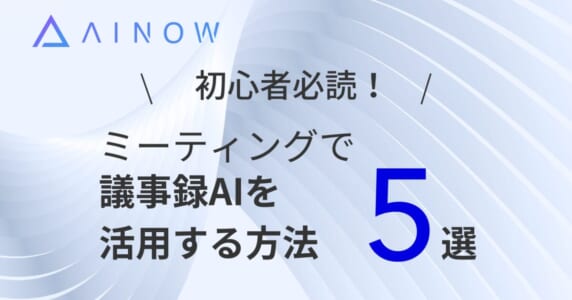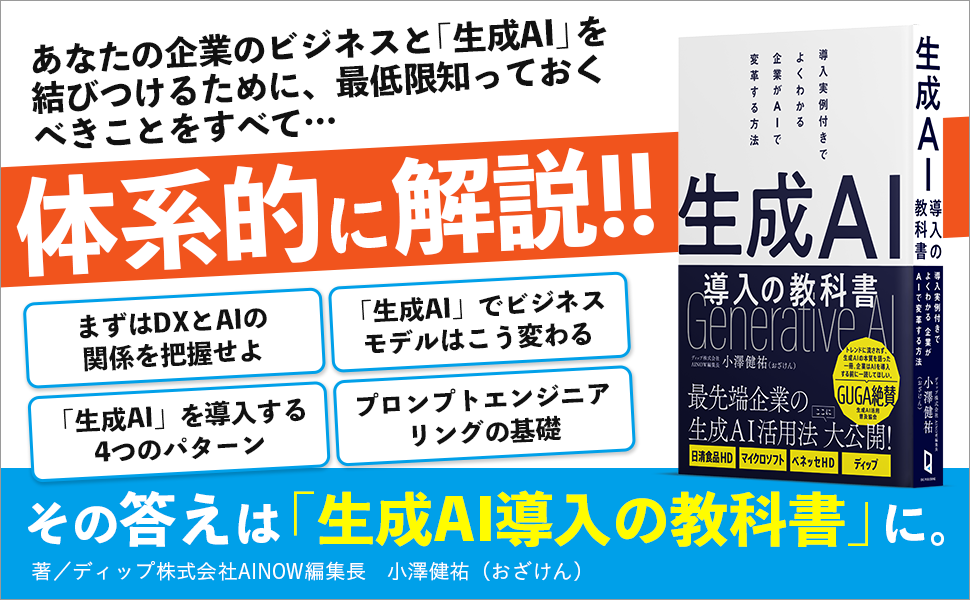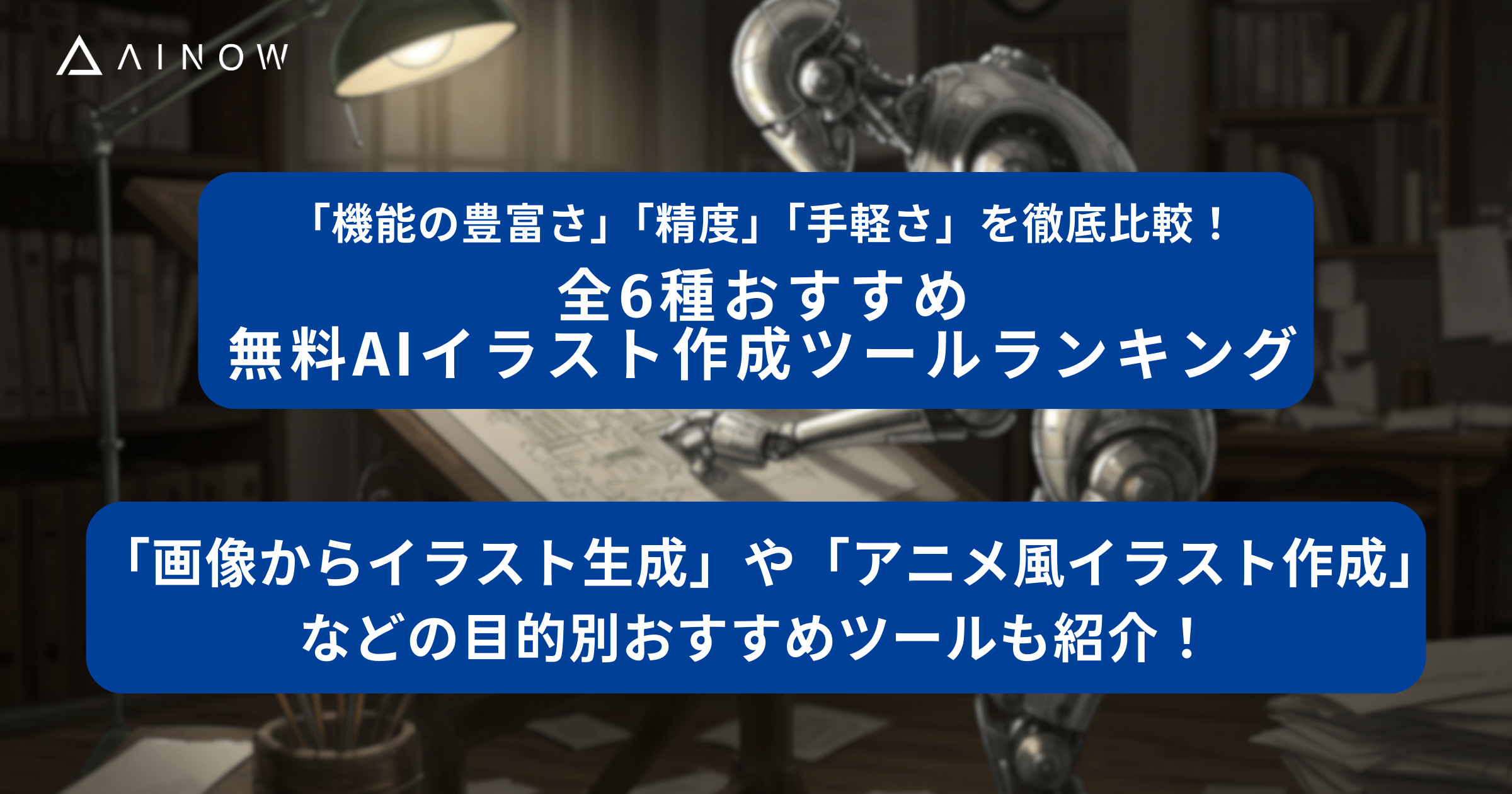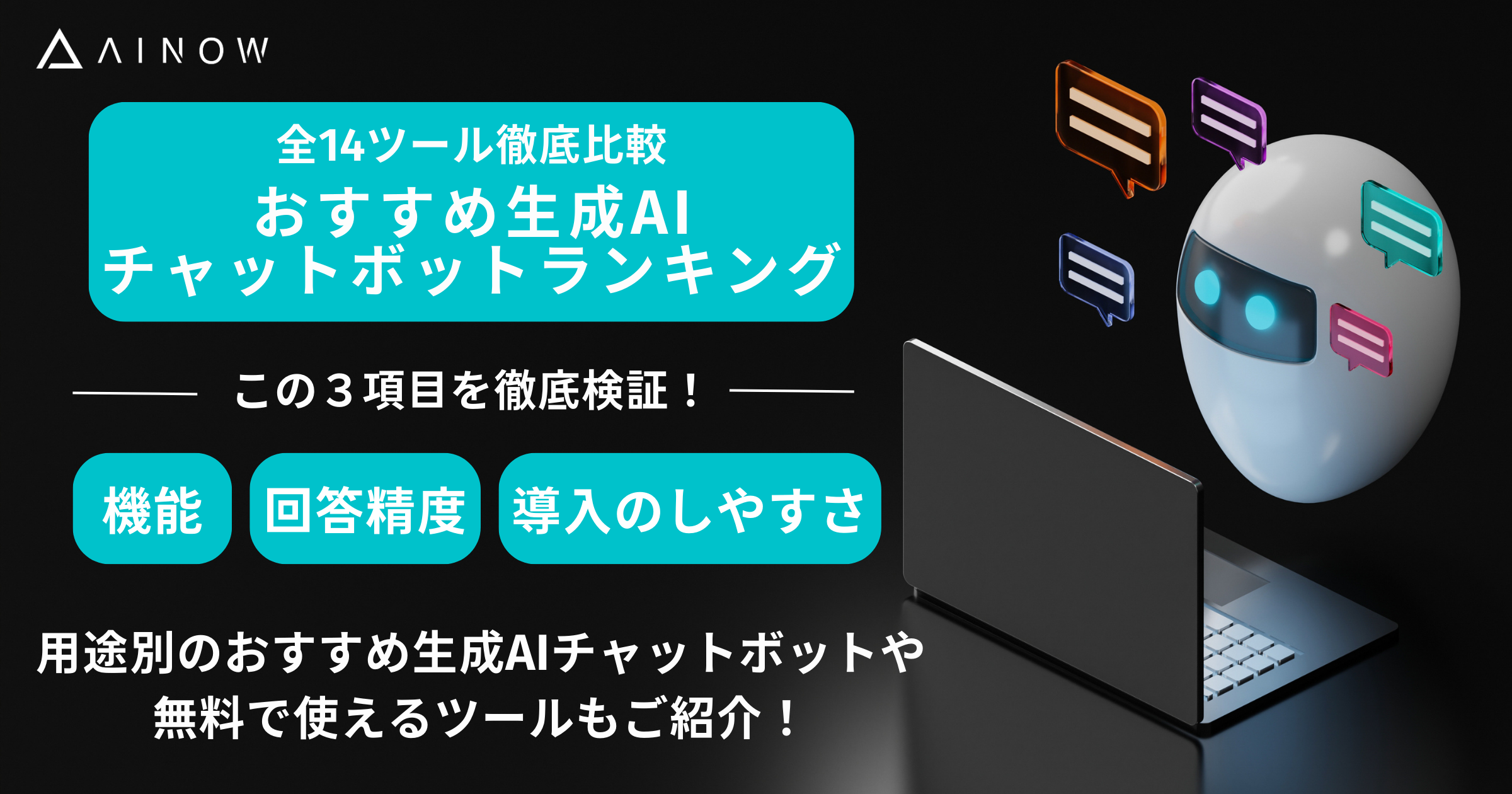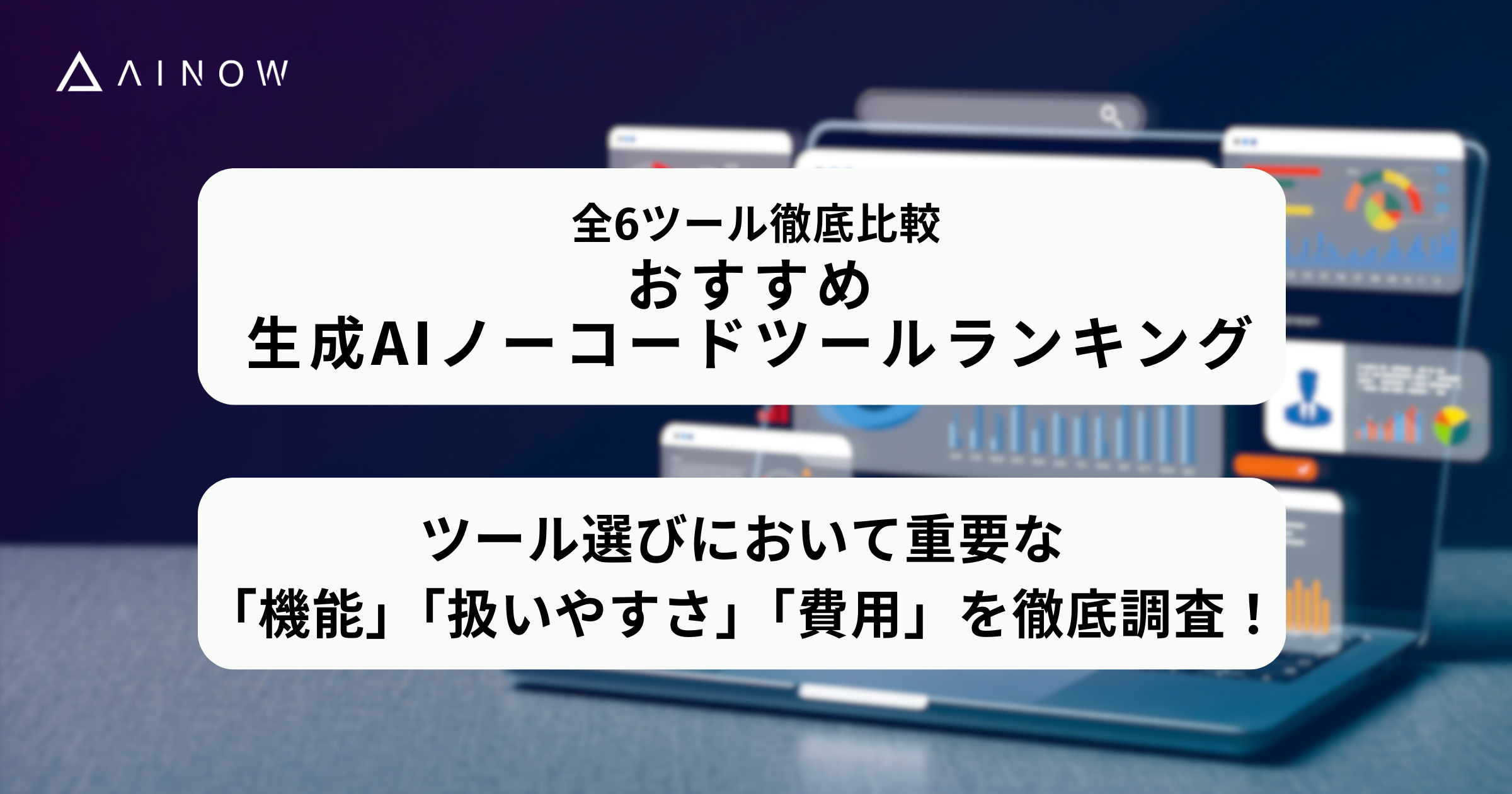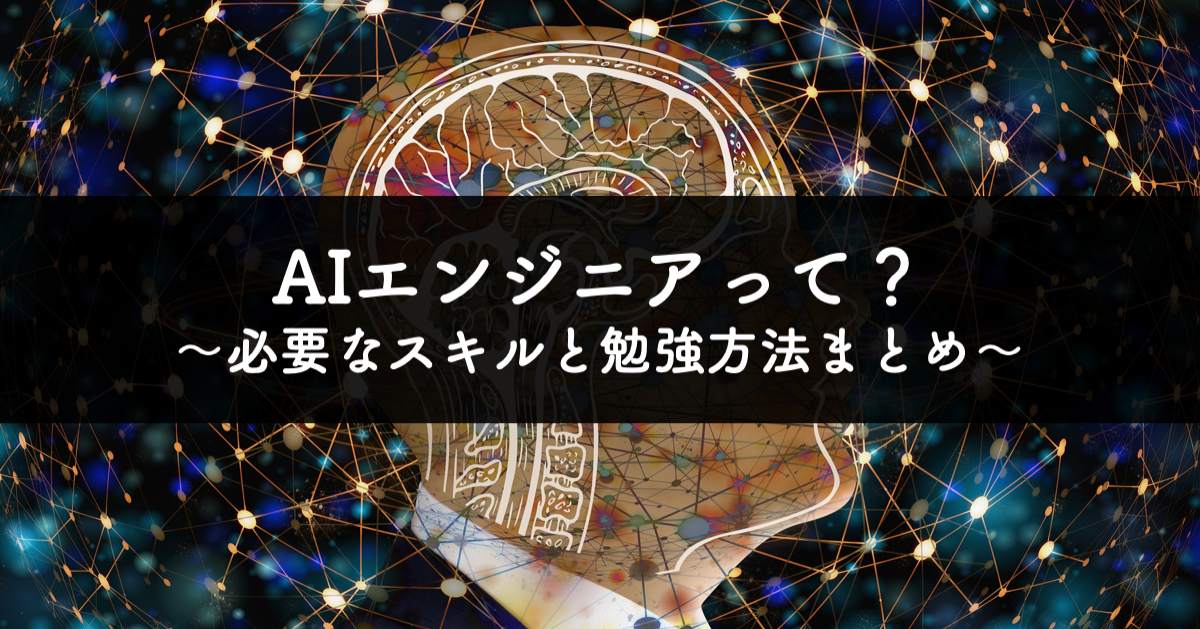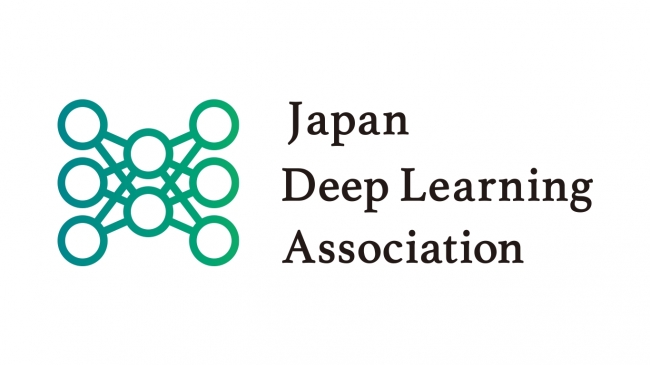目次
超AIとは何か
基調講演は「超AI」という言葉の定義からはじまりました。落合陽一氏の「超AI」という言葉は、元は落合陽一氏が研究代表を務めるJST(科学技術振興機構)のCRESTという研究プロジェクトの事業名に出てきた言葉であり、また落合陽一氏の書籍『超AI時代の生存戦略 ―― シンギュラリティ<2040年代>に備える34のリスト』によっても流行した言葉です。
超AIとは、「すごいAI」という意味ではありません。「メタAI」という意味で、人的システムやハードウェア実装、社会システムも含めて、「AIによって定義されるソフトシステムだけでは解決できない問題をどう解決するか」ということに焦点が当てることをテーマにした言葉です。
すなわち、我々は、コンピュータ内のデータだけでは解決できない課題や、AIと呼ばれるソフトシステムに基づいてどのようなコミュニティを形成し、システム化するかという課題について取り組んでいく必要があります。

多様なAI
多様なAIの必要性
昨今話題になるAIの代表例として様々な認識器を考えます。現在、画像処理系では顔認識や物体認識など、または音声認識系では発話や環境音の認識など様々な需要に合わせた認識器が必要とされています。個人や社会の多様な課題を解決するために、AIは個別多様化していく必要がある面も大きいですが、現場に合わせてチューニングするためには非常に多くの工数がかかります。現場でチューニングするためには、ワークショップで現場の理解を促したり、継続的にデータ収集とアップデートの行われる実践コミュニティを作っていく必要があります。
AIと社会の関わり
工場でのプロジェクトを例にとって、例えば不良品を仕分けるAIについて考えます。人間による検品とAIによる検品を比較すると、99%の精度が求められている場合はAIが勝りますが、99.99%以上の精度が求められているときには人間による検品が勝ることもあります。そういったときのメタAIを含むシステムをどう考えていくのか。
例えば人間による検品の場合は、認知負荷の大きさについても考える必要があります。ここでの認知負荷はストレスと言い換えることもできるでしょう。ここで、本来は隅々まで検品する必要があったものを、AIのサポートによって一部だけ検品するだけで済むようになれば、検品者の認知負荷を減らすことができます。
高齢社会である日本では、認知能力や身体能力が低下してきた老人に注目するのも社会課題の一つであり、上記と同様で、どのようにAIによってサポートし、ストレスがかかる状態を軽減していくかというのが焦点になります。
現状我々の抱えているこのような問題への対応策は非常に属人的な課題として捉えられがちですが、日本の人口が減少している現状を見ると、多様なAIと人的リソース、そして環境に埋め込まれたIoT技術によって解決していくことは有力な選択肢の一つであるかもしれません。もしくは移民による労働力確保が必要になるかもしれませんが、そういった政策は複数の選択肢が同時に進むことでしょう。
身体の多様性に合わせたインターフェイス
少子高齢化社会では、例えば視力に関する多くとのトラブル、例えば、老眼や視野狭窄などに悩まされる人口が増加していきます。そのため、個人にとって最適化された網膜投影やそういった網膜検査技術の需要が高まります。あるシステムに対する最適化問題というのはAIの得意分野ではありますが、個人の視覚に対応する最適化は未だコストの面でも技術開発の面でも困難な課題のうちの一つです。
さらにハードウェアとしての目だけでなく認識器としての視覚についても注目します。これまでもコンピュータビジョンによる自動運転などは実現に近づいていますが、落合陽一氏の筑波大の研究室では、車いすの自動運転を、少ないコストでどう社会にデプロイするか(研究成果を社会実装するか)という取り組みを行っています。ワークショップなどを行い、自動運転で判別すべきところだけでなくリモコンで操作できるようにすることや、古典的なマーカーによる追従を実装することなどによって、コストダウンに成功しました。車いすは自動車と比較して低速で動くため接触による事故のリスクが小さいため、タブレットやスマートフォンで扱える範囲の計算量で解決することができるかもしれません。
音を触覚に変換するデバイス
落合陽一氏は、富士通の本多達也氏との共同研究や自身が代表を務めるピクシーダストテクノロジーズの開発による耳の聞こえない方のためのIoTデバイスの開発にも取り組んでいます。例えば聴覚補助として音を触覚に変換する際には、触覚情報が恣意的にプログラミングされることが問題となるため、実際に自分で運用するエンドユーザーが現場に向かい合うことでしか見えてこない課題があります。
今、さまざまなIoTデバイス自体は回路の小型化や開発環境のコモディティ化によって実現していますが、個々人へのチューニングが必要であり、エンドユーザーがプログラミングできるようなUIを作ることが必要となります。そういった研究をCREST xDiversityプロジェクトの一環として、大阪大学の菅野さんや富士通の富士通の本多氏と行っています。また、耳が聞こえる開発者には耳の聞こえない開発者の持つ課題が直感的に認識できないため、最初に作ったデバイスがそのまま上手くいくとは限らず、ワークショップで試行回数を増やすなどの対策が必要です。
エクストリームユーザーとAI
AIによる最適化やロボティクス、また3Dプリンタなどのデジタルファブリケーションツールを用いた最適な義足の作成は、足の不自由な一般人にとっても、アスリートにとっても重要な課題です。CREST xDiversityプロジェクトの一環としてSony CSLの遠藤氏とAIを用いた身体の最適化のプロジェクトも行っています。
この点については、草の根的なアプローチによるユーザーに向き合った課題解決と、大きな課題を持っていたり、アスリートのように身体的に優れ競技的に注目を集めるようなエクストリームユーザーに注目したアプローチが考えられます。
落合陽一氏によると、年末までにこの件に関する大きな発表があるそうです。

多様なAIの課題
ここまで、視覚、聴覚、身体能力などについて、個々人に合わせたAIの必要性について述べてきました。このように多様な人的システムやハードウェアを含めたメタ的なAIシステムやエコシステムの実現のための課題について考えると、現状、技術面では少ないデータセットでどのように学習するかということ、個人や目標課題に合わせてどのようにチューニングするという二点を大きな課題として取り組んでいます。
前者については三次元のモデルを作成し射影することによって大量の二次元画像のデータセットを得たり、敵対生成ネットワークなどの技術によって学習用データセットを生成するなど、解決可能の糸口が考えられます。後者については、学習のために」個人に合わせたUIデザインの最適化などの対策が考えられます。また、社会面ではユーザー層へのリーチや実践コミュニティ作り、産学官の連携による人材の育成などが課題となります。
「早くAIになりたい」
以上のように、さまざまなシステムにまたがる多様なAIの実装というのは、ケースバイケースな課題解決が求められます。現状では、現場に行き、ワークショップ等を行うことによって対応しています。ユーザーと課題が与えられたときには、現場でチューニング可能なUIを作って、現場で解決してもらう実践コミュニティ自体を増やしていくのが筋の良い解決策です。
しかし、ユーザーが工場のような法人格でゴール設定が明確である場合には課題の要件ははっきりしていますが、ユーザーが個人である場合には、課題の要件が「認識・出力・動作・コミュニティや文化」のどの部分にあるのか分析していくことから始まります。人口が減少している社会においては、こういった課題抽出の部分を省人化したり自動化するなど、「広い意味でのAI化」をしないと社会問題は解決しません。落合陽一氏は、このようなことを自分自身が「早くAIになりたい」という言葉で表現していました。
産業とAI
アカデミックな論文と産業界のギャップ
計算機科学分野でのトップカンファレンス(難関国際会議)に通るアカデミックな論文といえども、そのままでは産業に応用できない場合も多いです。そのため、トップカンファで活躍している優秀な学生が、そのまま産業界で活躍できるとは限らないのが現状です。しかしながら、そういった優秀な学生が産学官を行き来できるようなエコシステムを作っていかなければ、どちらも共倒れになってしまいます。
また広くAIを産業に応用するためには、その導入コストや開発コストについても考える必要があります。例えばものづくりに関して、最適化や自動化を行うようなプロジェクトの場合、限界費用と限界効用について考えることなくプロジェクトは始められません。例えば、3Dプリンタは限界効用を増やせないため、人的リソースによる設計や管理のコストと比較したときに限界費用を減らし、それが限界効用に寄与するように使わないといけない。
その点から考えると、上記の認識器の自動化やモデルの生成などのタスクについて、時給が高い人の業務をAIで自動化していくことをコスト面でまず考えるのが先決なのではないでしょうか。人手不足を考慮しても、介護や医療のうちまず安全に導入できるところから現場課題を吸い上げていく必要があるはずです。

イルカはスマホ搭載型人類
スマートフォン以後の人類について考えるとき、漠然とシンギュラリティのようなバズワードで解釈するのでなく、ほかの生物種のアナロジーで考えてみてはいかがでしょう。例えば、イルカの音響感覚器官は非常に優れており、スマホが搭載された人類のような相互ネットワークを実現しているという報告があります。そういった音声通信に関して鋭敏な感覚を持っていると言われています。その点でイルカの脳は、数万年という長い時間の自然淘汰により最適化してきました。
ここでいう最適化について考えるとき、対象のシステムの最適化はAI分野の検討課題であり、メタ的な目線で捉えれば、生物が長い時間かけて最適化してきたものを、AIの力によって最適化することができるのかもしれません。
例えば、落合陽一氏が博士課程からずっと取り組んでいる空間に音響ポテンシャル場を作る最適化のためにはコンピュータによる最適化計算が必要です。そういったハードウェアとソフトウェアの融合により、局所的に音を鳴らすことや、局所的に光を発生させることを行ってきました。ハードウェア的に困難度が高いシステムなので、そっちに目がいきがちですが、ソフトとハードの融合したホログラム関連技術の実現のためには最適化されたものにさらに情報を乗せる必要があり、困難な課題の一つと考えられます。そういった観点から落合陽一氏の考える次のAIの主軸は、今スマートフォンに代表されるカメラディスプレイマイクスピーカーの組み合わせだけではない、音や光の最適化計算を、人間の認識とつなげていくことです。
日本の産業は撤退戦
そういった自動化、省人化、身体補助、工業の効率化を今考えないといけないのはなぜでしょうか。今、日本の人口ピラミッドは海外メディアによれば、「棺桶型」とも言われていて、日本の人口は減少の一途をたどっています。これまでは日本はハードウェアとしてものをつくる国家でしたが、今後は、近代の産業形態とは別のアプローチをしていく必要があり、日本の生産力について考えるときその再興戦略において自動化省人化を含む広い意味でのAI活用が肝要となります。
少子高齢化社会では、身体ダイバーシティ、人間の補助や能力の強化に関する需要は増加していきます。高精度なセンサーや処理の重い計算機資源にはコストの問題があり、産業としてすぐ応用が効くものとは限りません。今コモディティ化しているスマートフォンなどのハードウェアと、安価に入手可能なGPUを積んだPCの計算コスト内でどこまでのことができるかということを考える必要があります。
産業のエッジケースをブロックチェーンのようにスケールメリットが低いものに置き換える。このような最適化、業界や業態のコンサルティングをAIで行うことの価値が高まっていくと考えられます。
Find a worthy problem
イノベーションが起こる領域について考えると、課題が未知か既知かという軸と、解決策が未知か既知か、もしくは単純かという軸によって、6つの領域に分類されます。今、すぐに産業応用を考えるときにAIが活躍すると考えられる領域は、課題も解決策も既知であるDeploy & Scaleの領域か、解決策は既知であるが課題は未知であるFind a worthy problemの領域です。
前者に関してはテックスタートアップを繰り返すこと、後者に関しては我々が足を使って価値のある問題を発見することによって、イノベーションを起こすことができるはずです。試行回数が重要なことだと思います。
超AI時代での生き方
知的生産はストレスフル
20世紀は、工業化や大量生産の時代であり、その勤務時間について考えるときにタイムマネジメントという価値観が重視されていました。21世紀はタイムマネジメントではなく、ストレスマネジメントの時代です。知的生産というのは本質的に脳負荷による」ストレスのかけ具合との調整なので、どうやって認識負荷を下げ、どこをディスパッチすることによってストレスを減らすことができるかということに、自動化テクノロジーやAIを活用していくことが必要です。
世を捨てよ、クマを狩ろう
我々は、かつては狩猟民族でした。農耕の発明によって、将来の糧のために働くようになりました。工業社会となった現代も農耕時代とは本質的には変わらず、将来の賃金のために会社で働いています。このことは狩猟民族の血が流れる我々にとって同じことを繰り返し、短期的にその恩恵に預かれない状況はストレスフルですし、課題や困難に向かい合いながら日々のゴールを目指して生きていくことが向いているのではないでしょうか。堀江貴文氏の『多動力』などの本が流行していることの理由も、我々に流れる狩猟民族の血にあると僕は個人的には分析しています。
突発的なゴール、倒すべき目標に立ち向かうことを繰り返すことが、狩猟民族たる我々のDNAに刻まれているのかもしれません。そのため、どのように狩猟民族としての本能と会社生活を調和させていくかを考えていく必要があることでしょう。
会社生活と狩猟民族の血を両立させるために、会社を辞める必要はありません。自分の手で最初から最後までプロダクトを作ることを提案します。クマを狩るツールとしてコモディティ化しつつあるAIやAIのプログラミングを行うプラットフォームを活用できます。クマという課題に対して、副業として数人で週末に取り組むことによって、狩猟民族としての本能を満足させることができます。
まだ能力的に成熟しておらず、金銭的な制限に縛られている学生でも、課題さえ発見できれば解決することができます。現代には課題を発見できる人間が少ないですが、限界費用の安いソフトウェアやAIを用いた副業、特にオープンソースによる貢献に対して企業が金銭を支払う制度を作れば、社会は良くなっていくに違いありません。
落合陽一氏は、最後に再び「世を捨てよ、クマを狩ろう」と繰り返し、講演を締めくくりました。
■AI専門メディア AINOW編集長 ■カメラマン ■Twitterでも発信しています。@ozaken_AI ■AINOWのTwitterもぜひ! @ainow_AI ┃
AIが人間と共存していく社会を作りたい。活用の視点でAIの情報を発信します。