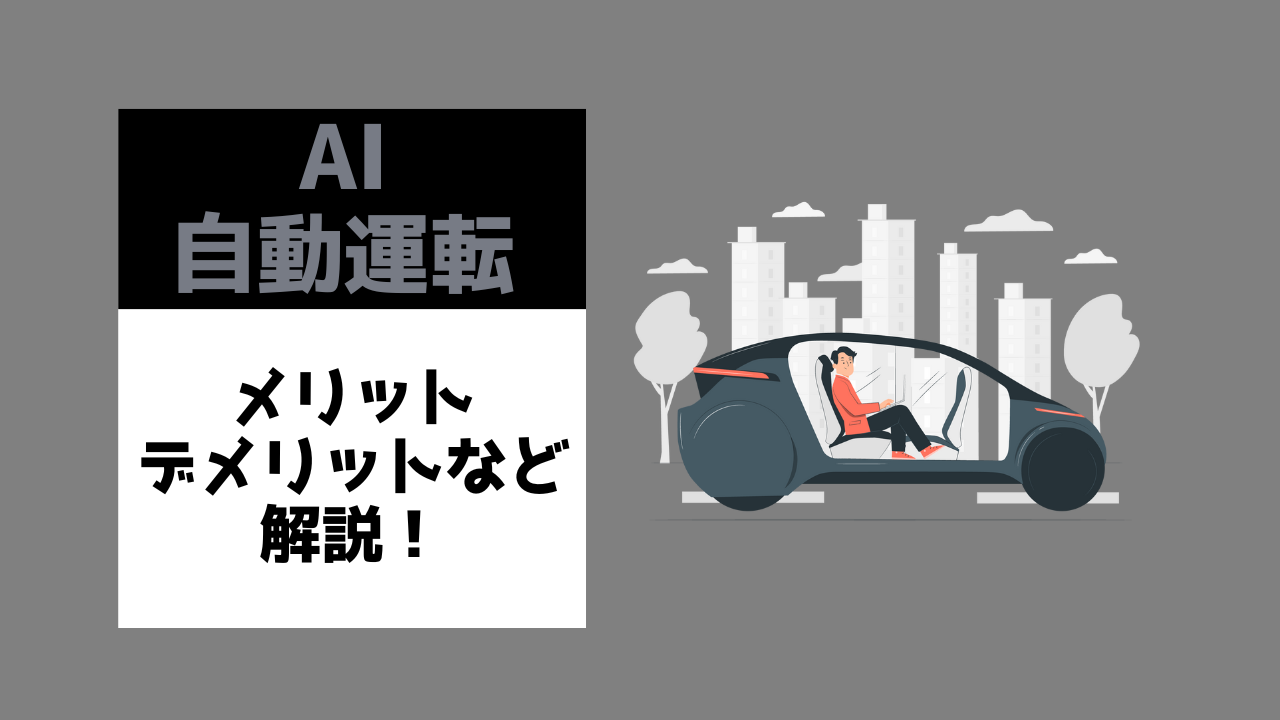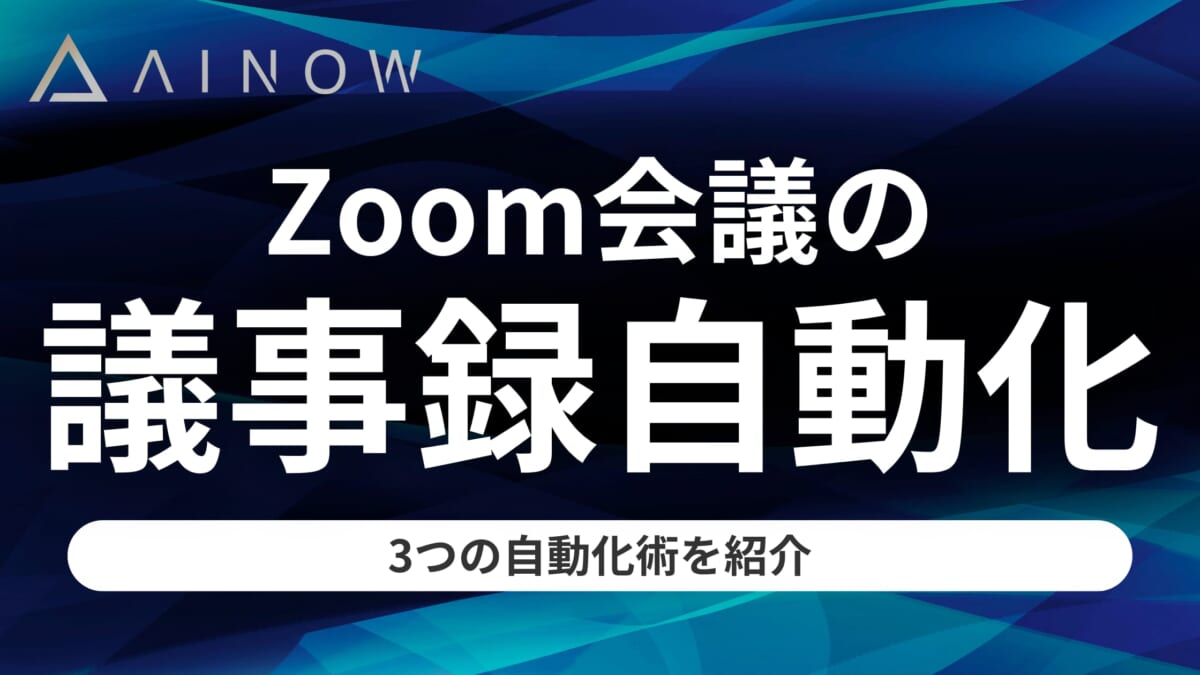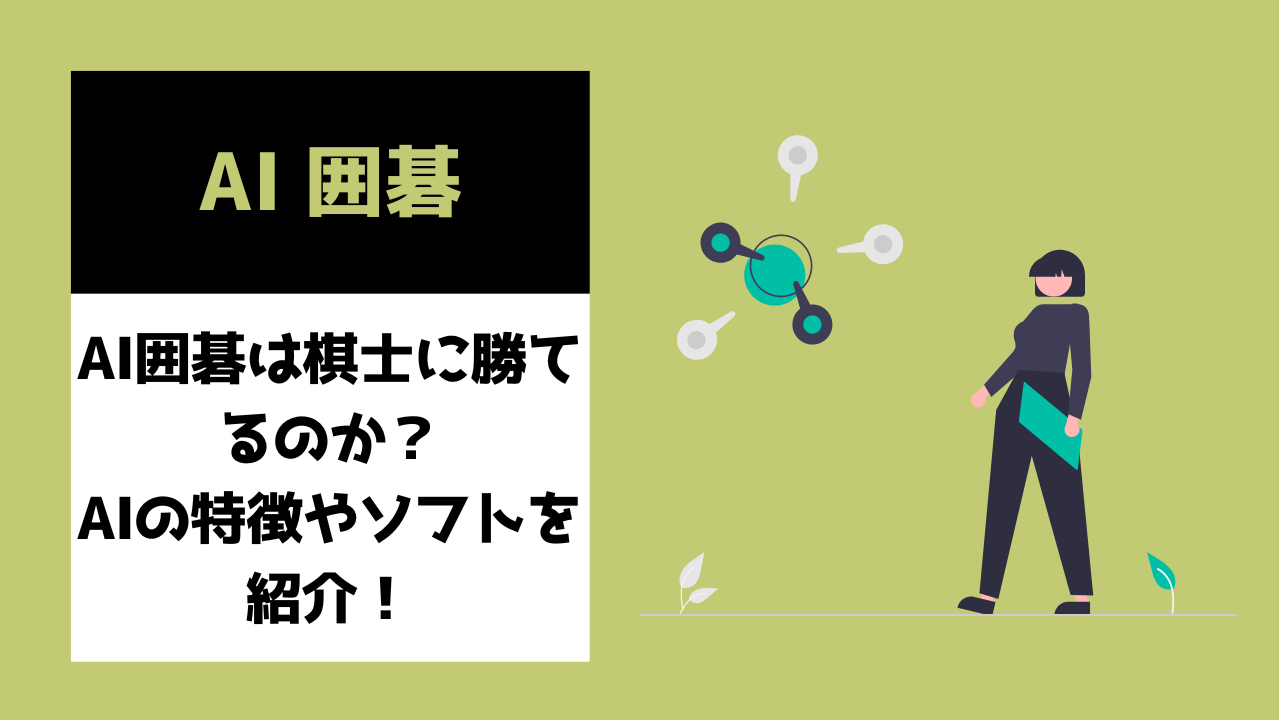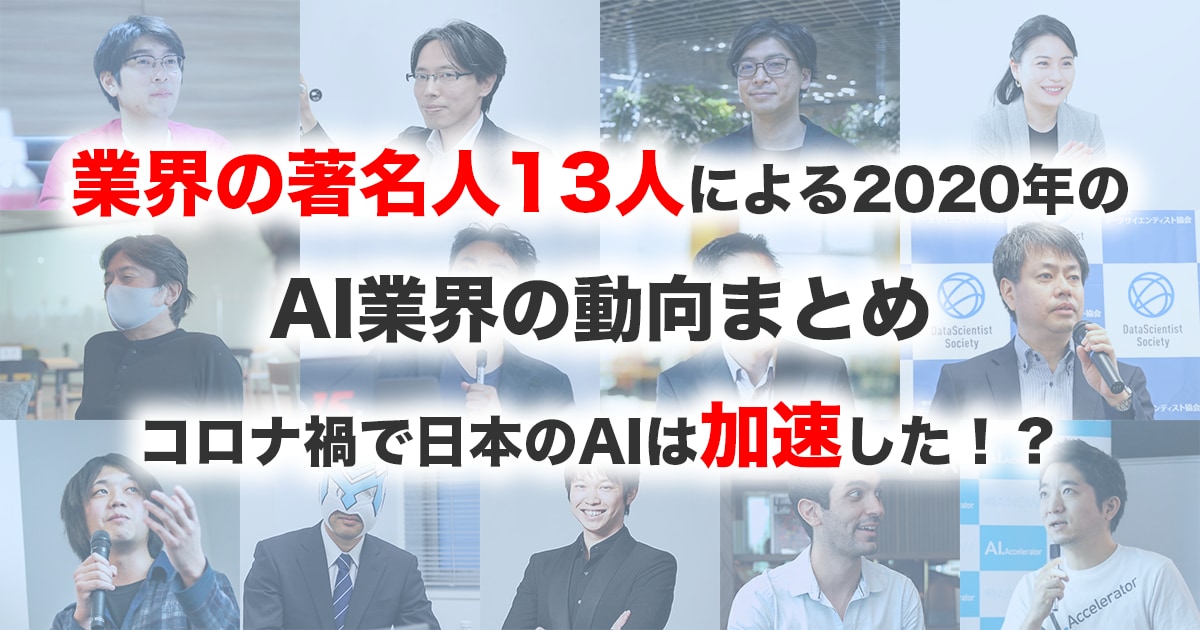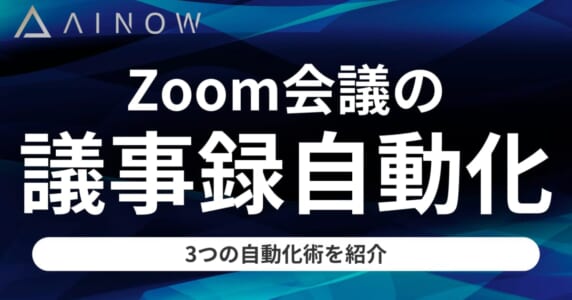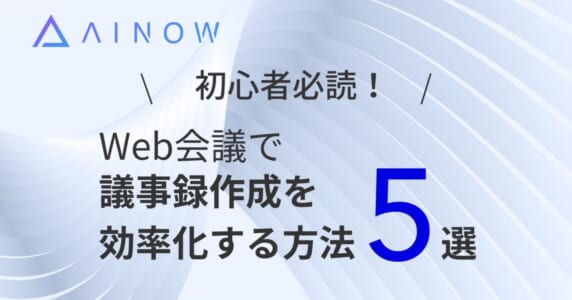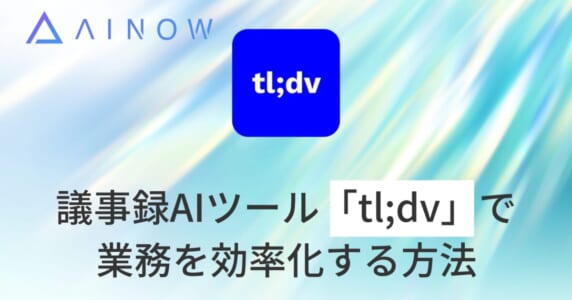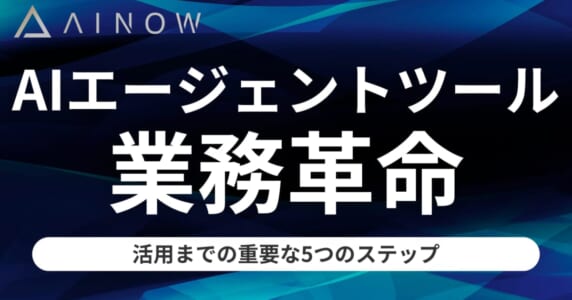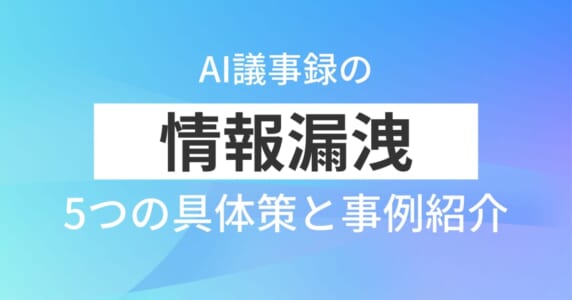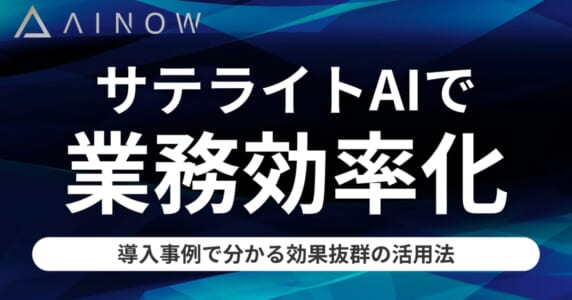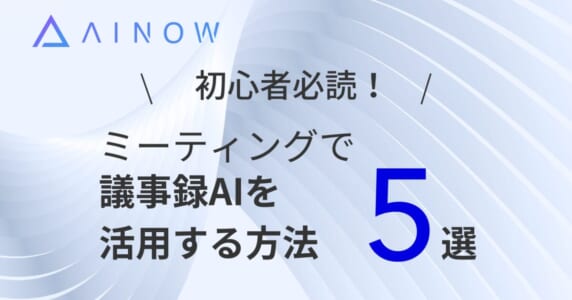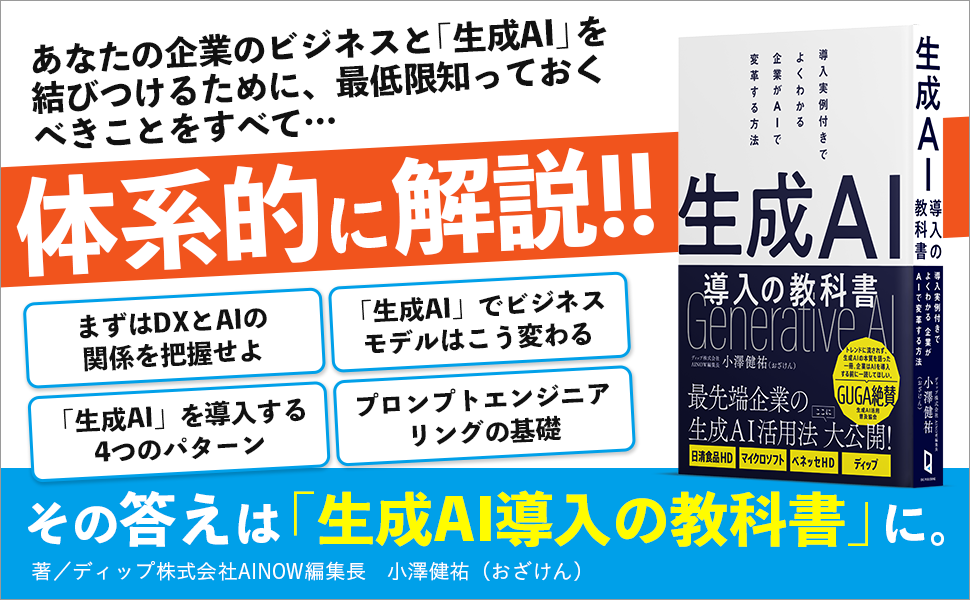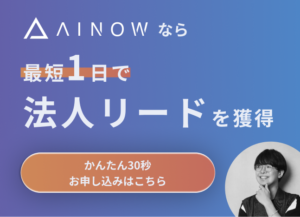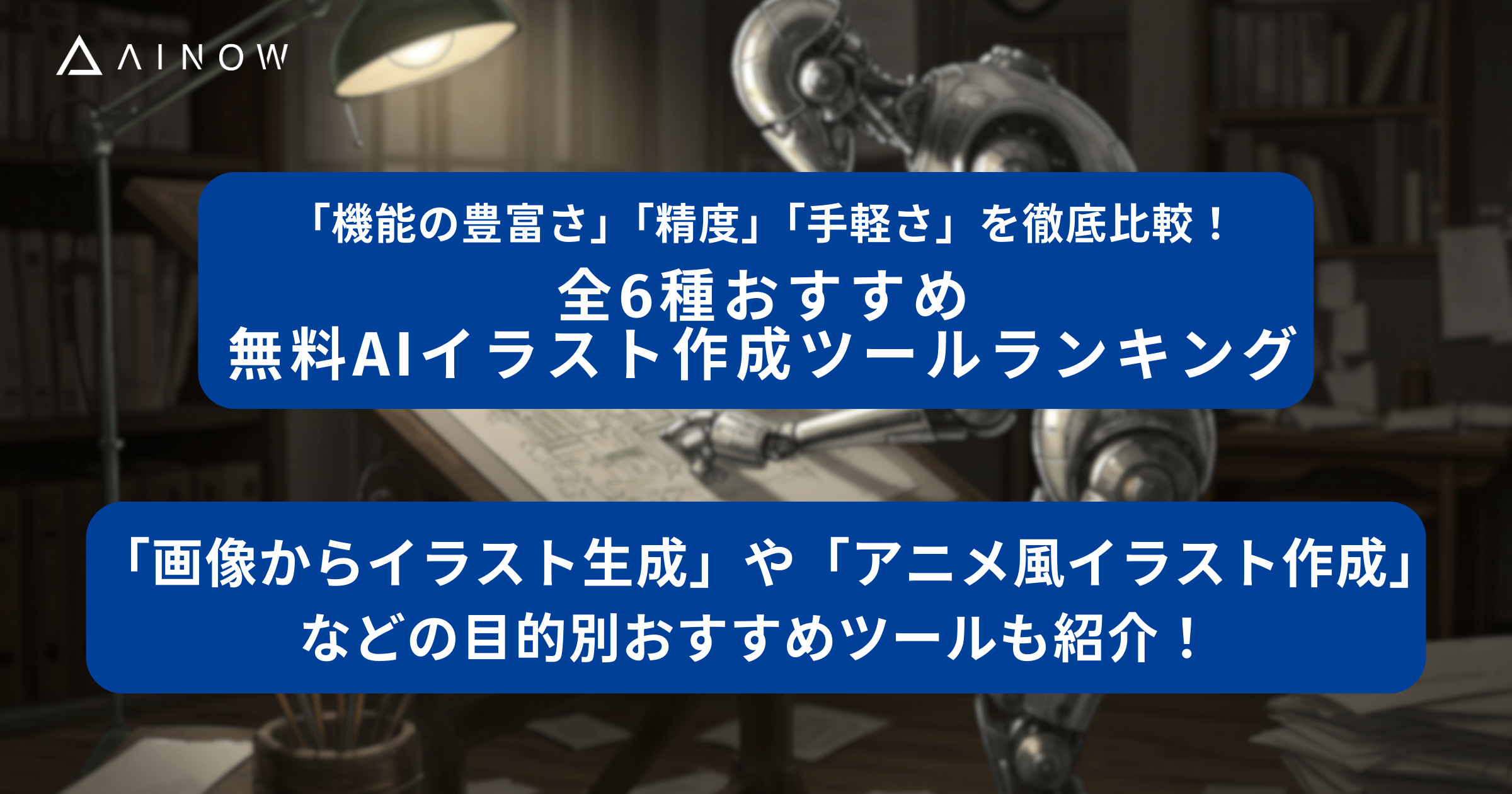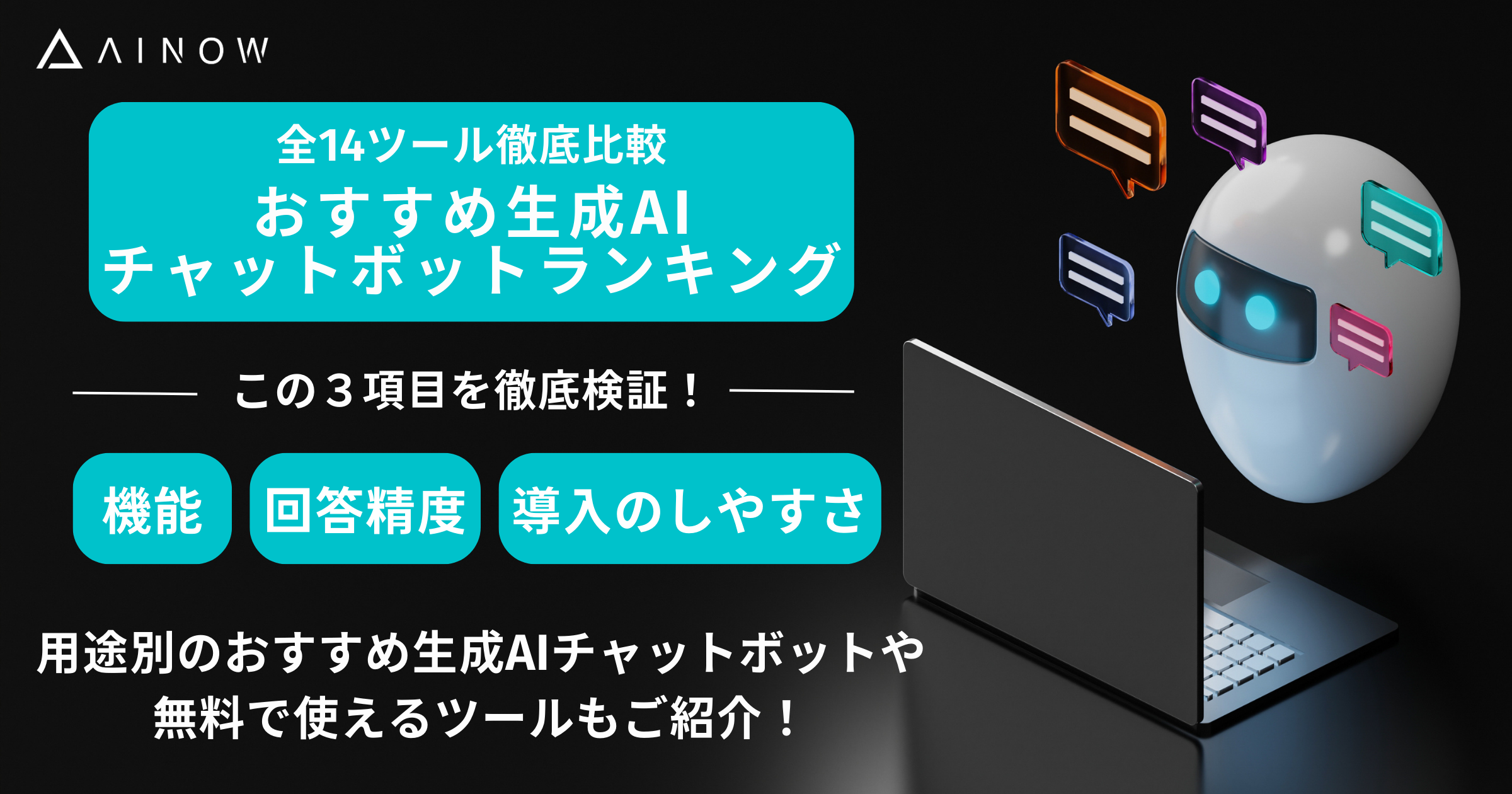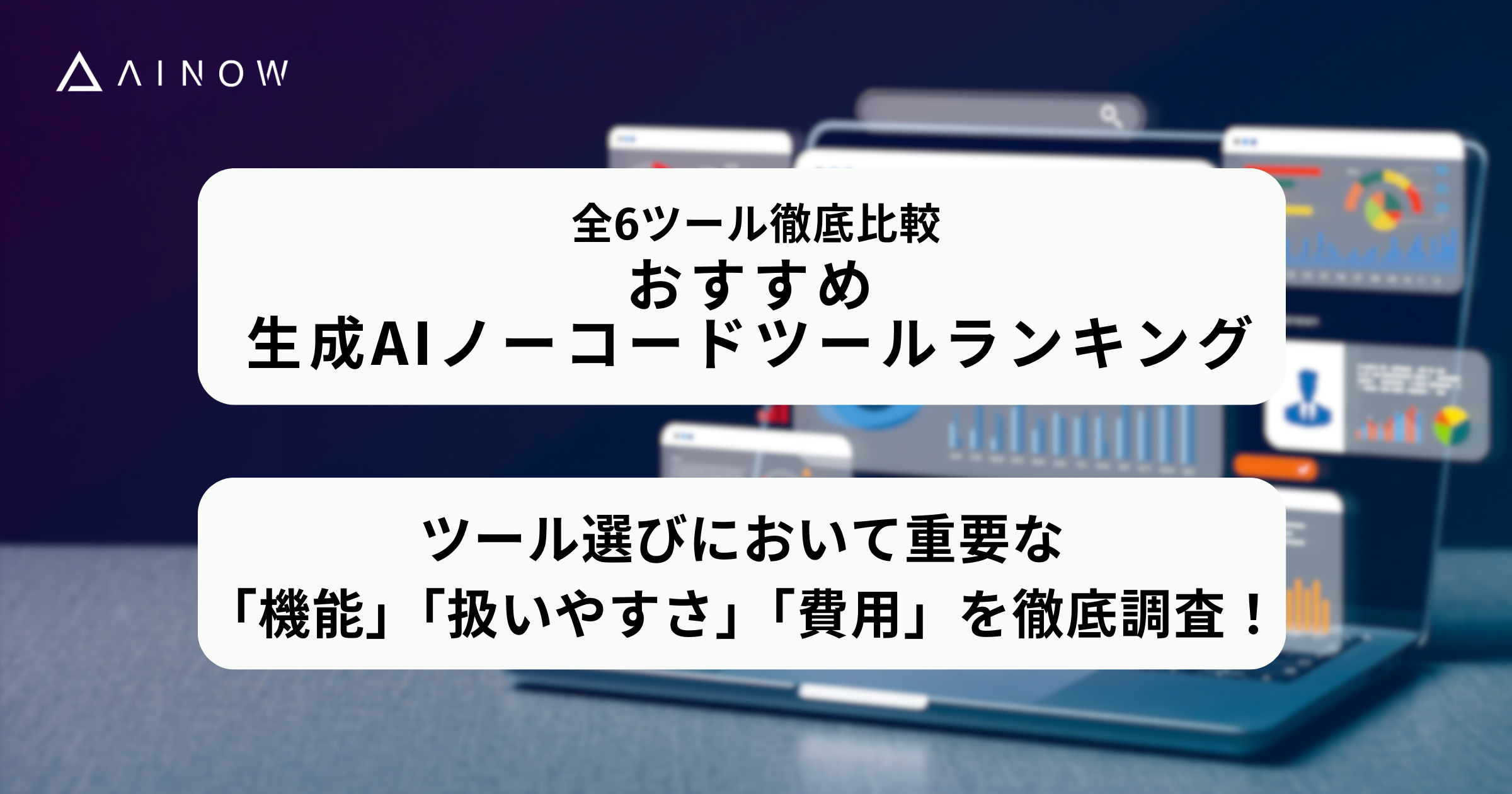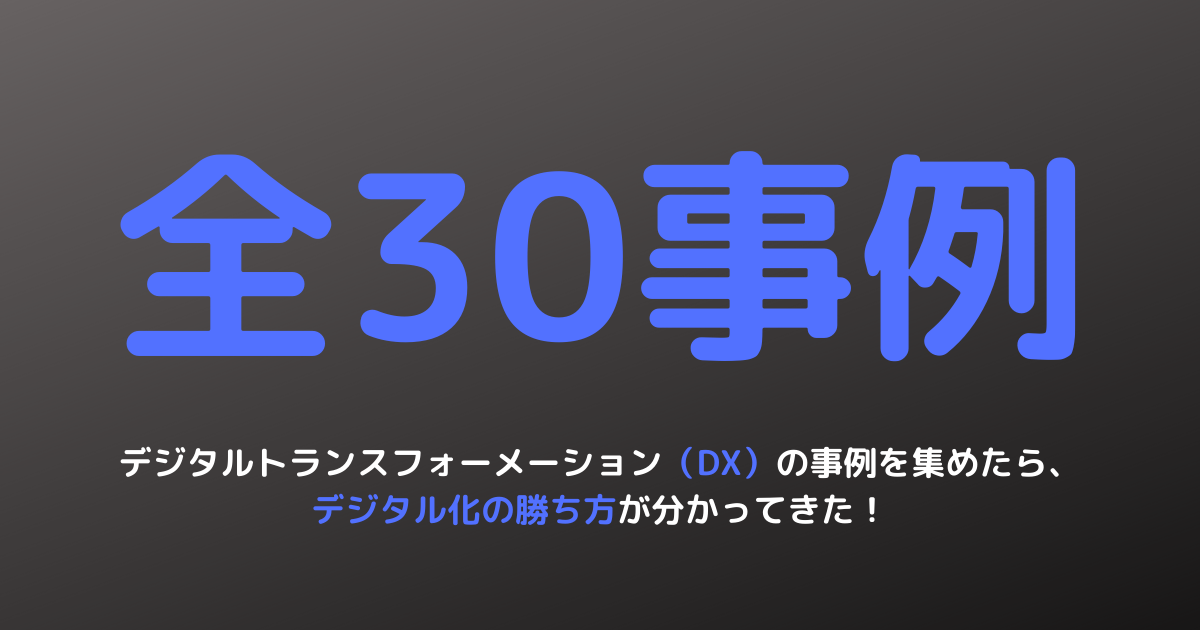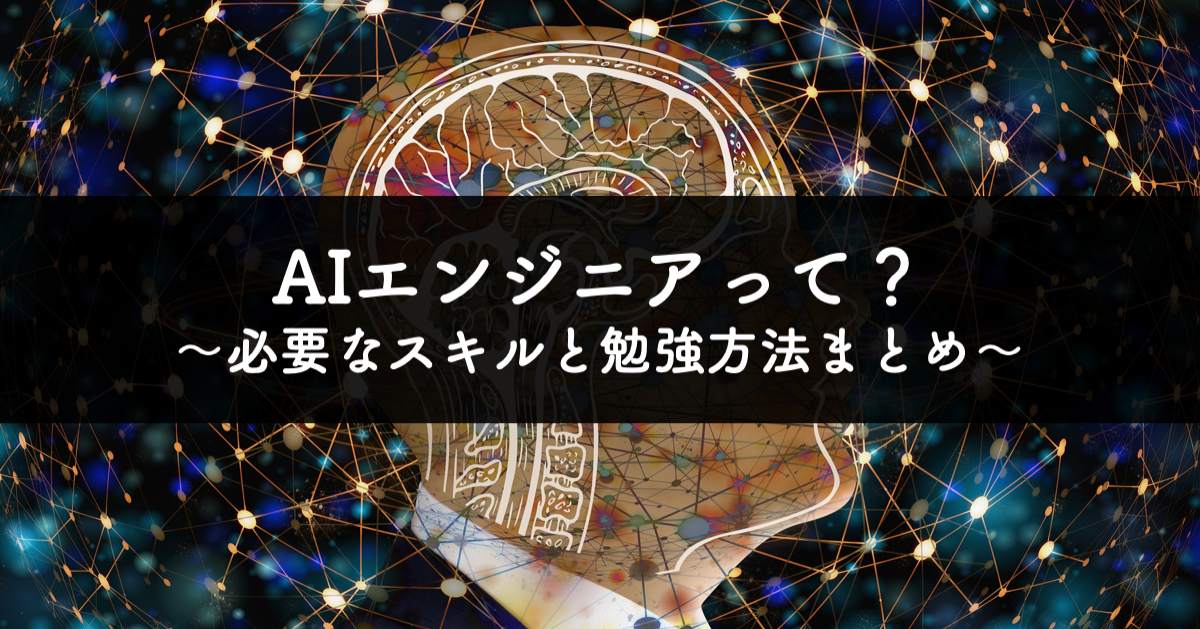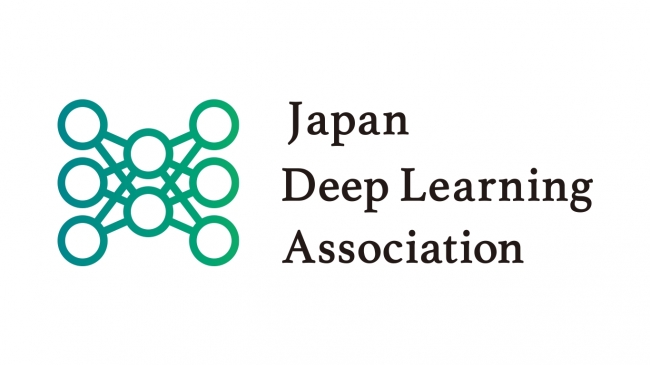生成AIの普及に力を注ぎ、幅広いユーザーにその価値を届けるために尽力するusutaku氏(@usutaku_copilot)。彼の過去から現在までの軌跡を振り返り、テクノロジーへの好奇心から起業家としての道のり、生成AIとの出会い、そしてSNSでの成功に至るまで、その情熱と取り組みに迫ります。
目次
生成AIに力を入れるusutaku氏の過去から現在まで
生成AI技術をより広いユーザーに届ける取り組みをしているusutaku氏。本章では、彼の過去から現在までの歩みを振り返り、その情熱と取り組みを探ります。
テクノロジーへの好奇心
ーーusutaku氏がテクノロジーに興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか。
usutaku氏:小さい頃、両親がよくテニストーナメントを企画していて、そこでお客さんが喜びそうなものを業務スーパーで仕入れて売る経験をさせてもらったんです。自分で値段をつけて売ると、たくさんのお客さんが買ってくれて、小学生ながらにお小遣いをたくさんもらえた。そういう体験から、自分で何かを生み出す楽しさを知りました。
小学2、3年生の頃には、当時まだYouTubeが一般的でなかった時代に、Windowsムービーメーカーでゲーム実況動画を作ってYouTubeに上げていました。昔から新しい技術で何かを作るのが好きだったんです。
起業家を目指すきっかけ
ーー起業家を目指すようになったのは、いつ頃からですか。
usutaku氏:高校生の頃から起業に興味があって、高校生向けの起業イベントに参加したり、物販をやったりしていました。大学生になると、ベッコアメ・インターネットの尾崎憲一さんやサイバーエージェントの藤田晋さん、堀江貴文さんの著書を読んだりして感銘を受けました。同時に、この方々と比べて自分はまだ何もできていないという思いもありましたね。
生成AIとの出会い
ーーusutaku氏が生成AIの分野に惹かれたのは、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
usutaku氏:大学時代、PKSHA Capitalでインターンをしていて、AIと機械学習の基礎は学んでいました。ただ、その時はまだすべてをベットするほどの魅力は感じていなかったです。転機が訪れたのは2022年11月にChatGPT 3.5に触れた瞬間、これは自分がベットすべき技術だと感じました。すぐに最初のプロジェクト『GPTPlay.net』を立ち上げ、プロンプトの共有サイトを作成しました。
ここまで全力でベットできたのは、その前にあったクリプトブームの際は勇気がなくて参入できず、周りが次々と億万長者になっていく姿を見て本当に悔しい思いをしたというのが大きいです。だからこそ、次に来るものには必ず飛びつこうと心に決めていました。ChatGPTを触った瞬間、これだと確信したんですよね。
SNSでの成功とAI普及に向けて
ーーSNSでの発信で成功されていますが、どのようなことを意識されていたのでしょうか?
usutaku氏:AI関連の質の高い発信はXのテキストコンテンツに偏っており、XのアルゴリズムとしてAIに興味のないユーザには情報が届きにくいことを感じていました。そこで、あえて手間のかかる動画プラットフォームの生成AI市場に目をつけ、AIを知らない一般層に届けるためにインスタグラムやTikTok、YouTube Shortsを活用しました。投稿を続けていくことで、これらのプラットフォームでバズることに成功し、一般層を含む生成AIの幅広い認知に貢献できました。
ーーSNSでの発信を通して、印象に残っているフィードバックなどはありますか。
usutaku氏:普段AI界隈の情報に触れない人たちからの反応ですね。例えば、海外の大学院に進学した日本人学生から「usutakuさんのおかげで論文を楽に読めるようになった」とか。地方の中小企業経営者や学校の先生で「AIの研修は高すぎて手が出ないけど、usutakuさんを知れて本当によかった」といった声を直接いただけるのは本当に嬉しいですね。
逆に、アンチコメントも多いんです。「AIを使うのは情報漏えいだ」とか「お前じゃなくてAIが優秀なだけ」みたいな。これらのコメントはむしろ、AIを批判的に捉える人たちにもSNSを通じて情報が届いていると前向きにとらえています。ちなみに、動画自体の高評価率は97-99%なので、大多数の人には有益な情報だと捉えてもらっています。
日本の企業や個人の生成AI普及に向けて
usutaku氏は、生成AI技術の普及に向けて日本の企業や個人にどのように働きかけているのか、その考えとビジョンを伺いました。
生成AIの利用状況について
ーー生成AIの利用状況についてどのように考えられていますか?
usutaku氏:ChatGPTはできることが多すぎて一般層には受け入れられにくいと感じています。非常に多機能であるため、一般層には少し難解に感じられることがあります。一方で、例えばスライド生成ツールのGammaは、AI機能を増やすのではなく、スライド編集機能を強化しています。ここから見えるのは、今後AIは「AIツール」として流行っていくのではなく、素晴らしいツールの中にユーザーがAIと気づかないように、サービス体験にサラッとAIが組み込まれていくのが今後主流になる、と考えています。それがうまく実現した時、初めて一般普及すると言えます。今のChatGPTのようなUIじゃ、ほとんどの人がうまく使えないのは当たり前だと思います。
Microsoft Copilotの可能性
ーーusutaku氏はMicrosoft Copilotをインフルエンサーの中でも真っ先に発信されていましたが、こちらに注目したのはなぜでしょうか?
usutaku氏:Microsoft Copilotに注目したのは、Microsoftがこの技術に力を入れたら普及するだろうと直感的に感じたからです。2022年6月に発表された際、これは将来的に大きな影響を与えるだろうと思いました。特に、日本の企業は新しいツールを導入する際に慎重ですが、Microsoftが提供するツールであれば信頼して導入する企業が多いです。実際、ExcelやWordを使っていない大企業を探す方が大変なくらいです。Microsoftが提供するツールを社内で使うことを必須としている会社が多いので、MicrosoftがAIツールであるCopilotを発表したことで、今後の普及は早いと感じました。
余談ですがCopilotは、ChatGPT等と比べて活用事例が世に出ていません。これは、シンプルにSNSの情報発信者は基本ベンチャーなので、高いライセンスを払ってMicrosoft 365を使うよりGoogle Workspaceを好む傾向にあり、Copilot for Microsoft 365を使う機会がないからなんですよね。僕の場合はCopilotを使うためにあえてMicrosoftで統一しています。
日本企業のAI導入の課題
ーー日本企業のAI導入の現状と課題についてどう思われますか?
usutaku氏:現在、生成AIは『Nice to Have』(あったほうが良い)と見なされることが多いですが、生成AIの活用に成功している企業の多くは経営層がAIの必要性を強く認識しています。例えば、経費精算ツールのように、ツールとして欠かせないものだという認識を経営陣が持たない限り、真の導入は難しい。現場レベルの意識改革はもちろん大事ですが、やはりトップの理解が何より重要だと感じています。
AIの個人利用の推進
ーー個人のAI利用に関してはどう思われますか?
usutaku氏:個人の皆さんにはぜひ一度AIのすごさを体験して欲しい。最初は使い方が分からなくて挫折する人も多いと思いますが、うまく活用できた時の感動は忘れられないはずです。まずはライトな気持ちで触れてみることから始めてみてください。プロンプトに頼らず、日常的に使っているツールとの自然な融合こそが、AIの真の力を引き出す鍵になると信じています。
まとめ
このインタビューを通じて、usutaku氏がどのようにして生成AI技術にたどり着き、その普及に力を注いでいるかを紐解いていきました。
幼少期からのテクノロジーへの好奇心に始まり、起業家としての道を歩み始めたのは高校生の頃。大学時代にAI技術と出会い、その可能性に魅了され、2022年にはChatGPT 3.5との出会いが転機となり、現在は生成AI技術を日本の企業や個人に広める活動に注力しています。
SNSでの発信では、いち早く動画プラットフォームのニーズを捉え、質の高いコンテンツを提供し続けています。これにより、AIを知らない一般層にも情報を届けることができ、生成AIの認知拡大に大いに貢献しています。Microsoft Copilotに注目したのも、企業が新しい技術を導入する際の慎重さを見越したものでした。Microsoftの信頼性が、AI導入のハードルを下げると確信し、真っ先に発信を始めました。
彼は時代の流れを読み、AI技術がサービス体験に自然に組み込まれ、一般の人々にも普及する未来を見据えています。これまでのusutaku氏の取り組みは、生成AI業界に大きな影響を与えており、今後も彼の活動から目が離せません。
執筆:林 啓吾
編集:おざけん