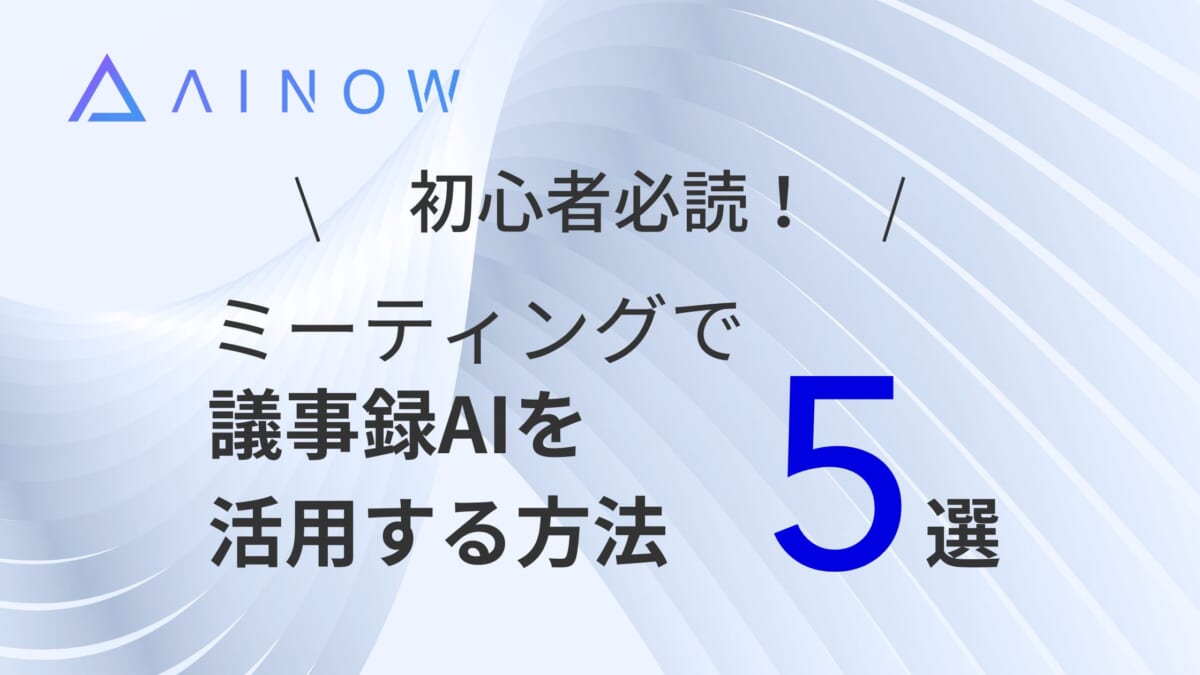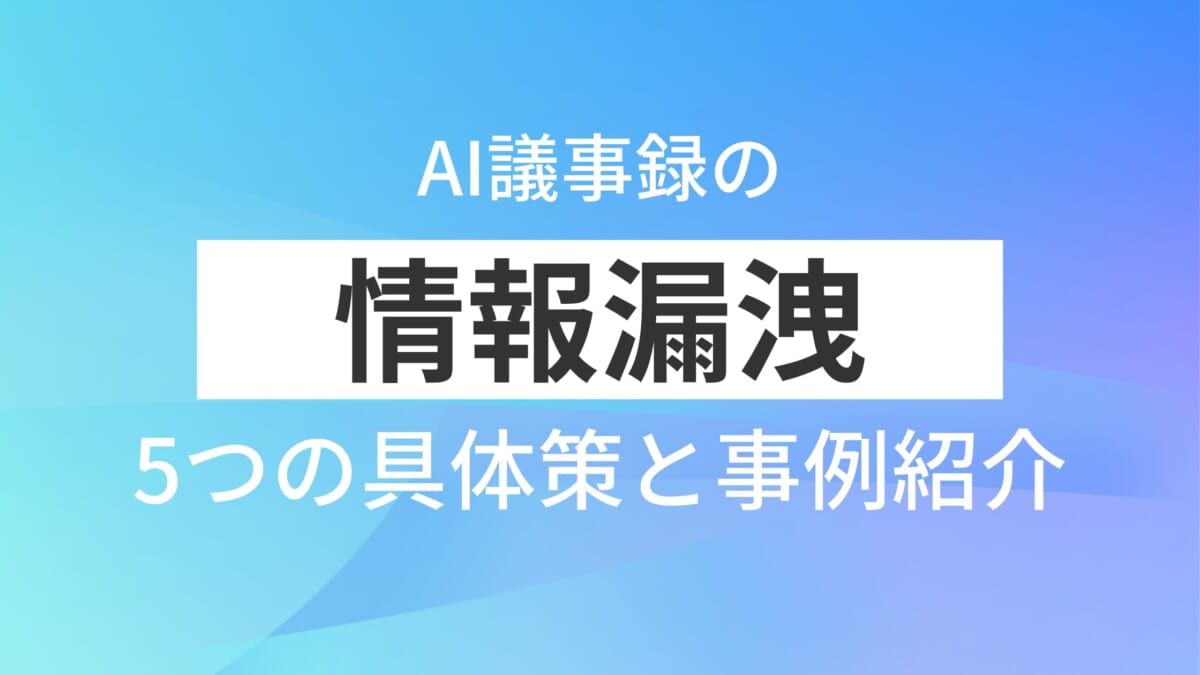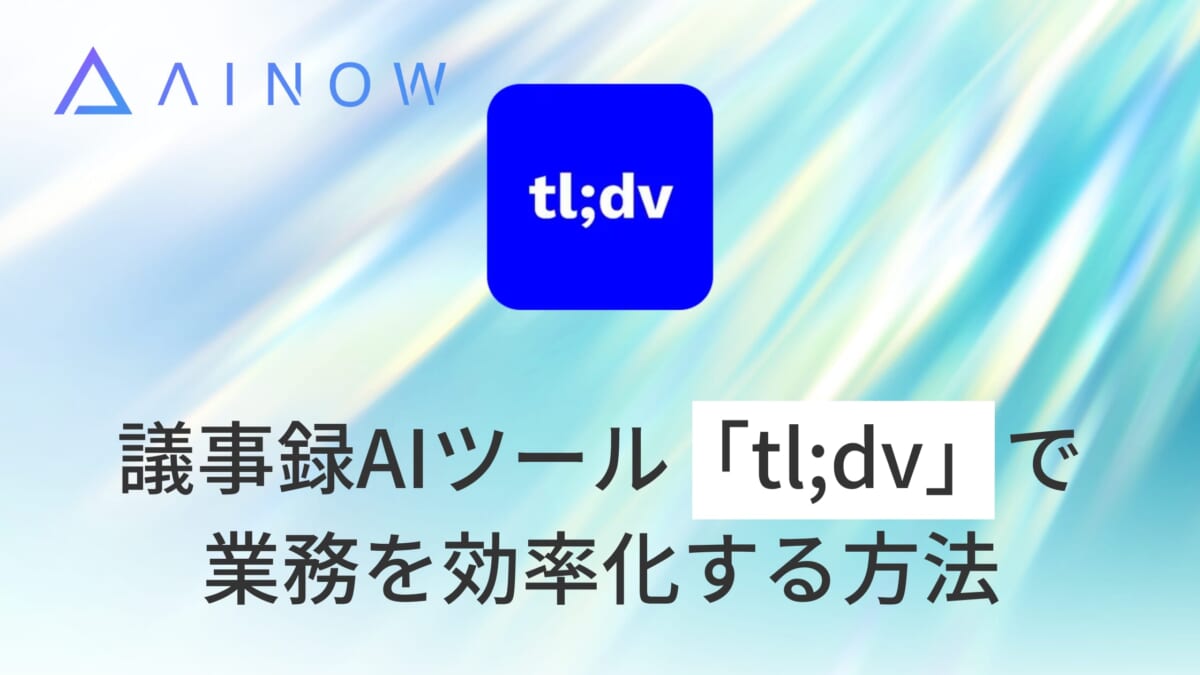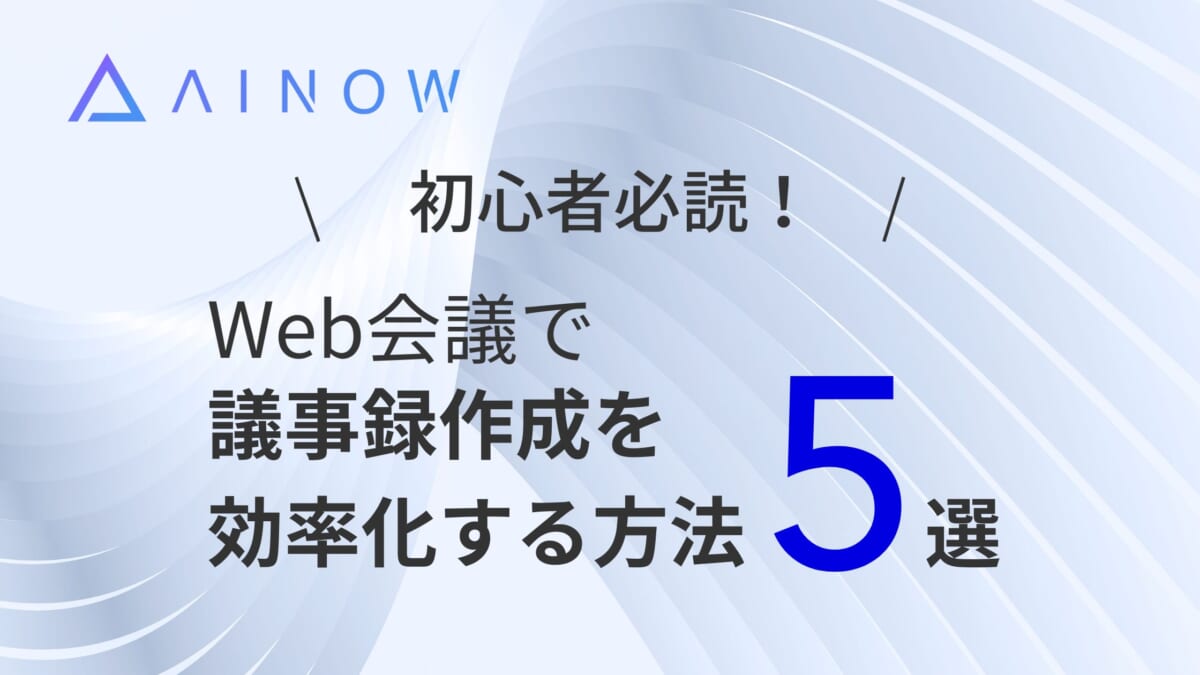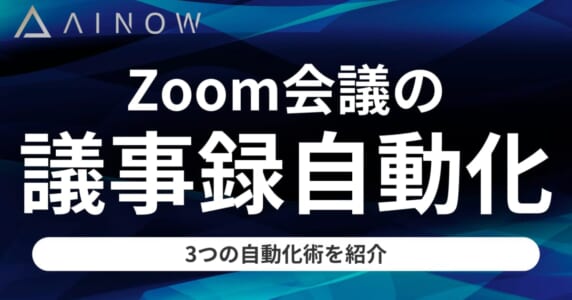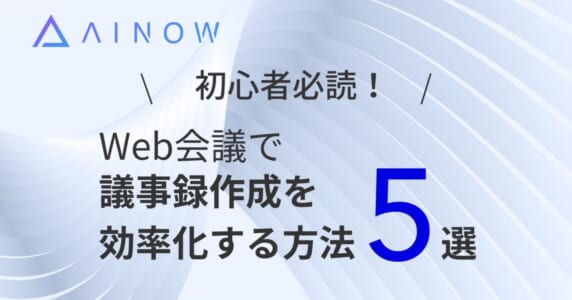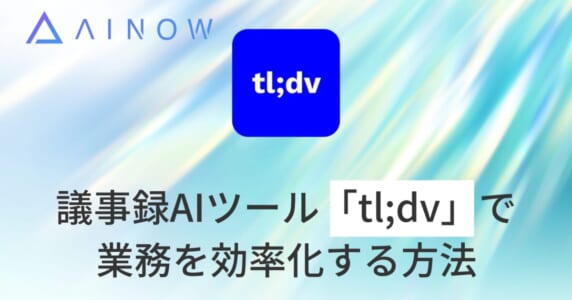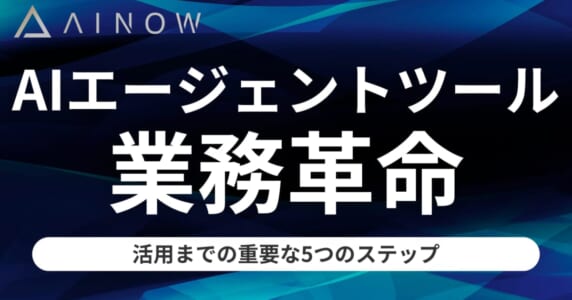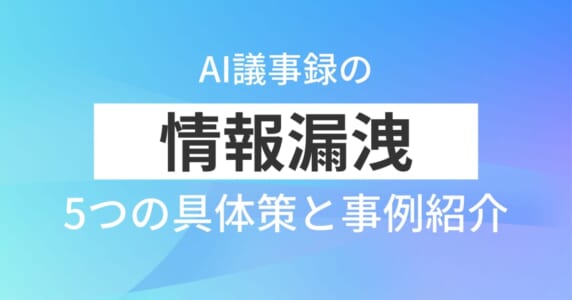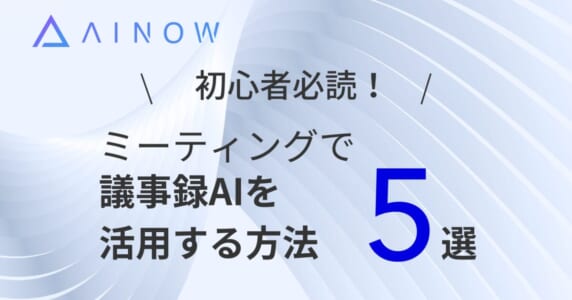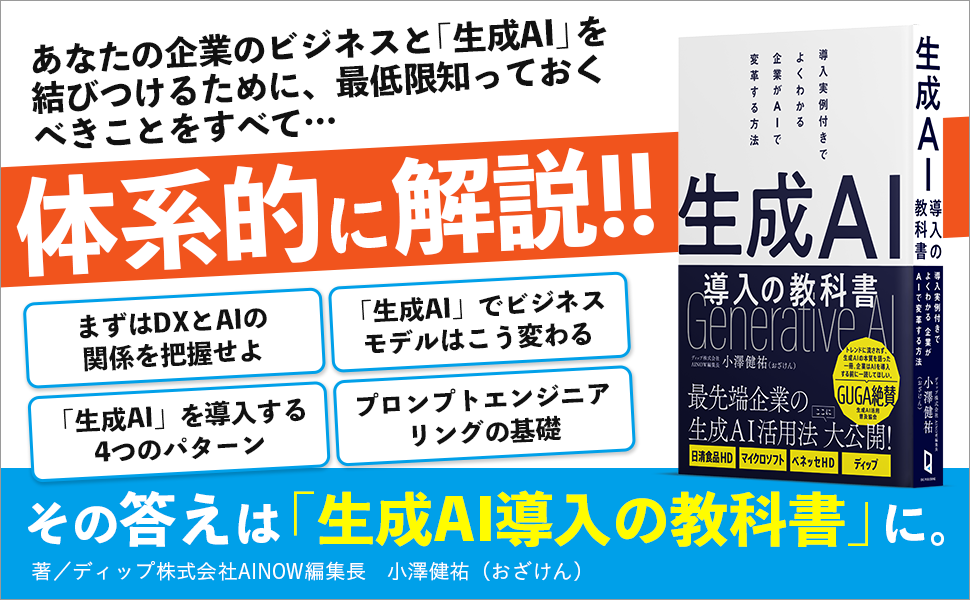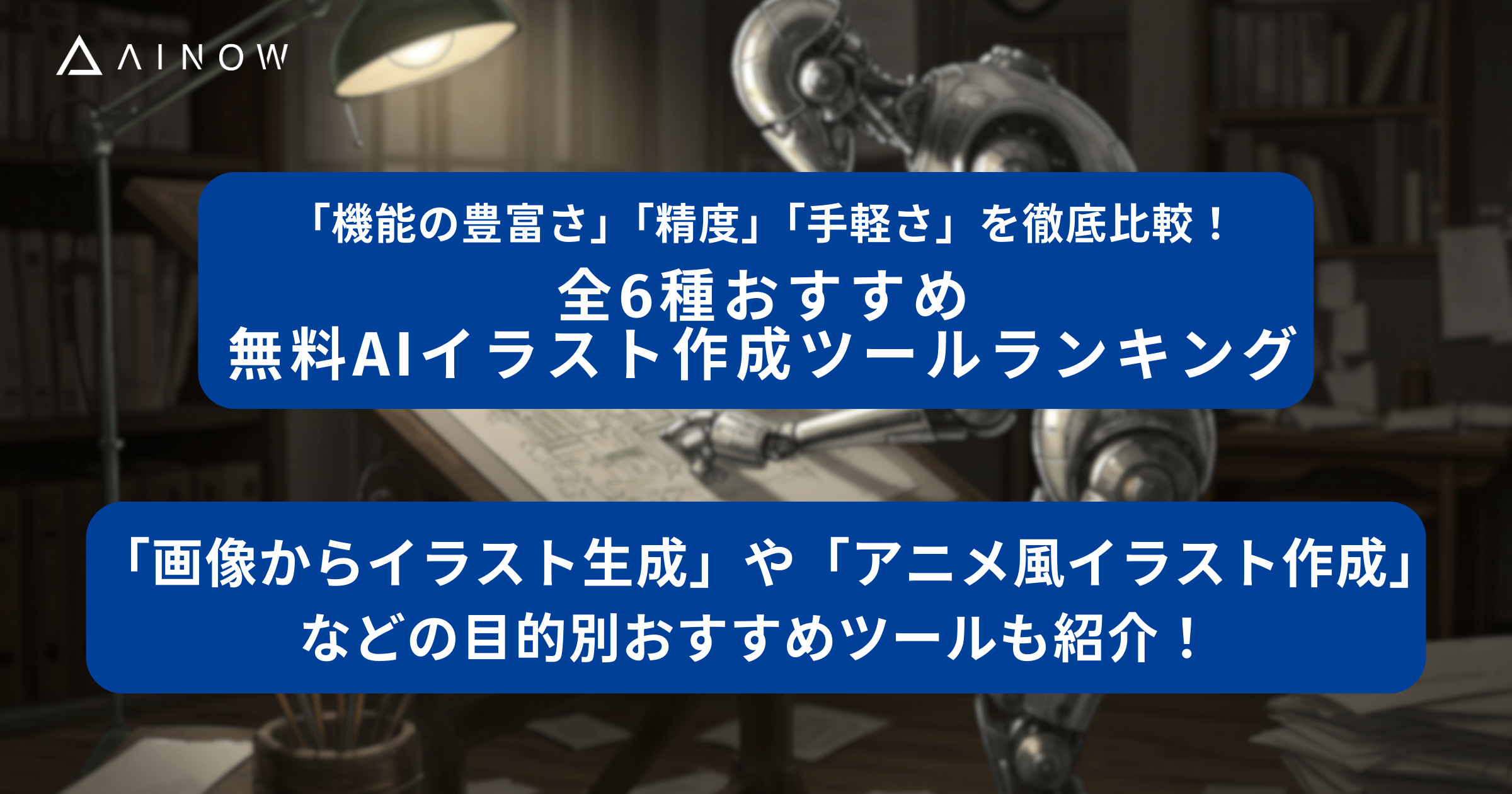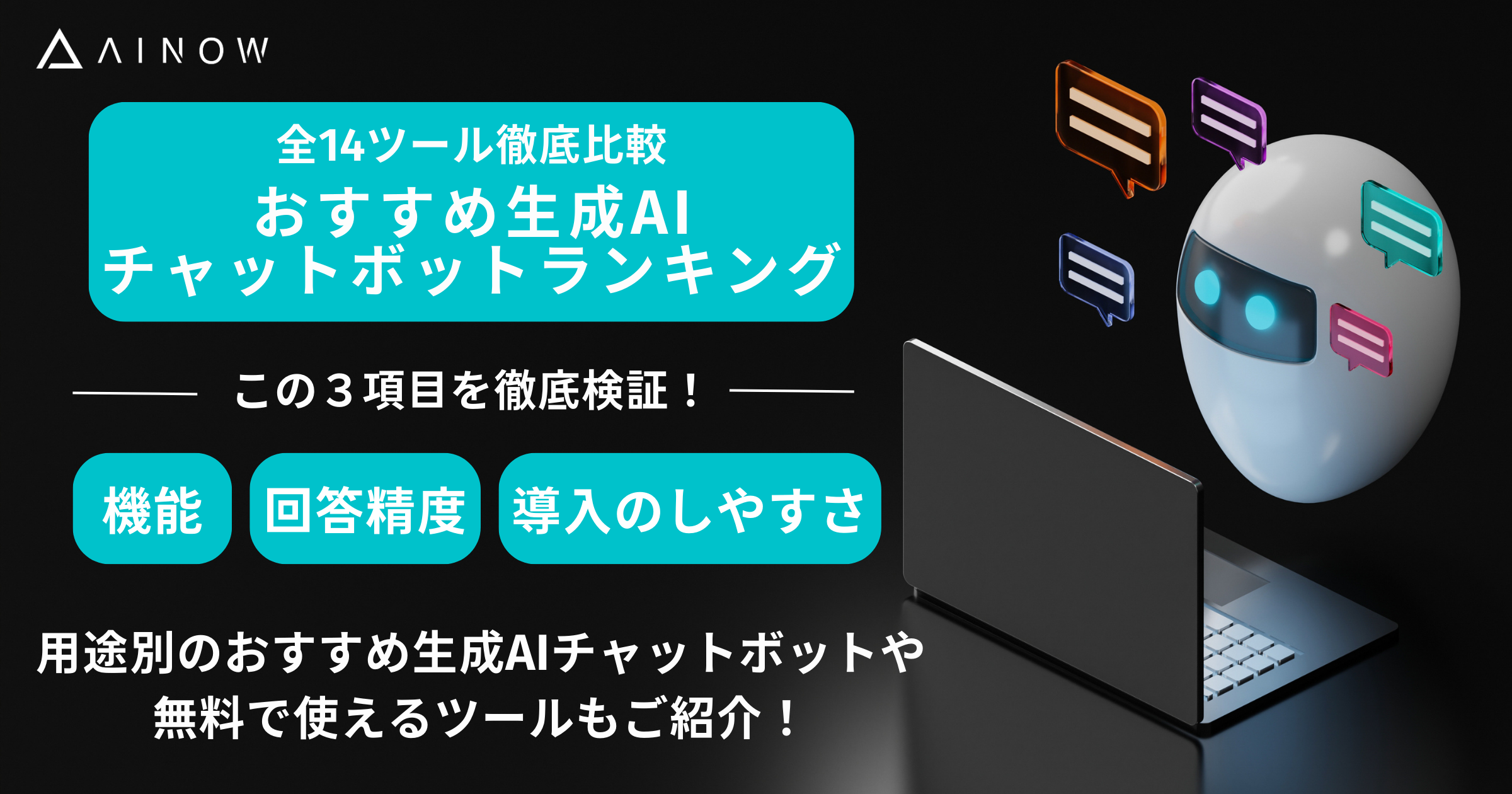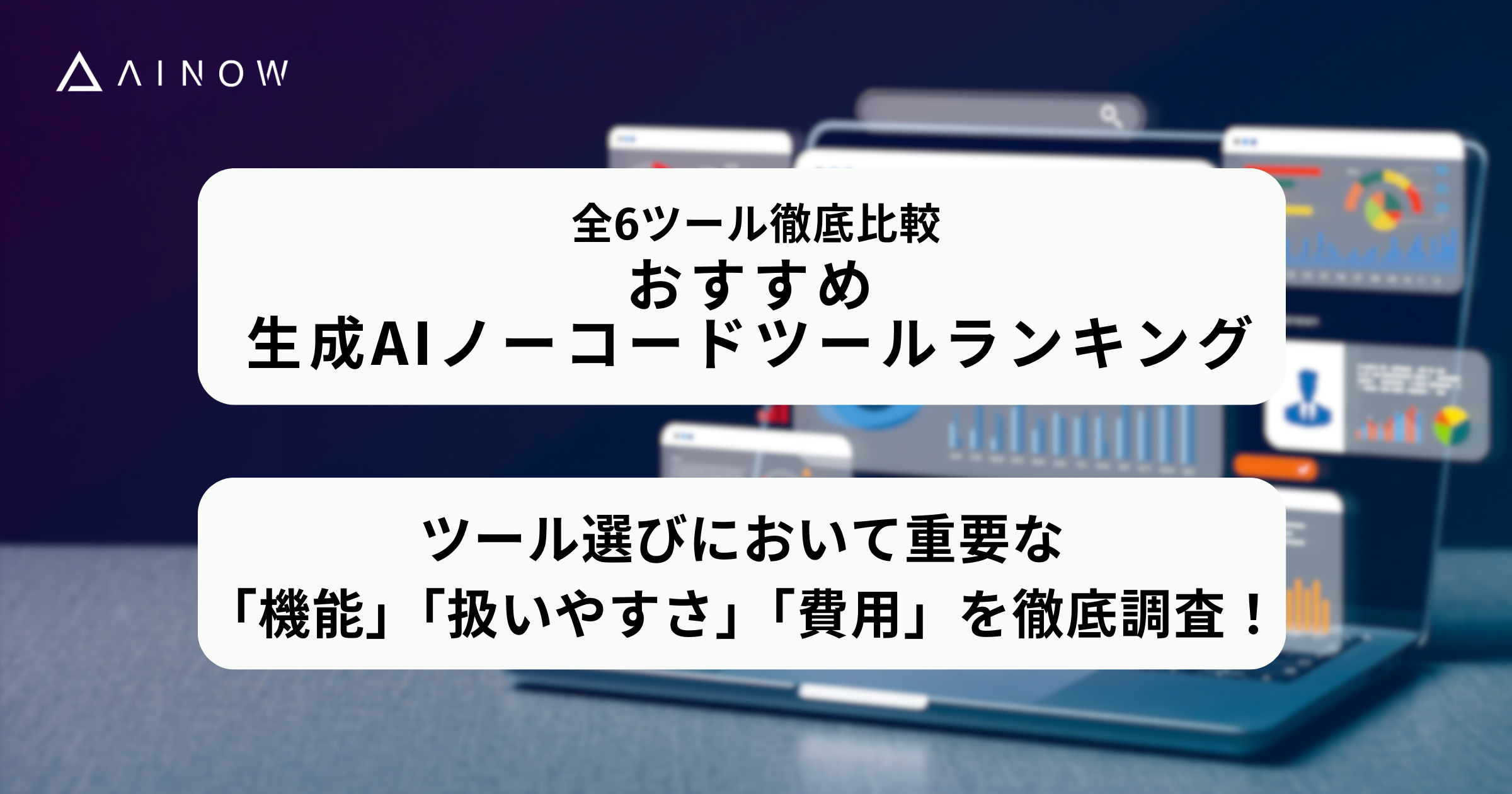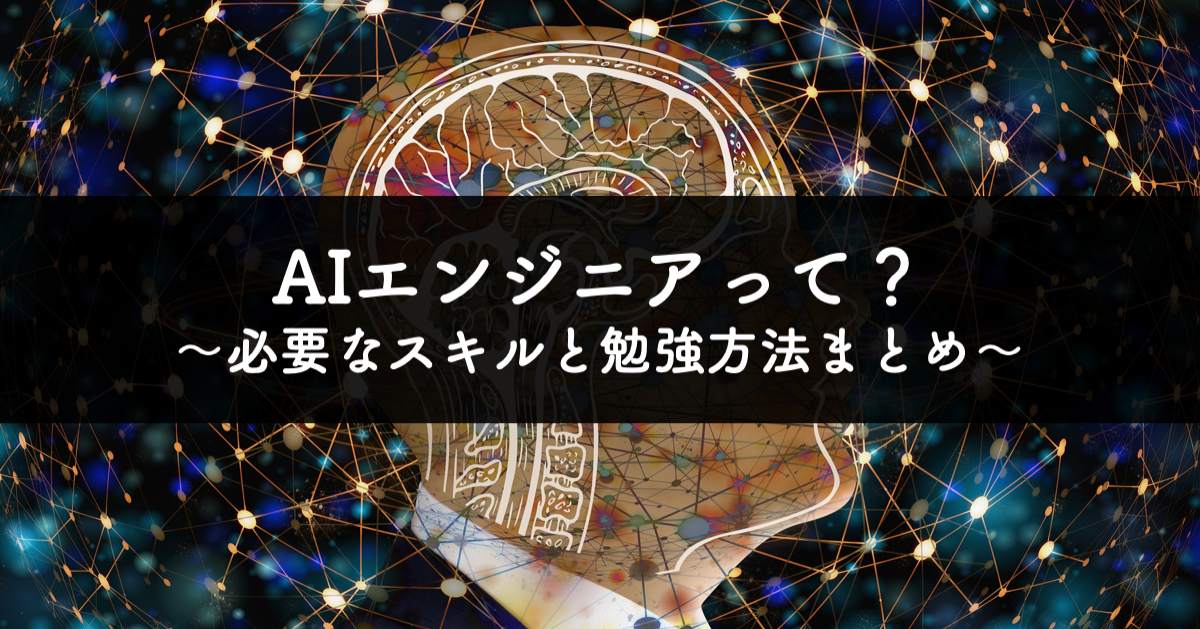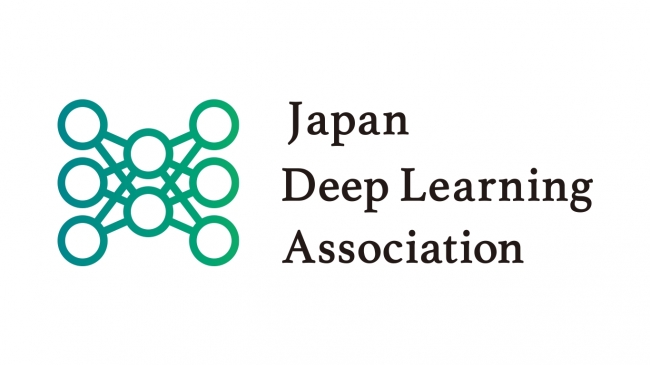株式会社Ristの遠野です。
現在は製造業・医療分野を中心として、Deep Learningを始めとした機械学習を取り入れた画像・動画解析を中心に行う事業を展開しています。
今回は「AIの未来予測」ということで、がっつりポエムなノリでこれからのAI開発はこういう方向に行くんじゃないか、というかこういう方向に行くと面白いだろうなぁっていうことを書いていきます。
生き物のように振る舞うアルゴリズム
人間でも、賢くないけど賢そうに振る舞ってると賢く見られる現象。
結局、見えない中身や過程より、見えるアウトプットが重視されるのは自然の摂理なのかもしれません。
僕はもともとが化学専攻で、社名の由来もそれに由来しているので、化学の話をします。
例えばBelousov-Zhabotinsky反応は、マロン酸と臭素酸塩を媒介とした金属イオンの酸化・還元反応ですが、反応により生成と消費される各物質の濃度が均一でないことから、図のような周期的なパターンが生まれます。
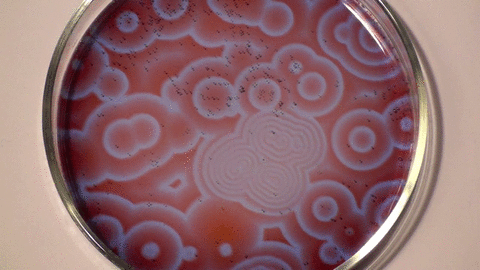
アメーバや単細胞生物のコロニーを彷彿とさせるこのようなパターンですが、ここには単に、濃度勾配と反応速度に関わるパラメータで同様の現象をシュミレーションすることができます。
詳細は省くので、以下のリンクを参考にしてください。
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Belousov-Zhabotinsky_Reaction.gif)
(http://endeavor.eng.toyo.ac.jp/~yoshino/lecture/ex_com_simulation/2009week09.pdf)
所詮はアルゴリズム
しかし上記のようなパターンは、「生物」でも「知能」でも何でもないのは明らかかと思います。
生き物らしい振る舞いだったとしても、そこに「知能」とゴーストは宿ってません。
「〇〇のときは△△をする」というルールがあるだけで、それに従った結果の出力が現れているだけです。
誤解を恐れずに言うと、第三次人工知能ブームの火付け役となったDeep Learningも、結局はアルゴリズムであって、知能からは程遠いです。
「大量のラベル付きデータ」を「多層パーセプトロンモデルに入力」し「誤差逆伝播法などに入力とラベルとの誤差をよりを減らす方向に重みを更新する」というルールに則ると、教師データと同じような振る舞いで、新しい入力を出力する。
基本的にはそんな感じです。
夢のない話に聞こえるかもしれませんが、それでもこのアルゴリズムは多次元データを扱った予測モデルを作るには強力な手法なことは間違いありません。
人の判断のような予測モデルを作成することもできますし、清く正しく使っていけば非常に有用です。
遺伝的アルゴリズムをアナログの世界へ
先ほど説明したようなアルゴリズムは、いくつかのルールによって生き物らしい振る舞いを生み出すことできるというものの一例でした。
それとは少しアプローチの異なる手法として、そう、みんな大好き遺伝的アルゴリズムというものがあります。
遺伝的アルゴリズムは、幾つかの解の候補を複数用意し、適応度の高い解を優先的に選択して、その選んだ個体に突然変異などの操作を繰り返しながら解を求めていく手法です。
分かりやすい例でいうと、ダーウィンの進化論のように、最初の起源は同じでも、その場の環境と突然変異によりそれぞれの生き物がそれぞれの環境で最適な進化を遂げるというようなイメージです。
このアルゴリズムの面白いところは、突然変異などを意図的に取り入れることで、より幅広い可能性を検討することができ、結果が良ければそれを良しとする結果至上主義である点です。
この手法はよくシミュレータ上で行われることが多いのですが、これをアナログのハードウェアに適用した研究があります。
それは1996年にイギリスのエイドリアン・トンプソンとサセックス大学の研究グループによって行われたもので、課題は「異なる音程の二つのブザーを聞き分けるチップを作る」というものです。
参考(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.29.7790&rep=rep1&type=pdf)
この課題自体はそこまで難しくなく、およそ4,000世代の進化ののちに無事タスクをこなすチップが得られましたそうですが、その最終的に生き残ったチップを調べてみると以下の奇妙な点がありました。
1. そのチップは100ある論理ブロックのうち、37個しか使っていない
2. 人間が設計した場合に最低限必要とされる論理ブロックの数を下回る数で、普通に考えると機能しない
3. 37個しか使われていない論理ブロックのうち、5つは他の論理ブロックと繋がってもいない
4. 繋がっていない孤立した論理ブロックは、機能的にはどんな役割も果たしていないはずなのに、そのどれか一つを取り除いても、回路は動かなくなってしまう
なんとも、摩訶不思議なものが出来上がってしまったようです。
どういう了見なのでしょうか。
結論から言うと、この回路では、単なる回路素子のデジタルな情報のやりとりだけでなく、電磁的な漏出や磁束を巧みに利用し機能していたようです。
いやー、アナログの世界もハックするとは遺伝的アルゴリズム恐ろしいですね。
この話は、森田真生さんの「数学する身体」を読んで知りました。
面白いのでぜひ読んでみてください。
DeepMindのAlphaGoにも利用されている深層強化学習や、のような遺伝的アルゴリズムの分野で、実用的なサービスが出来ると面白そうですね。
知能を生み出してきた目的関数と、それを用いたAI開発
「あなたの人生の目的関数は、なんですか?」
これ、知能やAIを開発する上で割と重要な話だと思ってます。
一般的に、売り上げ予測の「人工知能」なら、売り上げ予測精度の誤差を最小とするような目的関数を設定するかと思います。
ですが、売り上げ予測が得意な「人間」の目的関数は違います。
人それぞれだと思いますが、基本的には生物として「生存と自己複製を行う」という目的があります。またその目的のためには「社会的に平和に生きていく」ことが必要です。そしてそのために「お金が必要だから給料をもらう」ということが必要で、そのために「会社の売り上げを伸ばす」ことが必要なので、売り上げ予測を最大化しようと努めています。
つまり、「生存と自己複製を行うため」に必要なものとして知能を持ち、「売り上げ予測を最大化」しようとしているとも言えます。
そして、地球上に存在するいわゆる「知能」と思われるものに共通している目的関数は「生存と自己複製」だと僕は思っています。
逆に言うと、それ以外の目的関数をもつ主体は、単なる自動システムのような代物でしょう(それはそれでいいんですけど)。
ということは、実は「生存と自己複製」を目的関数とし、突然変異を一定の条件で起すような主体を設計すれば、自ずと知能が生まれるのかもしれませんね。
例えば、「生存と自己複製」を至上命題としながらも突然変異を許容するコンピュータシステムが野に放たれた場合に、迷惑を掛ける種は人間に駆逐され淘汰されますが、突然変異により宿主のパソコンの不要なデータなどを定期的に消去してPCを最適化してくれるようなシステムが残ることもあるかもしれません。そのようなコンピュータウイルスの行っていることは、生物でいう共生を営もうとする知能に近く、また何世代にもわたってより優秀なシステムのみが残されることで人間がデザインするよりも良好な作業を行うこともあるかもしれません。
このように、生存と自己複製を目的関数としながらも、進化の過程で人間との共生をデザインできるようなボトムアップ式の開発手法が、将来のAIの開発の未来となっていくような気がしています。
そして、それを生み出すのが弊社からであるように、密かに独自で研究・開発を行っていきたいなと思っています。