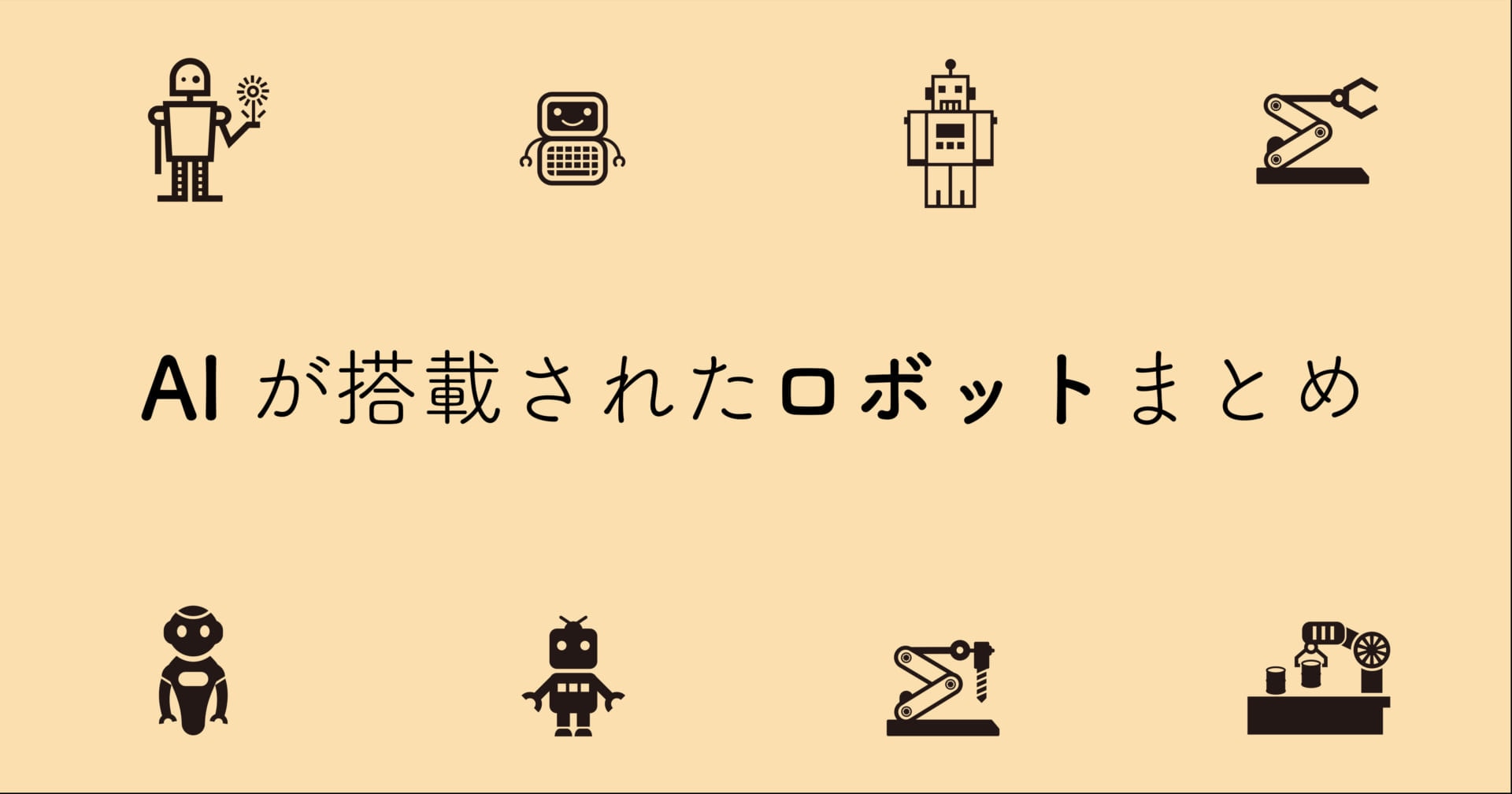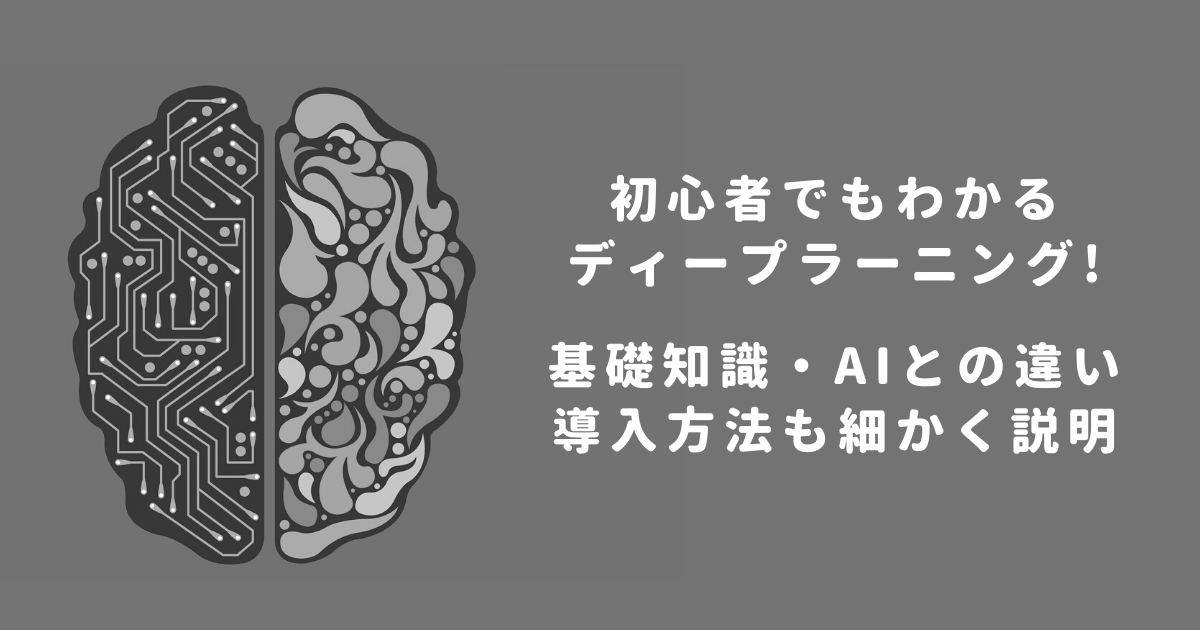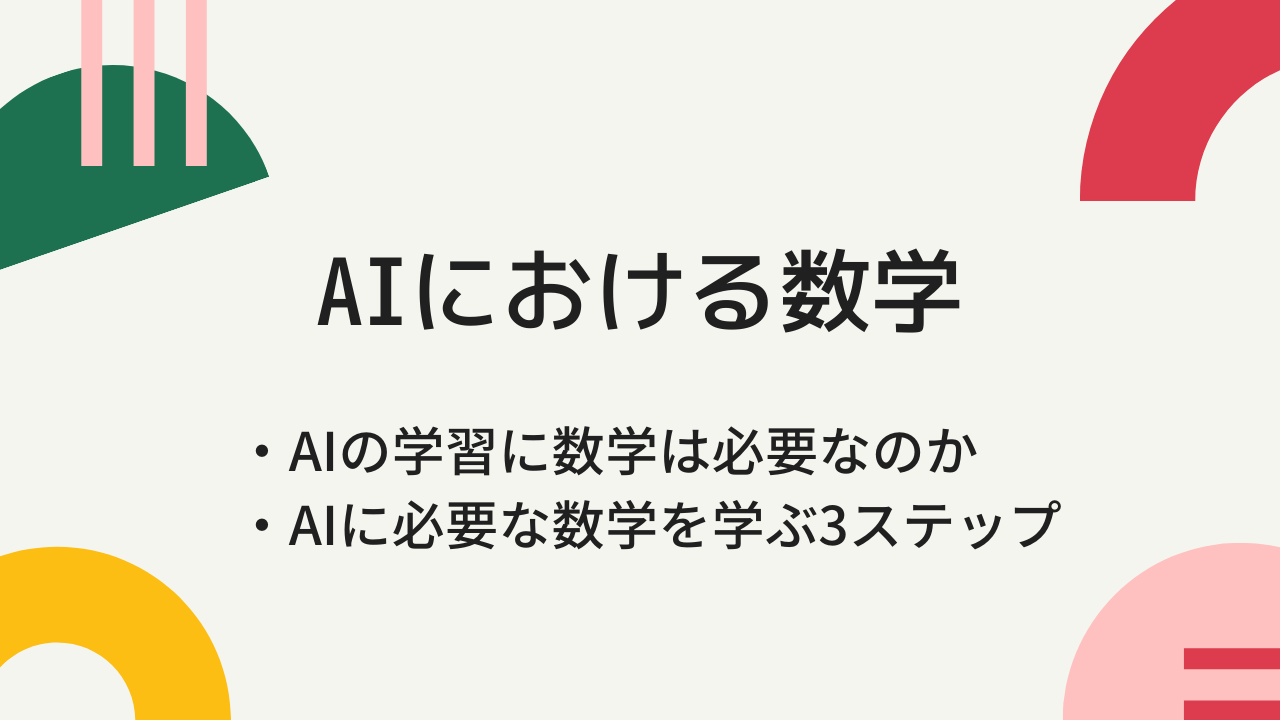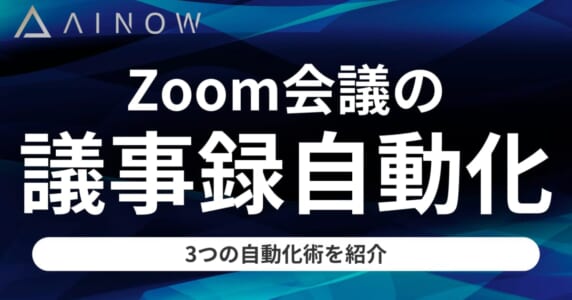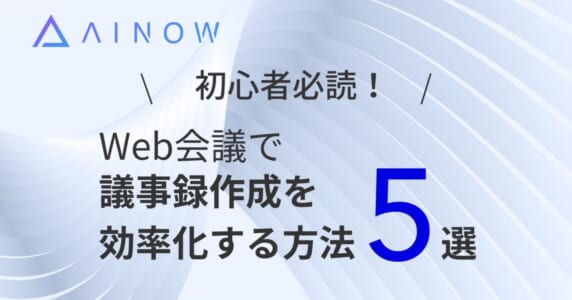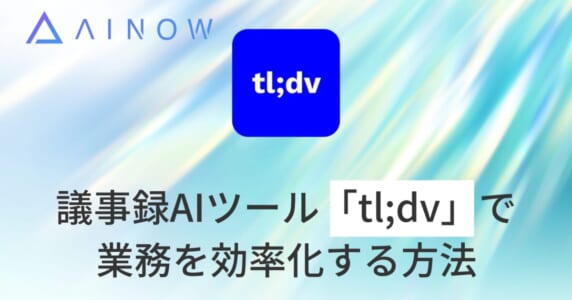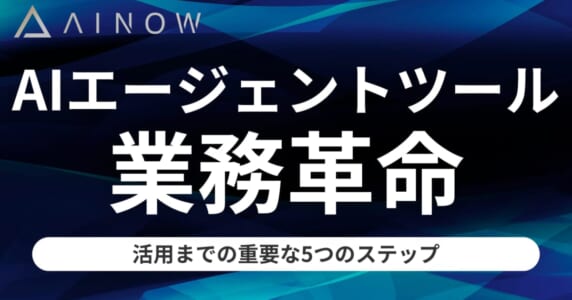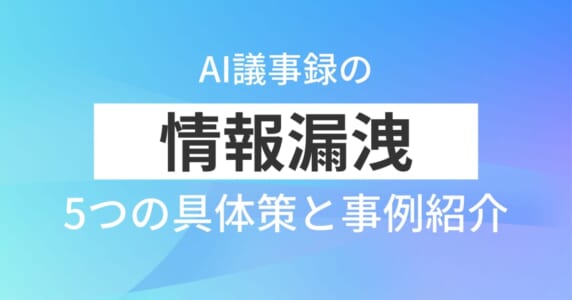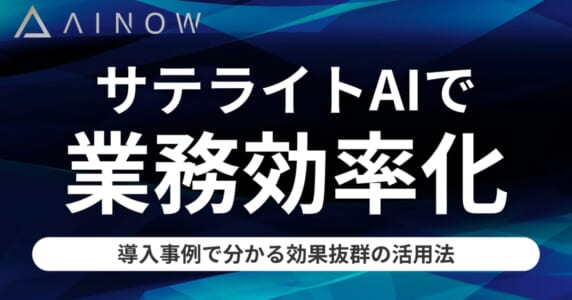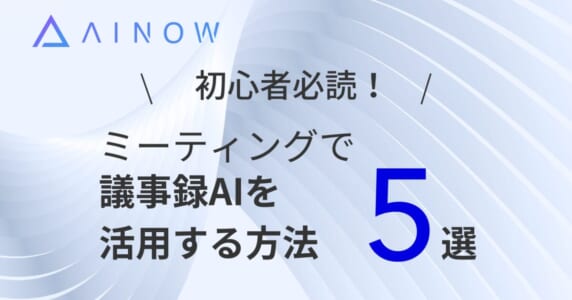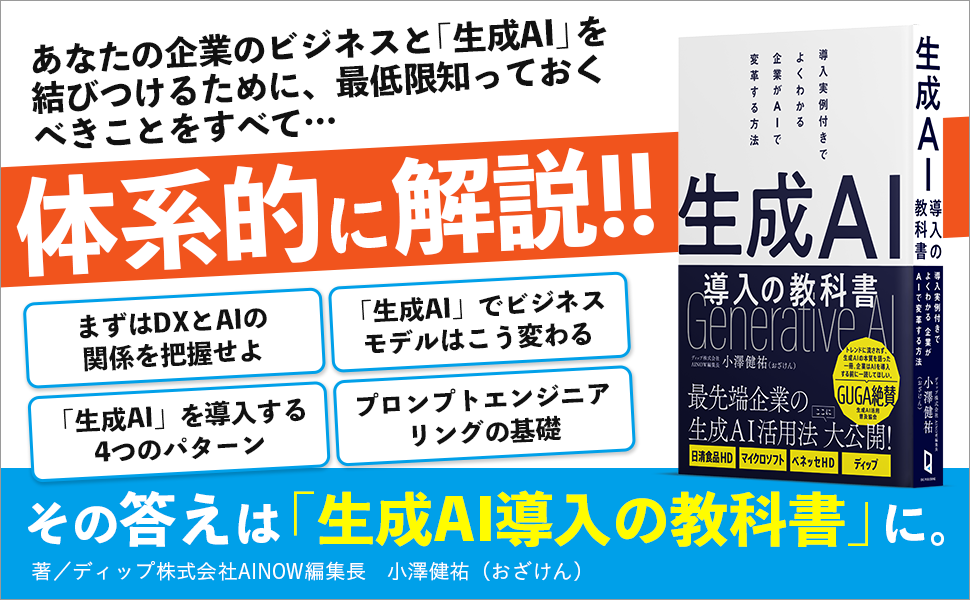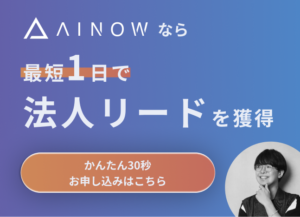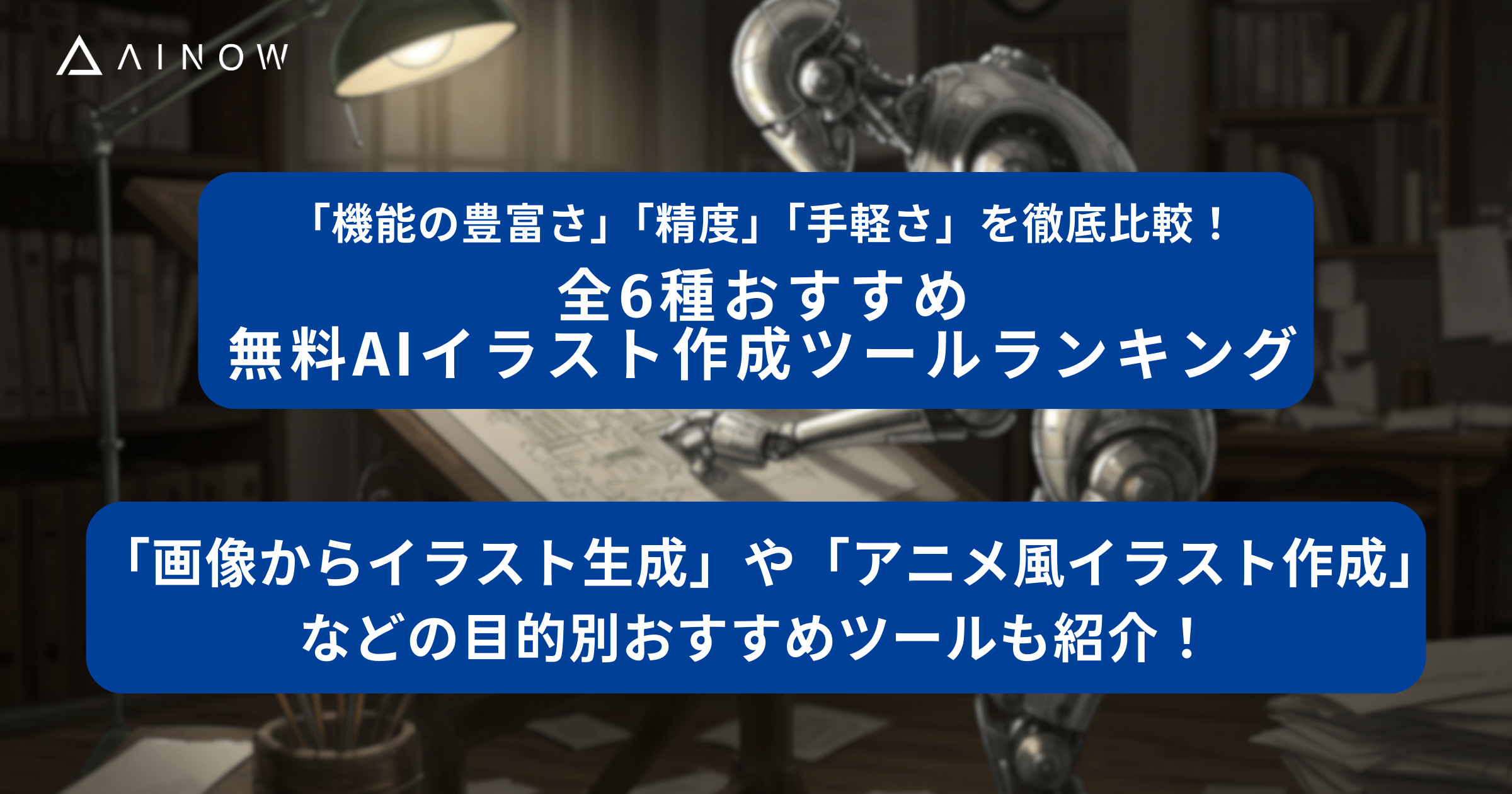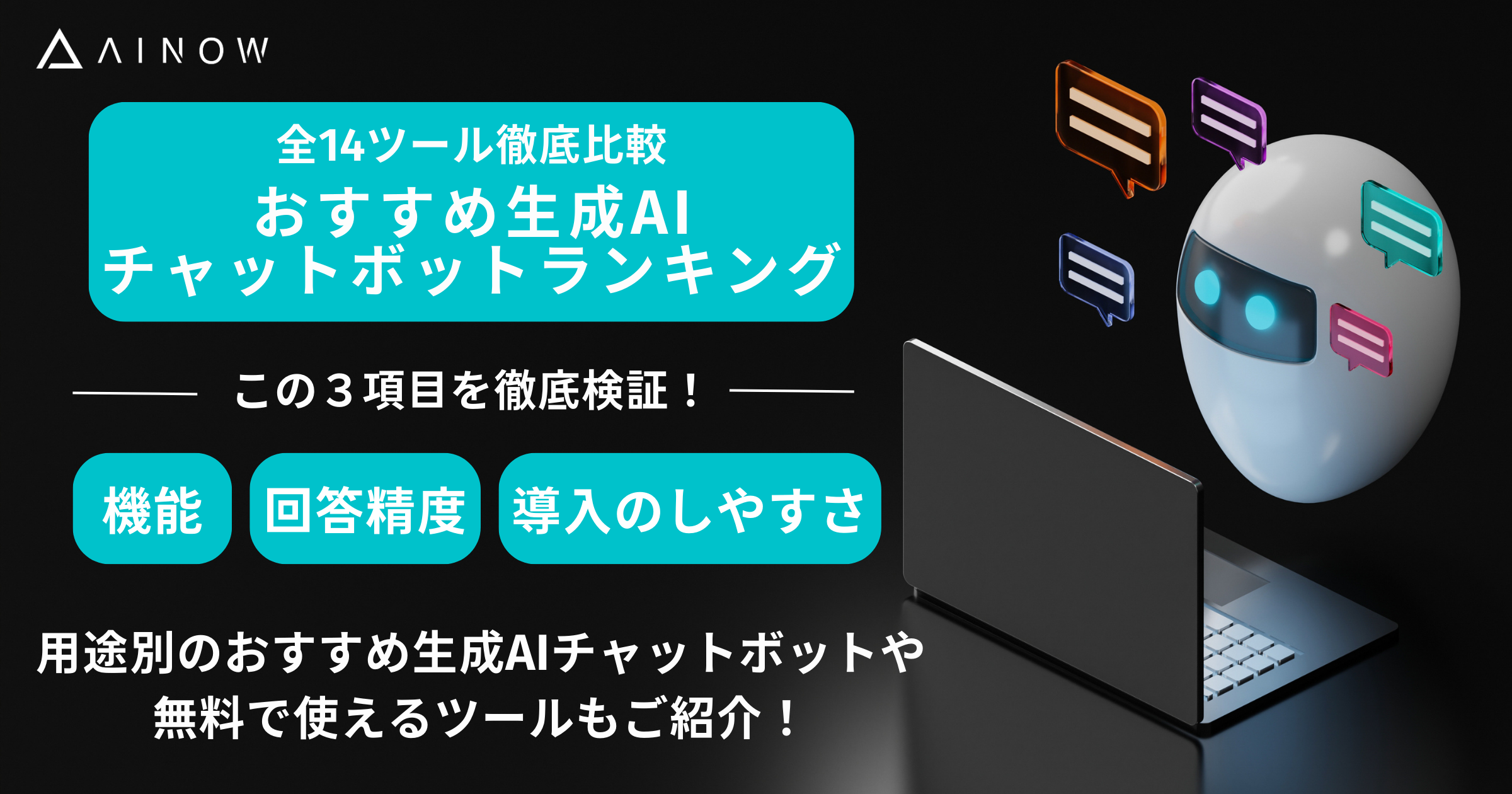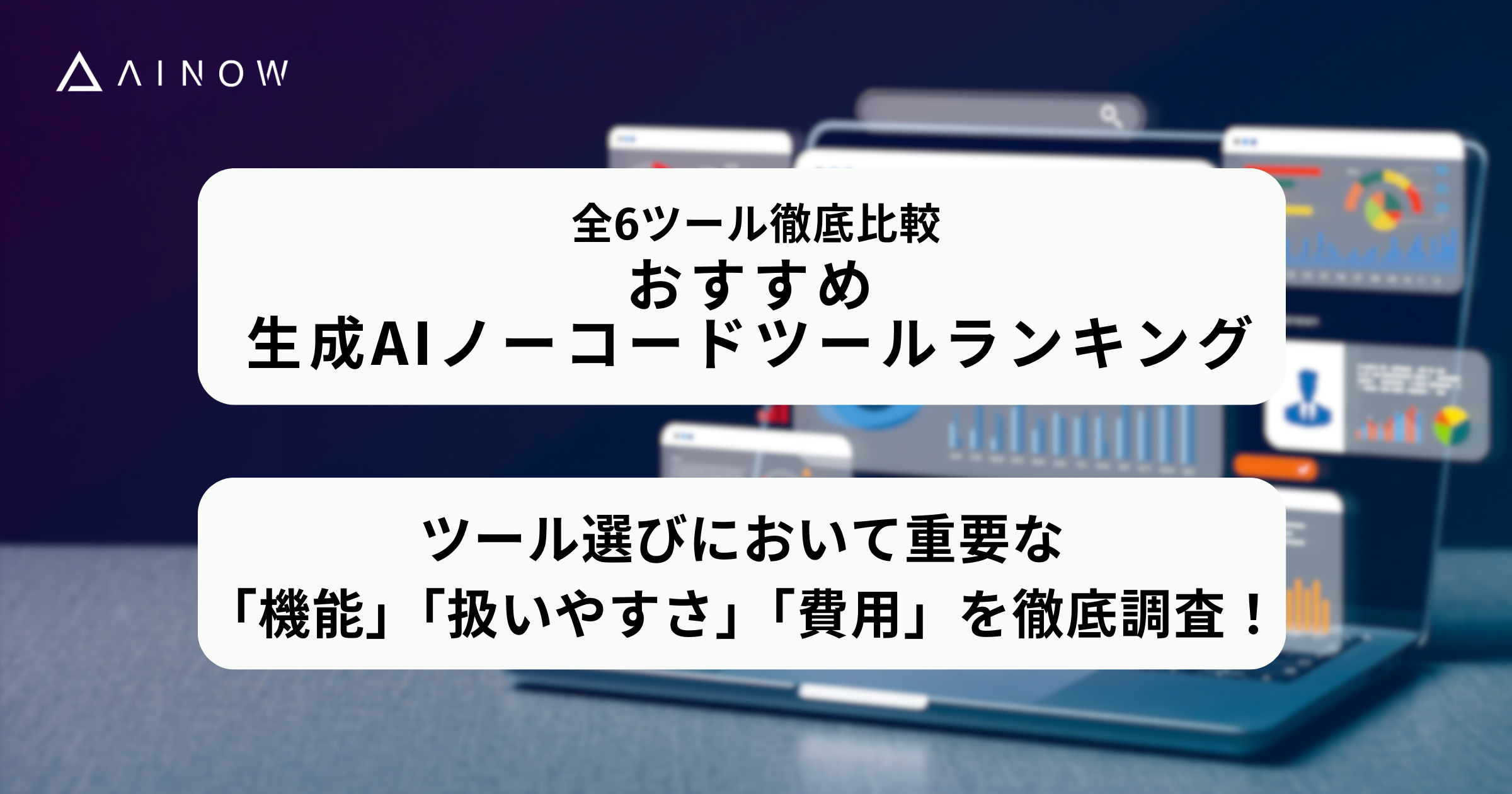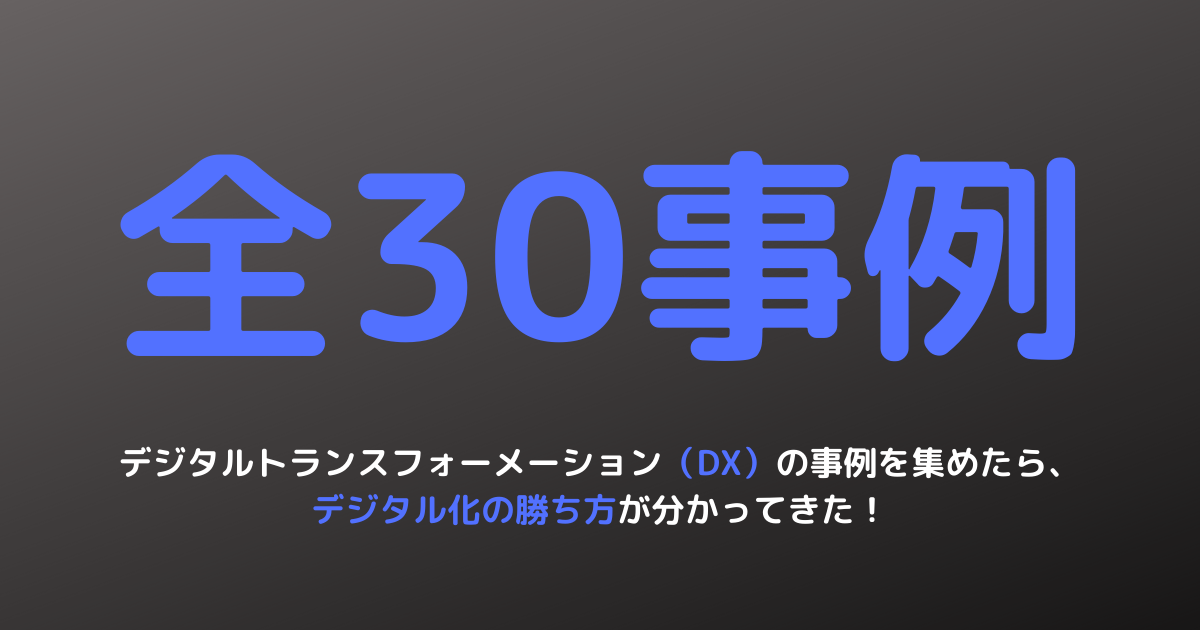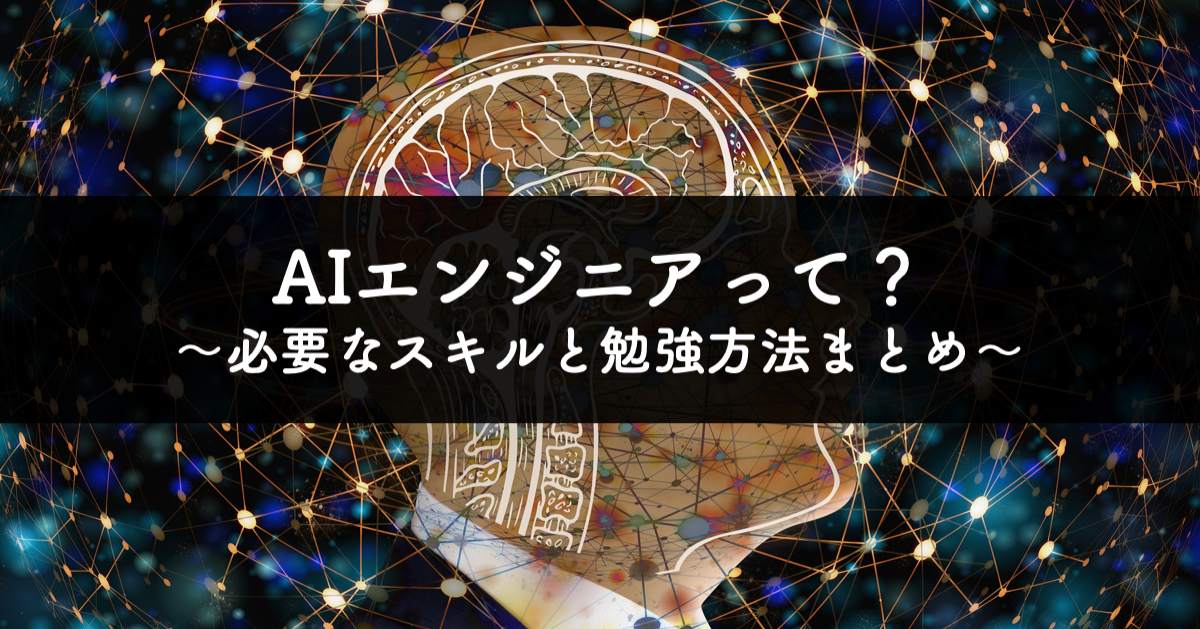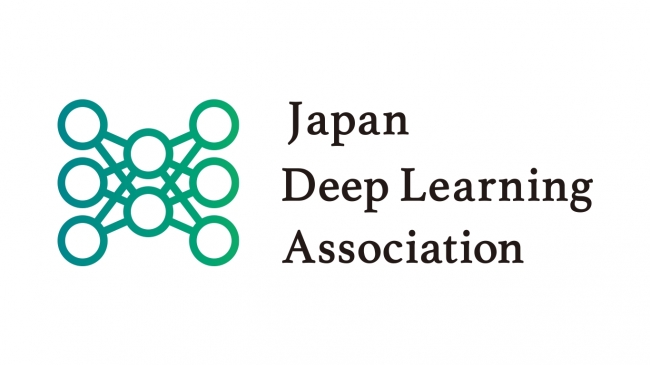2023年2月2日に渋谷ストリームホールにて、メタバースにおけるテーマごとのセッションと各企業ごとの展示会を軸とした、「MetaverseJapanSummit(メタバースジャパンサミット)2023」が開催されました。
本サミットは、web3という新しい時代の原動力が加速する今、メタバースが急激に拡大する可能性を秘めているとし、「地方創生×メタバース」を掲げ、教育、医療、SDGs、観光、スポーツなどの幅広い分野のテーマについてセッションを行いました。
デジタル技術が格段に進歩し、さらにwith/afterコロナの新たな生活様式が広がり始めた現在、主催であるMetaverse Japan (メタバースジャパン)は地域をメタバースでどう活性化し自治体とのハブを築くことを目的に、「地方創生×メタバース」の未来と課題を議論し学ぶ場を提供しました。
本記事では、サミットで行われた2つのセッションに焦点を当ててレポートしていきます。

※また、本記事では講演内容の一部割愛や表現の変更をしておりますのであらかじめご了承ください。
「メタバース×エンタメ」の熱狂的なアプローチ
「メタバースがどのように生活に関わってくるのか」という議題の重要な分野としてエンタメが挙げられます。
本サミットの概要で示した通り、観光やスポーツ、他にもゲームやライブなど既に様々なエンタメ分野がメタバースに関わっています。
「メタバース×エンタメ」の新しい形が盛り上がることでエンタメ自体が大きく変化してきています。
従来のエンタメの形としてサービスを受ける、つまり「受動的な形でエンタメのサービスを利用している状態」が、メタバースが関わることにより、「能動的な形で参加する状態」へと進化しています。
では、「能動的な形で参加する状態」へ変化するとはどのようなものなのでしょう。
それはつまり、無料or有料で自分と同じ参加者同士で共に1つのエンタメに参加するということです。
実際、どのような形で参加するかはサービスによって異なるのですが、今までの自分対エンタメという構図が自分を含めた複数の参加者対エンタメになるため、より白熱した盛り上がりになるのです。
その中には、スポーツ観戦やアーティストのライブ参加、各名所の観光などが存在し、既存のメタバース×エンタメでは既に熱狂的な盛り上がりを見せています。
その中でも本サミットで行われた「メタバース×スポーツ」と「メタバース×観光」がテーマのセッションについて紹介していきます。

メタバース×スポーツ
コロナウィルス感染拡大の影響でスポーツ業界は大きな打撃を受けてきました。そんな中、オンライン上での新たな体験の提供を可能とするメタバースの活用も注目を集めています。スポーツのあり方、ファンエンゲージメント、そして熱狂体験とメタバースの可能性について業界をリードするメンバーで議論した内容を紹介していきます。

渋谷キャストでのエアレース(スピーカー:豊田啓介)

豊田氏- メタバースとスポーツの組み合わせについては、想像がつかないところもあるかもしれません。
しかし、渋谷キャストという複合施設を設計している私たちが持っている細かい3Dデータを活用することで、面白いことができるのではないかと考えました。
例えば、バーチャル空間でエアレースを開催することができます。具体的には、自由参加型でVRチャットの中で渋谷キャストの周りを自由に飛び回ることができます。
その後は、渋谷の上空を自由に飛び回ることもできます。リアルの空間には本当にこのゲートが設置されていますが、ゲートだけではわかりにくいため、バーチャルで飛んでいるレースに名前をつけ、現地に行ってARを呼び出すことで自分のレースを呼び出すことができます。
そして自由視点で、どこから見ても自分のレースを観戦することができます。VR、AR、リアルの3つが重なり合って、お互いに連携することで、それぞれの要素を活かした新しい体験を提供しています。
この世界では、絶対リアルでは一緒に飛ぶことができない人と競争したり、「あそこで俺が、こうスタートしたんだ!」とみんなに見せながら話したりすることができます。ARで実際の渋谷に持ってきて、レースが終わると渋谷ストリームやスクランブルスクエアの上を飛び回ることもできます。
何回か飛んでいると渋谷キャストに愛着が湧き、場所や現実性を超えたストーリーの共有が可能となったり、スポーツならではの肉体感覚を体験することができるようになります。
祭典の新たな会場構想(スピーカー:早川周作)

早川氏- 私たちがフェスを開催する会場は、沖縄アリーナという1万人収容の会場ですが、B1リーグ※1に参加するためには5000人以上収容できるアリーナを用意する必要があります。
※1 B1リーグは、日本のプロバスケットボールリーグである。
しかし、私たちはこの規制が時代遅れだと考えており、1000人程度の熱狂的な会場を作って、その他の部分はWeb3の技術とメタバースを活用して熱狂を伝えられるのではないかと考えています。
アスティーダ※2トークンやWeb3を組み合わせることで、VRからメタバースまで含めた技術を用いて熱狂を伝えることができるようになるでしょう。
※2 アスティーダは、沖縄県を本拠地とする日本の卓球チームである。
このような技術はますます進歩すると思われますが、その際に無駄な箱を作るのではなく、Web3やトークンを活用したり、メタバースを利用したりすることが大切だと思います。
スポーツを超えた新しい体験の可能性(スピーカー:早川周作)
早川氏- 渋谷キャストを舞台にしたエアレースをはじめとする、メタバースとスポーツの組み合わせは、新しい体験の可能性を広げています。
地方創生や競技や観光など,、他の分野との連携も重要です。また、リアルな場所とバーチャル空間を結びつけ、掛け算的な思考に基づいた循環型のモデルを作り出すことが求められています。
Web3の技術を活用することで、誰もが様々なスポーツを楽しめる新しい時代が到来するでしょう。
野球観戦の形がメタバースによって変わる(スピーカー:佐藤晃司)
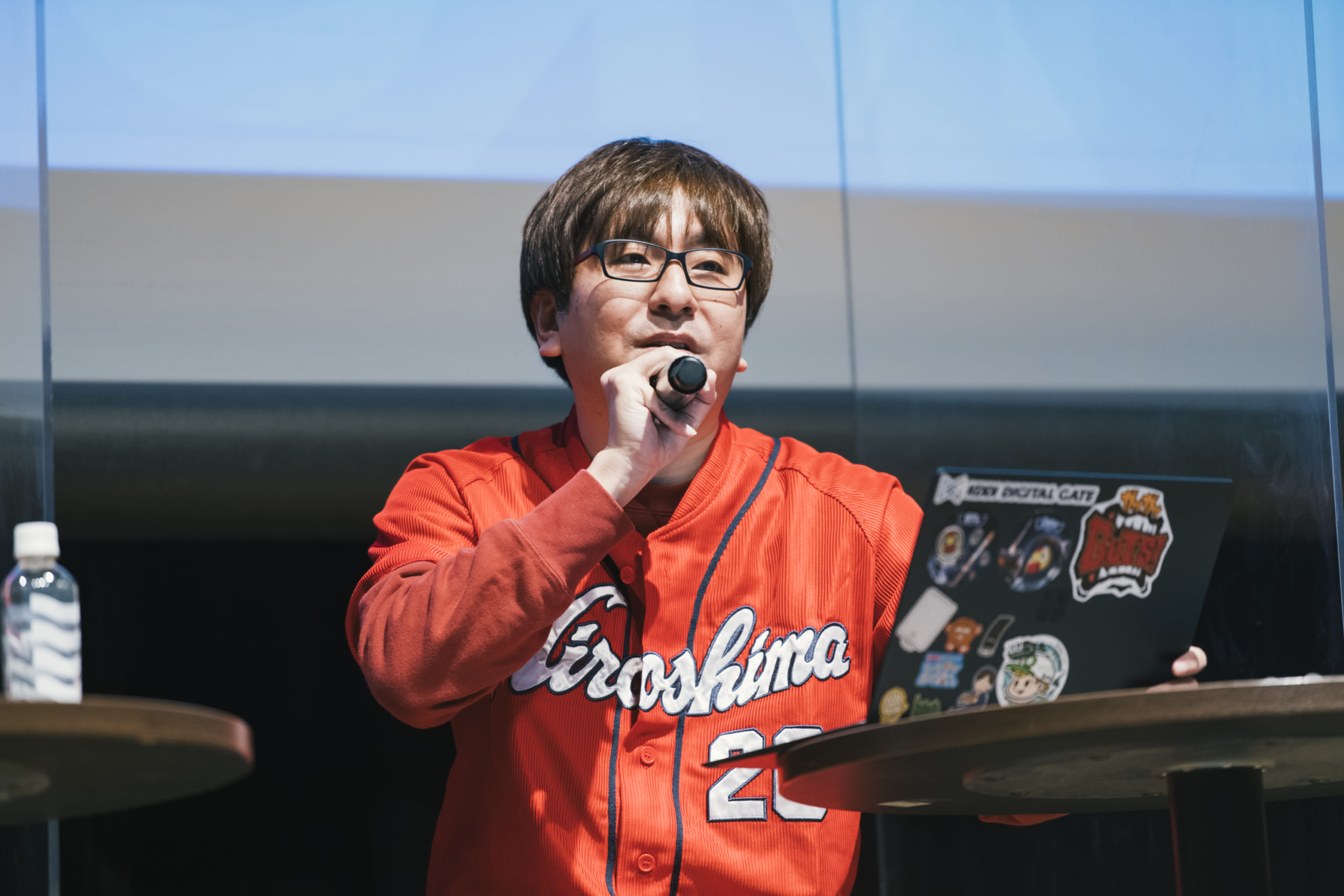
佐藤氏- 広島県では、広島東洋カープが非常に熱狂的なファンを獲得していることは皆さんご存じだと思います。
そして、野球やその他のスポーツなどは現地に行って応援することが1番のスポーツの良さだと思います。
メタバースやファントークンなどは、現地に行って応援するほか、例えば投資目的や他のファンとの交流目的など、違ったアプローチが可能です。
それにより、より深いファンが増えたり、違ったコミュニティが出来たりする可能性があり、その部分にも期待しています。
メタバースジャパンには、多くの企業が参加していると思いますが、メタバースで費用対効果が出るためには、目的を明確にして、どのようなものを作っていくかをしっかりと考える必要があります。
多くの企業がこの問題に悩んでいると思われますが、我々は広島県からの補助金を受け取り、色々な試みをすることができました。
その結果、メタバースの得意な部分と不得意な部分が明確になりました。不得意な部分については諦め、得意な部分だけに注力し、比較的安価で作ることに力を入れています。
メタバース上の見た目よりも、参加者全員が熱狂できるような取り組みに絞り、費用対効果を高めることを目指しています。
メタバース×観光
現在では、あらゆる体験やサービスがリアルからオンラインに切り替わり、その場にいるような没入感を得られるメタバースを活用して観光を楽しむサービスも増え、いつでもどこでも世界中を旅することができます。
地域が主体となってメタバースを観光に取り組もうとする動きは世界でも加速し、さらに関係人口の増加や経済活動にも寄与できる可能性を秘めており、地域の魅力をどうメタバースで伝え、さらにリアルとの連携の可能性について議論した内容を紹介していきます。

メタバースやWeb3が文化と産業を変える(スピーカー:金山淳吾)

金山氏- まず、Web3やメタバースといった新しい技術が、どのように文化となり、産業になっていくかを整理したいと思います。
技術的なイノベーションは、世の中に先行して出ていくものであると考えており、まさにメタバース、AR、VR、Web3、ブロックチェーンといった技術は、現在そのような段階にあると思います。
これらが良い具合に混ざり合い、実用化していくことにより、文明的になってくるのではないでしょうか。
文明の上に文化が成り立ち、文化が産業になると考えています。メタバース、AR、VRなどは、まだ技術だけが存在しているに過ぎないと思われます。
現在、これらをどのようにフォーマット化し、文明化し、文化を育んでいくかが、各地で考えられている段階だと思います。
渋谷のメタバースとARプロジェクト(スピーカー:金山淳吾)
金山氏- 渋谷は、さまざまな取り組みの中でも先駆的な存在です。例えば、2019年には「渋谷5Gエンターテインメントプロジェクト」というコンソーシアム※3を立ち上げました。
※3 複数の企業が「共同企業体」を組成して、一つのサービスを共同で行う取引である。
当初は、AR、XR、MRのプロジェクトの開発を行っていましたが、2020年、新型コロナウイルスの影響を受け、バーチャルリアリティで街の可能性を研究する「バーチャル渋谷プロジェクト」がスタートしました。
VRやARといった言葉を聞くと、デジタルコンテンツや映像、画像、キャラクターが想像されるかもしれません。しかし、私たちは音声ARのプロジェクトにも取り組んでいます。
このプロジェクトは、渋谷拠点の企業であるDJラボさんと協力して行いました。具体的には、明治神宮の歴史や渋谷の歴史をマッピングし、音声AR技術を使って観光インフラとして活用する「サウンドマップ」というソリューションを実装しました。
街中には、ARのコンテンツやアート、サインなどを自由に貼り付けることができるプログラムがありますが、私たちはこれを実験的に導入し、どのように活用されるか、どのように公共の財産になるかを研究しています。
渋谷の取り組みと可能性(スピーカー:金山淳吾)
金山氏- 渋谷には、実を言うと観光資源がほとんどないように感じます。もちろん、ビルの再開発によって新たな名所が生まれることもありますが、渋谷の観光スポットとしてよくリストアップされるのは、ハチ公像やスクランブル交差点、代々木公園などです。
しかし、これらのスポットはほとんど経済的価値を生み出してはいないと考えられます。代々木公園は無料で入場可能で、スクランブル交差点は無料で渡れて、ハチ公像での写真撮影も無料です。
そこで、新しいテーマパークや遊園地を作って、それを観光資源として利用することを考えたとしても、土地が不足しているため難しいと思われます。
そこで、一般の商業施設だけでなく、Web3やメタバースなどの技術を活用して、観光テーマパークを作ることが必要かもしれません。例えば、多くのアーティストがUGC(ユーザー生成コンテンツ)のレイヤーに、様々なテーマパークコンテンツを設け、そこで課金して経済を生み出すようなビジネスモデルが考えられます。
現在、株式会社クラスターさんと共同で取り組んでいるバーチャル渋谷のようなVR空間は、そのプロモーション用の空間として活用できるかもしれません。具体的には、VR空間で面白そうなレイヤーを見つけた人が、実際に町に来て、お金を払って体験することができるようなエコシステムを作ることができるかもしれません。
こうした取り組みが実現すれば、渋谷の観光も大きく盛り上がることでしょう。
「バーチャル大阪」プロジェクトについて(スピーカー:林真史)

林氏- 現在、「バーチャル大阪」というプロジェクトに、大阪府と大阪市が取り組んでいます。2025年に大阪で開催される予定の万博に向けて、都市の魅力を発信することがテーマの1つです。
私自身は、大阪ヘルスケアパビリオンを出店する責任者として、大阪万博に参加しています。パビリオンを検討している際に、有識者からバーチャルの活用を提案されたことが始まりでした。
昨年度に「バーチャル大阪」を作成し、いくつかのイベントを開催しながら、徐々にエリアを拡大しています。まだ新しいプロジェクトですが、今後は「バーチャル大阪」を活性化して、皆さんにバーチャル空間を楽しんでいただき、実際に大阪に訪れていただけるような仕組みを目指しています。
大阪には魅力的な場所がたくさんあります。そうした魅力を発信したいと思って、バーチャル大阪というプロジェクトを立ち上げました。イベントなどを通じて、様々な人々がバーチャル大阪に入って体験していただいている実感はありますが、イベントがない時はお客様に入っていただけていないという課題があります。
そのため、バーチャル大阪をより発展させ、実際に体験していただけるような仕組みを作り、現実の大阪にもお越しいただけるようにしたいと考えています。
Web3とメタバースに対する国の取り組み(スピーカー:中平公土、黒田玄)

左:中平氏、右:黒田氏
中平氏 – 文部科学省では、文化と経済の相互作用によって高い循環を生み出すことを目指しています。具体的には、文化が経済的な価値を生み出し、その利益が文化自身に還元されることで持続可能性を高めることを目指しているということです。
そのため、デジタル技術の活用に注力しています。特に、メタバースを活用することで、文化と経済の相互作用を促進できると考えています。
したがって、文化・芸術基本法に基づき、日本における文化技術の推進を計画しています。具体的には、デジタル技術を活用した文化技術活動の推進を含めた計画です。NFTを活用した創作取引や、メタバースにおける創作家等の良好事例の活用を図るための方策を検討しています。
黒田氏 – 文部科学省では、省内横断の業務の枠を超えて、メタバースの活用について勉強会を開催し、将来的にメタバースが本当に世界に実装されるときに、政策を立案することを支援しています。
メタバースにおいては、ARとVRに分けられます。VRの場合、3次元の仮想空間で身体性を伴いながら現実に近い交流ができることが楽しみの一つで、運用者が持続的にイベントを作り続けるシステムを確保するために、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を確保することが非常に重要です。
ユーザーが自発的に集まり、そのような活動がメタバース内で引き起こるような、ステージの確保などを探ることで、メタバースの活用の可能性があると思います。
メタバース×エンタメの今後の展望
メタバースとエンターテインメントは非常に相性が良いと言えます。メタバースでは、現実の制約を受けない自由な空間で、様々なエンターテインメントを行うことが可能です。
さらに、メタバースは単なる娯楽空間に留まらず、教育やビジネスの分野でも活用されることが期待されます。例えば、リモートワークやオンライン教育において、メタバースを活用することで、より効率的なコミュニケーションが可能になるでしょう。
また、ビジネスの分野では、商品の展示や販売を行うことができるようになるため、新しいビジネスモデルの創出も期待されます。
メタバースはエンターテインメントや観光だけでなく、様々な分野で活用が期待される技術です。今後ますます普及していくことが予想されます。
まとめ
多く認知されているメタバースは、ゲームやコンテンツを個々で楽しむようなものを想像していたと思うのですが、今回の「メタバース×エンタメ」では、現実のエンタメをバーチャルであるメタバースを利用して大々的にさらに盛り上げて行くことが設計されています。
これらは、メタバースという社会的に新しいプラットフォームが完成しつつあると思われ、メタバースを通じて新しい趣味や観光、コミュニティなど幅広い分野で使用されていくでしょう。
このメタバースの波に乗り遅れないよう、常に社会と技術の進歩を俯瞰し情報収集することが必要でしょう。